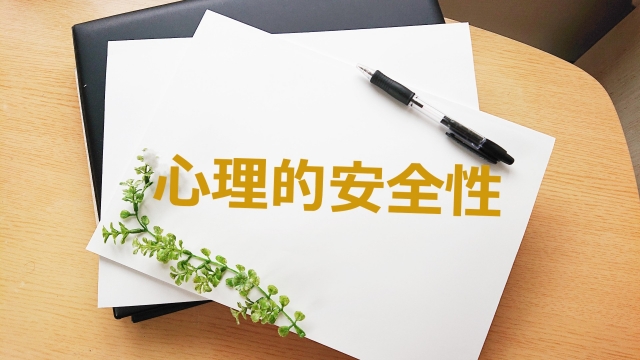医療現場で「心理的安全性」という言葉が注目されるようになりました。
心理的安全性が高い職場と聞いてイメージするのは、誰でも意見が言いやすく、皆がのびのび仕事ができている職場を思い浮かべます。
しかし、医療機関における心理的安全性は、
- ペイシェントハラスメントの早期共有
- 職員の孤立やメンタル不調の予防
- 管理職が安全配慮義務を果たすための基盤
としても機能する実務上きわめて重要な概念です。
本記事では、「心理的安全性」を単なる職場の雰囲気づくりやコミュニケーション論としてではなく、医療機関においてペイシェントハラスメント対策や安全配慮義務を機能させ、離職リスクを下げるための“実務基盤”として整理します。
管理職・医療安全担当者が現場対応に悩む背景には、制度やマニュアルを作る以前に、そもそも「声が上がらない・共有されない」といった職場構造が存在します。
心理的安全性は、その構造を変えるための出発点なのです。
心理的安全性とは?
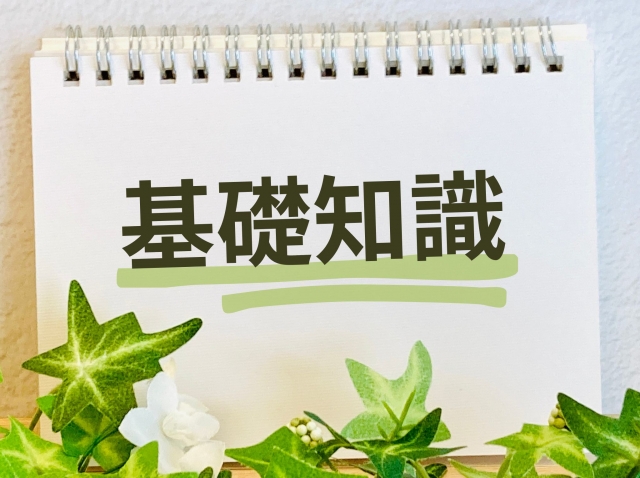
心理的安全性の定義
心理的安全性とは、「対人関係のリスクをとっても安全であると思うこと」と定義されています。
日本人の多くは、問題点に直面しても対人関係の摩擦を恐れ、問題点の指摘や改善の提案を避ける傾向があると思います。
心理的安全性が高い職場においては、問題点の発見と改善が進みやすく、学びの機会が得られることから、生産性が高まると言われています。
ハーバード大学のエドモンドソン氏が研究を発展
心理的安全性に関する研究を発展させたのは、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・C・エドモンドソン氏と言われています。
職場のパフォーマンス向上の要因は、従来、職場環境や賃金制度などのハード面が注目されていました。
それに対しエドモンドソン氏は、職場の対人関係などのソフト面が職場のパフォーマンス向上の要因になると提言しました。
医療過誤の調査から心理的安全性の重要性に気づく
そもそもエドモンドソン氏が心理的安全性の重要性に気づいたのは、病院における医療過誤の頻度の調査を行ったときと言われています。
その時の調査では、「インシデントの報告数」と「チームの開かれた雰囲気」に相関性があることが分かりました。
つまり、優れたチームほど、積極的にインシデント報告を上げ、チーム内で情報共有を図り、改善に向けた議論を行っていることがわかったのです。
Google社の「プロジェクト・アリストテレス」で脚光
心理的安全性の考え方は日本の企業にも広く取り入れられています。そのきっかけになったのが、Google社が行った「プロジェクト・アリストテレス」という調査でした。
この調査は、効果的な職場の条件を探ることを目的に、2012年から4年にもわたり200弱の職場を対象に行われた一大プロジェクトと言われています。
Google社が示す”効果的な職場で重要度が高い5つの要因”
このプロジェクトの分析結果から、効果的な職場において特に重要度の高い条件として示されたのが、心理的安全性を含む以下の5つの要因でした。
- 心理的安全性
対人関係のリスクをとっても安全と思えること - 相互信頼
メンバー同士が信頼し合っていること - 構造と明確化
チームの目標達成に向けたプロセスが設計されていて役割が明確であること - 仕事の意味
メンバーが仕事に目的意識を感じること - 影響度
自分の仕事に重要性を感じていること
「プロジェクト・アリストテレス」でわかったことは、高い成果をあげるチームの最大の共通点が「心理的安全性」だったことです。
Google社は、メンバーが安心して発言でき、失敗や疑問を共有できる環境こそが、イノベーションや生産性向上の鍵になると結論づけています。
なお、心理的安全性の考え方を医療現場で実際に機能させるには、管理職による指導・評価・叱り方の設計が欠かせません。具体的な実務対応については、以下の記事で詳しく整理しています。
▶ 心理的安全性を阻害しない評価・指導・叱り方― 医療機関管理職が誤解しやすいポイントと実務対応
医療機関における心理的安全性は「医療安全」と「労務リスク管理」の基盤

「医療安全」は現場スタッフの心理的安全性確保で維持される
医療現場こそ、心理的安全性の確保は極めて重要な課題です。
医療現場では、医師を中心に看護師やコメディカルなどの多職種が、性別、経験年数など様々な属性の人間が集まって一人の患者の治療を進めます。
心理的安全性が確保されていない医療現場で考えられるのは、例えば、明らかに誤った医師の診療上の指示に対して、周りの医療スタッフが疑問に思っていても誰も意見が言えず、治療が進んでしまうリスクがあります。
前述した“インシデント報告数とチームの開かれた雰囲気に相関関係があった”という調査結果からも、医療現場における心理的安全性の重要性に気づかされると思います。
「労務リスク」は医療現場の心理的安全性欠如から生まれる
さらに、患者や家族からの著しい迷惑行為に対しても、職場の心理的安全性が欠けると、対応に困っていても声を上げられない、理不尽な要求を受けても我慢してしまう、といった状況を作ってしまいます。
こうした状態が続くと、ペイシェントハラスメントの見逃しや、職員のメンタル不調、さらには安全配慮義務違反と評価されるリスクにもつながりかねません。
逆に、心理的安全性が確保された職場では、「困った」「危険だ」「一人では対応できない」という声が早い段階で院内に共有されるため、円滑な組織的対応が可能になります。
心理的安全性は単なる“感情論”ということだけではなく、「医療安全」と「労務リスク管理」を下支えする重要な“実務基盤”と言えるのです。
実際の医療現場では、心理的安全性という“実務基盤”の上に、具体的な初動対応や体制整備が積み重なります。
▶ ペイシェントハラスメントにどう対応する? 医療機関が押さえるべきリスク管理と対応策
職場の心理的安全性をチェック!

ここでは、職場の心理的安全性を確認するためのチェックリストを紹介します。
以下のリストで、心理的安全性が高い職場か、低い職場かを別々にチェックすることができます。
管理職だけではなく、スタッフ全員がチェックを行うことが望ましいでしょう。
立場や個人によって回答が異なると思いますので、回答者同士で話し合いを持つことができれば、職場改善の一歩となるかも知れません。
引用:伊達洋駆著「60分でわかる!心理的安全性超入門」(技術評論社)
「心理的安全性が高い職場」のチェック項目
以下の項目に当てはまるものが多いと、「心理的安全性が高い職場」と言えます。
心理的安全性が高い職場
☐ 職場では問題点を提起できる
☐ 職場では、メンバー同士で故意に努力を損ねることはしない
☐ 自分の能力は職場で適切に評価され、活用されていると感じる
「心理的安全性が低い職場」のチェック項目
以下の項目に当てはまるものが多いと、「心理的安全性が低い職場」と言えます。
心理的安全性の低い職場
☐ 職場では、失敗したら悪く思われる
☐ 職場において、異質なメンバーが拒絶されることがある
☐ 職場では、他のメンバーに助けを求めにくい
心理的安全性の向上がもたらす4つの効果

心理的安全性の向上が、職場にどのような効果をもたらすのか。以下の効果が考えられそうです。
心理的安全性の向上がもたらす4つの効果
- 心理的安全性向上による医療ミスの減少
- 医療チームのパフォーマンス向上
- 医療従事者のストレス低減と離職率低下
- 改善が行われやすい組織文化の醸成
それぞれ簡単に解説していきます。
効果1:心理的安全性向上による医療ミスの減少
医療安全の分野では、インシデントから多くの学びを得ていると思います。
心理的安全性が高く、インシデント報告がしやすい職場であれば、その部署に限らず院内全体でインシデントに至った経緯などの情報共有が進み、改善活動が行われることで、どのスタッフも同様のミスを犯す可能性が低下します。
効果2:医療チームのパフォーマンス向上
同じチームや部署のメンバーが気兼ねなく話せることで、新しいアイデアが生まれやすく、チームのパフォーマンス向上に期待ができます。
効果3:医療従事者のストレス低減と離職率低下
自分の意見が否定される心配が減りますので、業務上のストレスが軽減され、いきいきと業務に励むことができます。
チーム内のコミュニケーションが活性化され、メンバー同士の信頼関係が醸成されます。
医療機関でも近年多くみられるメンタル不全での休職者の減少や、経営課題でもある離職率の低下が期待できます。
効果4:改善が行われやすい組織文化の醸成
自分の声が組織の改善に活かされれば、それが自信に繋がりまた次の改善行動につながります。
個人の意見が職場改善に活かされることを組織全体が認識するようになれば、改善が行われやすい組織文化の醸成につながります。
心理的安全性を高める医療現場向け研修の意義と内容

医療現場で心理的安全性を定着させるには、日常業務での気づきだけでは難しいと考えます。
そのため、定期的な研修を設定し、体系的な学びを通して職場に浸透させていくことが有効です。
心理的安全性向上研修の意義
- 専門家からの理解促進
-
専門家もしくは自院担当者からの研修を通じて、スタッフは心理的安全性の定義や重要性を体系的に理解できます。
例えば、「チーム間で失敗を報告しても非難されない」環境の重要性などを、組織やスタッフ同士の共通認識として浸透させることができます。 - 事例を通した学び
-
演習やケーススタディを通して、医療現場での実際のコミュニケーションの課題やスタッフ間に生じる関係の質の問題を自ら体感でき、改善につなげることができます。
研修プログラムに含むべき内容
- 基礎講義
-
「心理的安全性とは何か」「なぜ重要か」を整理して体系的に学びます。
インシデント報告の促進が、自分自身や組織全体の医療ミスの再発防止につながるという視点も重要になります。 - 演習とロールプレイ
-
シミュレーション型の研修では、心理的安全性が担保された環境で対話スキルや関係構築力を養い、実際の医療現場で使える具体的なスキルとして定着させます。
- 継続的評価と振り返り
-
研修後も前掲した職場の心理的安全性チェック項目などを利用して職場環境を測定し、定期的な改善とフォローアップを行う仕組みを取り入れると、より効果的です。
成功事例に学ぶ心理的安全性向上の取り組み
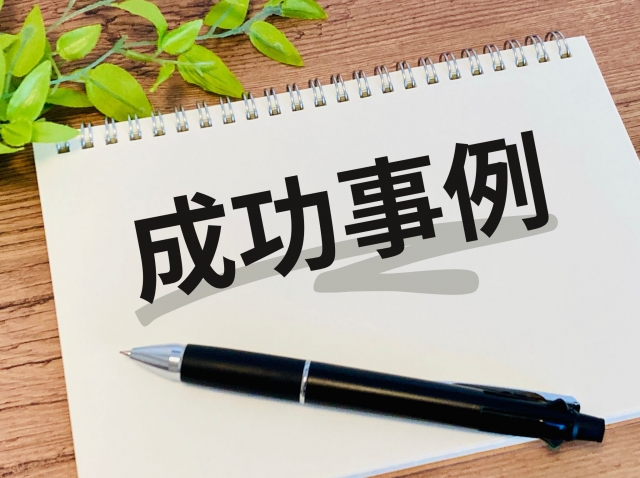
取組事例①:香川医療生活協同組合・高松平和病院
始めに、2023年7月21日の日経ヘルスケアon the webのテーマ「あなたの職場の『心理的安全性』は高い?」で取り上げられた香川医療生活協同組合・高松平和病院の事例を紹介します。
【事例医療機関】香川医療生活協同組合・高松平和病院(香川県高松市、123床)
- 同院では、2020~2021年に人間関係のもつれなどから複数の職員の退職が相次いだ
- この問題に対応するために、「気兼ねなく意見を出せる職場の雰囲気作り」に着手
- 2022年度病院目標に「情報発信と情報共有・心理的安全性の構築」という言葉を入れ、浸透を図る
- 全職員250人を対象に、チェックリストを使って心理的安全性の現状を把握
- 取組の効果は「インシデント・アクシデントレポート」が職員に定着したこと
※2021年度600件→2022年度700件に提出数増加
※医師からの提出ほぼゼロ→約9%が医師からの提案に - コロナ対応時には、部署の垣根を越えて助け合い、職場では感謝の言葉が飛び交った
取組事例②:医療法人社団おうちの診療所
次に、「心理的安全性AWARD 2025」でゴールドリングを受賞した医療法人社団おうちの診療所の事例を紹介します。
【事例医療機関】医療法人社団おうちの診療所(東京都目黒区・中野区)
- 患者の「人生の最期」に関わる職場において、患者の意思決定支援で必要なのが、「職種間に壁がなく、なるべく多くの人が患者の価値観や支援について意見を出せる環境の確保」だった。
- 株式会社omnihealによる「心理的安全性・関係の質研修」を導入し、組織内に“関係の質チーム”を結成。多職種がフラットに意見交換できる環境を整備。
- 「心理的安全性7つの指標」(後述)を用い、定量的に推移を追って見える化することで、定期的な心理的安全性の測定による継続改善を実現。
- 週5日のうち1日を診療ではなく、対話・コミュニケーションに専念する「コミュニケーション特化日」を導入し、スタッフ同士の関係性を深める時間を確保。
- 組織のビジョンや価値観を共有・深化させる機会として、半年に一回「関係の質DAY」を開催。ワークショップ形式で“will・can・must”を考え、行動指針へ反映させる取り組みを実施。
- 「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」といった心理的安全性の要素をワークを通じて体感し、「助けてと言える」「頼れる雰囲気」を築く工夫を導入。
- 具体的な指標達成
※離職率の低下
※診療の質の維持
※常勤医師・看護師の直採用率100%の達成など
引用:株式会社omnihealが「心理的安全性・関係の質研修」を提供する医療法人社団おうちの診療所が「心理的安全性AWARD2025」にてゴールドリングを受賞 | 株式会社omnihealのプレスリリース
事例医療機関である医療法人社団おうちの診療所が、定期的な効果測定の指標として取り入れた「心理的安全性7つの指標」とは、前掲したハーバード大学のエドモンドソン氏が心理的安全性の度合いを測るためのアンケート項目として提唱したもので、以下の7つの項目を言います。
「心理的安全性7つの指標」
- ミスが非難される環境かどうか(否定的な指標)
- 困難な問題も提起しやすい雰囲気か(肯定的な指標)
- 異質な意見を拒絶される雰囲気があるか(否定的な指標)
- リスクを取る行動が安全と感じられるか(肯定的な指標)
- 助けを求めにくい雰囲気があるか(否定的な指標)
- 他者の努力を妨げる行為がないか(肯定的な指標)
- 自身のスキルが尊重され役立っていると感じられるか(肯定的な指標)
※回答の評価ポイントと使い方
各質問に「1(まったく当てはまらない)〜7(非常に当てはまる)」の7段階で回答、平均スコアを算出
- 否定的な項目(1・3・5):スコアが低いほど心理的安全性が高い傾向
- 肯定的な項目(2・4・6・7):スコアが高いほど心理的安全性が高い傾向
心理的安全性を取り入れる際の注意点

緊張感のない「ぬるま湯組織」になる可能性
心理的安全性の考え方を職場に取り入れると、失敗を恐れずに仕事に打ち込めるプラス面はあるものの、反対に仕事に対する緊張感がなくなり、モチベーション低下を招く可能性があります。
そうした「ぬるま湯組織」になってしまわないためにも、導入前と導入後にアンケートを取るなどして、施策の評価を行うことが大事になります。
また、定期面談等をとおしてスタッフの生の意見を吸い上げることも大事です。
年齢にばらつきがある職場とは相性が悪い
職場内で年齢のばらつきがあると、派閥が形成されやすくなり、派閥同士の対立から心理的安全性の確保が難しくなる側面が考えられます。
そもそも職場内で年齢にばらつきがあるということは、言い換えれば「組織に多様性がある」ということにつながります。組織にとっての多様性は、生産性向上につながる肯定的な側面としても捉えられています。
年齢構成にばらつきのある職場で心理的安全性を高めていくには、多様性の意義や重要性を管理者から繰り返し発信し、職場に浸透させていくことが重要です。
世代間における価値観の共有については、いま多くの職場が抱える課題ですが、医療機関においてZ世代が定着するための方策について、以下の記事で解説していますので併せてご参考ください。

まとめ

ここまで、心理的安全性の本当の意味やその重要性を共有し、医療現場において働きやすい職場環境をつくるための方策について解説してきました。
最後に、改めて心理的安全性の向上がもたらす4つの効果をまとめます。
- 心理的安全性向上による医療ミスの減少
- 医療チームのパフォーマンス向上
- 医療従事者のストレス低減と離職率低下
- 改善が行われやすい組織文化の醸成
心理的安全性は、単なる職場改善のスローガンではありません。
医療現場においては、ペイシェントハラスメントの早期対応、安全配慮義務の履行、離職防止といった実務課題を支える「基盤」であることがお判りいただけたのではないでしょうか。
制度やマニュアルを整備しても、現場から声が上がらなければ機能しません。
心理的安全性をどう作り、どう維持するかは、管理職や医療安全担当者にとって避けて通れないテーマだと考えます。
心理的安全性を「考え方」で終わらせないために
心理的安全性は、職員の気持ちだけの問題ではありません。
ペイシェントハラスメント対応や安全配慮義務を機能させるための、組織として整えるべき土台です。
【2026年度研修計画をご検討中の医療機関様へ】
現場対応・体制整備・研修設計を含め、医療機関の実情に即した形で整理したい方は、以下をご覧ください。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。