コロナ禍では、新型感染症の最前線で治療に向かう医療従事者に称賛の声が上がりました。
その一方で、日常業務や生活において強いストレスに疲弊した医療従事者のバーンアウト(燃え尽き症候群)が問題視されました。
コロナ禍に限らず、医療従事者は人の命に係わる仕事を日常としています。一般の職場よりも緊張度を高く保つ必要があるため、日常のストレス状態からメンタル不調に陥る人も少なくありません。
今回は、看護師を中心に医療従事者が抱えるストレスの現状とその理由について、資料をもとに考えていきたいと思います。
労災請求件数からみる精神障害の実情

実際、職場におけるメンタル不調者がどれくらい増えているのか。
厚生労働省が公表している「過労死等の労災補償状況」をもとに、現状を確認していきたいと思います。
出典:令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省(別添資料2)
精神障害労災請求件数は一貫して増加
始めに、精神障害の労災請求件数の推移について共有したいと思います。
| 請求件数 (全業種) | うち自殺 | 請求件数 (医療、福祉) | 請求件数割合 (医療、福祉) | |
| 2019年度 | 2,060 | 202 | 426 | 20.7% |
| 2020年度 | 2,051 | 155 | 488 | 23.8% |
| 2021年度 | 2,346 | 171 | 577 | 24.6% |
| 2022年度 | 2,683 | 183 | 624 | 23.3% |
| 2023年度 | 3,575 | 212 | 887 | 24.8% |
| 2024年度 | 3,780 | 202 | 983 | 26.0% |
(厚生労働省・「過労死等の労災補償状況」を参考に筆者作成)
直近の推移でみると、2020年度以降、労災請求件数は「全業種」、「医療、福祉」共に増加していることがわかります。
表の右側「医療、福祉」の請求件数割合をみると、2019年度の20.7%から増加傾向にあるのがわかります。そして2024年度は26.0%と、全業種の請求件数の4分の1以上の割合を「医療、福祉」が占める結果となりました。
精神障害請求件数の多い業種とは?
次に、2024年度における精神障害の労災請求件数の多い業種について共有します。
| 業種(大分類) | 業種(中分類) | 請求件数 | 割合 | |
| 1位 | 医療、福祉 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 589 | 15.6% |
| 2位 | 医療、福祉 | 医療業 | 389 | 10.3% |
| 3位 | 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 | 145 | 3.8% |
| 4位 | サービス業 (他に分類されないもの) | その他の事業サービス業 | 127 | 3.4% |
| 5位 | 卸売業、小売業 | その他の小売業 | 112 | 3.0% |
(厚生労働省・「過労死等の労災補償状況」を参考に筆者作成)
全業種の中で労災請求件数が最も多いのが「社会保険・社会福祉・介護事業」の589件(15.6%)、次に「医療業」の389件(10.3%)となります。
3番目に多い「道路貨物運送業」は149件で、全体の請求件数の3.8%程度ですので、この資料からも「医療、福祉」業が他業種に比べて、精神障害の労災請求件数が著しく多いことがわかります。
精神障害請求件数の多い職種とは?
さらに、2024年度における精神障害の労災請求件数の多い職種について共有します。
| 職種(大分類) | 職種(中分類) | 請求件数 | 割合 | |
| 1位 | 事務従事者 | 一般事務従事者 | 577 | 15.3% |
| 2位 | 専門的・技術的職業従事者 | 保健師,助産師,看護師 | 242 | 6.4% |
| 3位 | 販売従事者 | 商品販売従事者 | 232 | 6.1% |
| 4位 | サービス職業従事者 | 介護サービス職業従事者 | 230 | 6.1% |
| 5位 | 販売従事者 | 営業職業従事者 | 211 | 5.6% |
(厚生労働省・「過労死等の労災補償状況」を参考に筆者作成)
全職種の中で、精神障害の労災請求件数が2番目に多いのが「保健師,助産師,看護師」の242件、4番目に多いのが「介護サービス職業従事者」の230件となっています。
医療職種の中でも、看護、介護系職種だけで全職種の12.5%を占めるほど、精神障害の請求件数が多いことがわかります。
精神障害支給決定事案で多くみられた具体的な出来事とは?
2024年度の精神障害における労災支給決定の要因となった、具体的な出来事についても共有したいと思います。
| 出来事の類型 | 具体的な出来事 | 支給決定件数 | うち自殺 | |
| 1位 | パワハラ | 上司等からパワハラを受けた | 224 | 10 |
| 2位 | 仕事の量・質 | 仕事内容・仕事量の大きな変化 | 119 | 21 |
| 3位 | 対人関係 | 顧客等から著しい迷惑行為を受けた | 108 | 1 |
| 4位 | セクハラ | セクハラを受けた | 105 | 0 |
| 5位 | 事故や災害の体験 | 業務で悲惨な事故や災害を体験、目撃した | 87 | 0 |
(厚生労働省・「過労死等の労災補償状況」を参考に筆者作成)
精神障害における労災支給の決定要因で最も多い出来事が「上司等からパワハラを受けた」224件、次に多いのが「仕事内容・仕事量の大きな変化」119件、3番目が「顧客等から著しい迷惑行為を受けた」108件となっています。
しかも、上位3位までの合計451件の労災支給決定のうち、32件(7.1%)が自殺に追い込まれていることは見逃してはならない事実だと考えます。
なお、労災支給決定の出来事として3番目に多い「顧客等から著しい迷惑行為を受けた」とは、カスタマーハラスメント(カスハラ)、医療業界においてはペイシェントハラスメント(ペイハラ)とも呼ばれるもので、現在多くの医療従事者が患者等からの迷惑行為に悩みを抱えています。
患者等からのクレーム対応が、いかに看護現場で苦痛の種になっているかについては、後ほど詳しく解説します。
このカスタマーハラスメントについては、2025年6月に改正労働施策総合推進法成立により、事業者がカスタマーハラスメント対策の義務を負うことになりました。
2026年中には施行される予定ですので、医療機関においても患者等からのカスハラ・ペイハラへの対策を講じる必要があります。
医療機関がペイシェントハラスメントにどのように対応すべきか、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

労働実態調査からみる看護職員のストレス事情
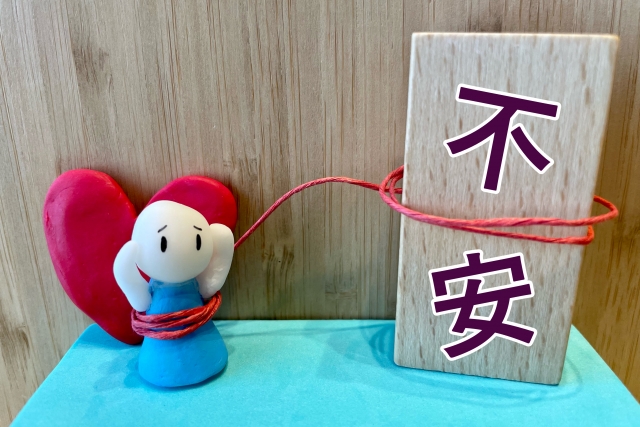
それでは、実際に医療の現場で働く人は、どのようなストレスを抱えているのでしょうか?
ここでは、日本医療労働組合連合会がまとめた「2022年看護職員の労働実態調査『報告書』」から、看護師が抱えるストレスの実態について探っていきたいと思います。
実態➊:仕事での強い不満、悩み、ストレス
Q.「今の仕事に強い不満、悩み、ストレス」
この調査では、看護職員の65%超が、今の仕事に強い不満やストレスを感じていることがわかります。
- 「ある」65.4%
- 「ない」19.8%
- 「わからない」14.9%
Q.「今の仕事に強い不満、悩み、ストレスが『ある』(勤務形態別)」
前掲した「今の仕事に強い不満、悩み、ストレス」があるかの質問に対して『ある』と回答した人を、勤務形態別で分けた結果が以下の資料です。
資料からわかるとおり、「3交替」や「2交替」などの交替制勤務で働く看護職の方が、より仕事に対するストレスを感じていることがわかります。
- 「日勤のみ」54.8%
- 「3交替」69.6%
- 「2交替」(夜勤16時間以上)68.2%
Q.「今の仕事に強い不満、悩み、ストレスが『ある』(時間外労働別)」
前掲した「今の仕事に強い不満、悩み、ストレス」があるかの質問に対して『ある』と回答した人を、時間外労働別で分けた結果が以下の資料です。
当然ながら、時間外労働が多い看護職員ほど仕事に対するストレスを感じていることがわかります。
- 「なし」41.3%
- 「10-20時間」71.8%
- 「30-40時間」81.7%
- 「60-70時間」88.6%
Q.「仕事での強い不満、悩み、ストレスの大きな要因」
前掲の質問で回答したストレスの原因のトップは、「仕事の量の問題」48.7%となっています。
資料からわかるとおり、看護職員が抱えるストレスの原因の約半数の回答が、業務量の多さを指摘していることがわかります。
次に多い回答が「仕事の質の問題」31.8%で、いずれも看護業務という仕事そのものからくる悩みを訴えているものと考えます。
- 1位:「仕事の量の問題」48.7%
- 2位:「仕事の質の問題」31.8%
- 3位:「職場の人間関係」22.2%
- 4位:「夜勤」16.2%
- 5位:「仕事への適性の問題」11.5%
- 6位:「教育の問題」9.1%
- 7位:「昇進昇級の問題」6.6%
- 8位:「患者・家族からのクレーム」6.3%
- 9位:「定年後の仕事・老後の問題」6.1%
- 10位:「勤務先の将来性の問題」6.0%
実態➋:患者・家族からのクレーム
Q.患者や家族からのクレームに対するストレス
前掲した「今の仕事に強い不満、悩み、ストレス」があるかの質問で、「患者・家族からのクレーム」は8位に入っていましたが、さらに掘り下げた調査が以下の資料です。
「強く感じている」と「少し感じている」、合わせて75%超の看護職員が患者や家族のクレームにストレスを感じていることがわかります。
- 「強く感じている」25.6%
- 「少し感じている」49.6%
- 「あまり感じていない」18.0%
- 「感じていない」6.9%
Q.患者や家族からのクレームに対するストレス 「強く感じている」(勤続年数別)
患者や家族からのクレームに対し、ストレス を「強く感じている」と回答した人を、勤続年数別に分けた結果が以下の資料です。
資料からわかるとおり、「25~30年未満」が最も多く34.1%と、この層の3分の1以上の看護職員が患者・家族のクレームに強いストレスを感じていることがわかります。
- 1年未満 12.9%
- 1~3年未満 18.5%
- 3~5年未満 23.0%
- 5~10年未満 26.1%
- 10~15年未満 27.7%
- 15~20年未満 29.8%
- 20~25年未満 29.1%
- 25~30年未満 34.1%
- 30年以上 32.0%
つまり、勤続年数が長くなると管理職に就く機会も増え、その責任に応じて患者のクレームに対応する機会が多くなることを示した結果でもあります。
管理職のストレス対策は病院運営上、見過ごすべきではないと考えます。
医療機関の管理職のストレスにはどのようなものがあるのか、どのような影響を組織にもたらすのかについて、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。

実態➌:仕事を辞めたい
Q.仕事を辞めたい
最後に、看護職に対して仕事を辞めたいかどうかを質問した結果が以下の資料です。
「いつも思う」と「ときどき思う」、合わせて80%弱の看護職員が仕事を辞めたいと思っていることがわかります。
- 「いつも思う」24.0%
- 「ときどき思う」55.2%
- 「思わない」16.6%
- 「わからない」4.2%
Q.仕事を辞めたいと思う主な理由
前掲の質問で回答した仕事を辞めたい理由のトップは、「人手不足で仕事がきつい」58.1%となっています。
その他、3位が「思うように休暇が取れない」32.6%、4位が「夜勤がつらい」23.6%となっており、人員不足の中でのシフト勤務の厳しさが、仕事を辞めたいと感じる理由の根本的な原因になっているものと考えられます。
- 1位:「人手不足で仕事がきつい」58.1%
- 2位:「賃金が安い」42.6%
- 3位:「思うように休暇が取れない」32.6%
- 4位:「夜勤がつらい」23.6%
- 5位:「思うような看護ができず仕事の達成感がない」23.1%
医療従事者が知っておきたいストレス対策とは

それでは、医療現場で働く人たちはどのようにメンタルヘルスケアを行えばいいのでしょうか。
最後に、厚生労働省が示す4つのケアについて触れたいと思います。
4つのケアとは
厚生労働省は、事業所におけるメンタルヘルス対策として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で「4つのケア」という考え方を示しています。
- セルフケア
- ラインによるケア
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
➊の「セルフケア」とは、文字どおり自分自身で行うメンタルヘルス維持の取り組みになります。
➋の「ラインによるケア」とは、職場の管理職が部下のメンタルヘルス維持に注意を払う取り組みで、産業医との連携も含まれます。
➌の「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」とは、自施設にある健康管理室などの産業保健機能による相談対応などがあたります。
❹の「事業場外資源によるケア」とは、外部資源を活用して自施設の職員のメンタルヘルスの支援をしていく取り組みで、EAP(従業員支援プログラム)などがそれにあたります。
以下の記事では、医療機関が考えるべき職員のストレス対策について、特に看護師に対するストレスマネジメントの方策について詳しく取り上げていますので、併せてご参考ください。
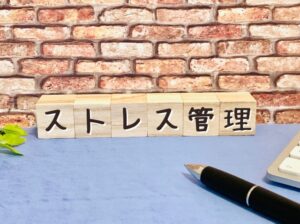
❹のEAP(従業員支援プログラム)は、医療機関の職員、管理者ともに導入メリットを享受できるサービスです。以下の記事でEAPの活用方法や導入手順について詳しく取り上げていますので、こちらもご参考ください。

このように医療従事者の精神障害が増加している背景には、個人の問題だけでなく、職場環境や組織の対応体制が深く関係しています。
医療機関には、職員の心身の健康を守るための安全配慮義務が求められており、その法的な考え方や実務上のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ストレス対策は「セルフケア」から
紹介したとおり、メンタルヘルスケアには4つのケアがあります。
しかし、自分自身で行う「セルフケア」がストレス対策の第一歩となることは言うまでもありません。
組織任せにせずに、日頃からセルフケアを行い、自分で自身のストレスの有無に注意を払うこと。
もし、自身のストレスに気づいたら、自分なりのストレス対処法を取り入れながらストレスを軽減させたり、メンタル不調にならないように心掛けていくことが重要です。
厚生労働省が運営する「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」に、セルフケアの具体的な方法が掲載されていますので紹介します。
「セルフケア」の具体的な方法
- リラクセーション
- ストレッチ
- 適度な運動
- 快適な睡眠
- 親しい人たちと交流
- 笑う
- 仕事から離れた趣味を持つ
まとめ
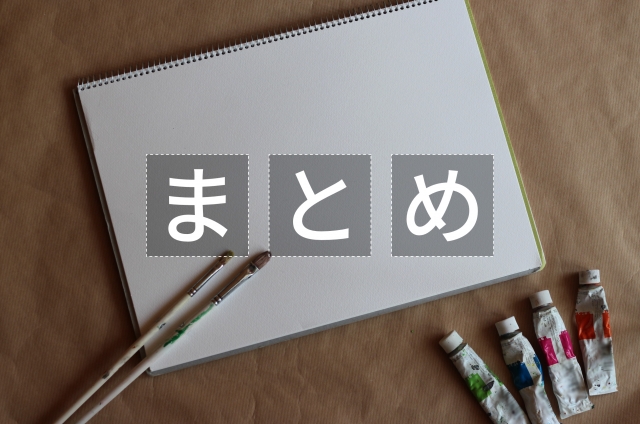
ここまで、看護師を中心に医療従事者が抱えるストレスの現状とその理由について考えてきました。
最後に、本記事の内容をまとめたいと思います。
- 「医療、福祉」業が他業種に比べて、精神障害の労災請求件数が著しく多い
- 看護職員の65%超が、今の仕事に強い不満やストレスを感じている
- 看護職員のストレスの原因のトップは、「仕事の量の問題」
- 75%超の看護職員が患者や家族のクレームにストレスを感じている
- 80%弱の看護職員が仕事を辞めたいと思っている
- 看護職員が仕事を辞めたい理由のトップは、「人手不足で仕事がきつい」
- 4つのケアのうち自分自身で行う「セルフケア」がストレス対策の第一歩
特に看護師は、人手不足を背景に、一人に係る仕事量が多いことに加え、自身で仕事のコントロールがしづらいという業務の特性があります。
他の職種より精神的なストレスがかかりやすいため、医療機関としては、組織的な対策の検討や具体的な支援が重要になります。
医療従事者個人として考えたいのは、バーンアウトを防ぎ長期的なキャリアを維持するためには、自分を大切にしながら働くという意識がより重要になってきます。
そのためには、まずは自身のストレスの原因を知り、自身で予防や対処を行いながら、周りの人にも支援を求めて、心の健康を保つことが大事になります。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。







