人はなぜ働くのでしょうか。
- 「お金を増やすため」
- 「生活を守るため」
- 「やりがいを感じるため」
- 「社会に貢献するため…」
答えは人それぞれ違うと思います。性別や年代でも答えは変わってきそうです。
今回は、仕事に対する価値観や、組織におけるモチベーション管理の重要性について考えていきたいと思います。
年代で異なる仕事の価値観

仕事に対する価値観は、年代によって異なると言われています。
いま、組織で管理職を任されている50代は、団塊ジュニア世代とか、氷河期世代とも言われる年代です。この年代は、言わば会社に身を捧げ、転勤もいとわないような、仕事優先の働き方をしてきた方も多いと思います。
一方、管理職の下で働くいまの若い世代は、相対的に、ワークライフバランスを重視し、社内の昇進より自己の有意義なキャリア形成を志向する人が多いとも言われています。
いまの若い世代は、「Z世代」とも言われています。1990年代中盤から2010年頃までに生まれた世代で、以下の特徴があると言われています。
- デジタルネイティブ
- タイムパフォーマンス重視
- 価値観の多様性を重視
- 自律的で柔軟な働き方を志向
現代の職場では、組織を「管理する層」と「管理される層」で、仕事に対する考え方が大きく異なります。
これからの時代、組織を適切に運営していくためには、いまの若い世代の特徴を十分理解すること、そして、多様な考え方を受け止める姿勢が非常に重要になります。
いまの若い世代をどのように人材として確保し活用していくか、以下の2つの記事で解説しています。併せてご参考ください。
「働き方に関するアンケート調査」から実態を探る
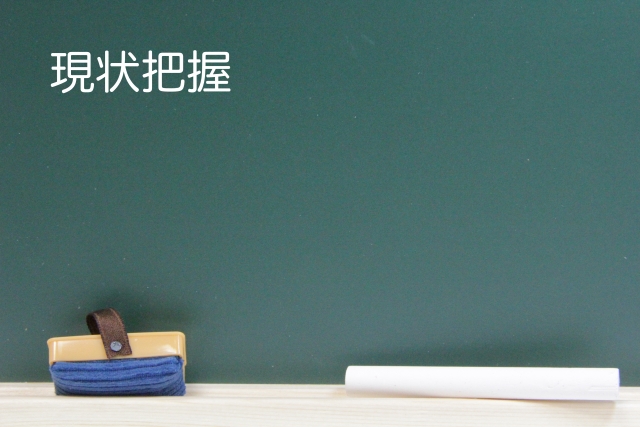
それでは、実際、現代の社会人は仕事に対してどのような意識を持って働いているのでしょうか。
また、年代や性別によって仕事に対する意識に違いはあるのでしょうか。
明治安田総合研究所が行った「働き方に関するアンケート調査」(2023 年 10 月、20 歳以上 69 歳以下の男女 1,800 人対象)から、実態を探っていきたいと思います。
仕事を選ぶうえで重視することは?
このアンケート調査によると、「仕事を選ぶうえで重視すること(上位3つまで)」の質問に対し、各年代や性別ごとに以下の割合で回答していることがわかります。
| 全体順位 | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
| 1位:収入 | 64.3% | 68.9% | 59.7% | 60.6% | 63.1% | 69.4% | 63.6% | 64.7% |
| 2位:仕事内容 | 57.7% | 59.3% | 56.1% | 50.6% | 53.9% | 59.7% | 62.2% | 62.2% |
| 3位:やりがい | 36.6% | 43.7% | 29.4% | 32.5% | 38.6% | 36.9% | 36.1% | 38.6% |
| 4位:勤務時間 | 31.2% | 26.7% | 35.8% | 24.2% | 29.2% | 31.7% | 34.4% | 36.7% |
| 5位:勤務地 | 24.6% | 19.9% | 29.2% | 16.7% | 18.3% | 27.8% | 30.0% | 30.0% |
| 6位:特に条件はない | 18.7% | 16.9% | 20.4% | 33.9% | 20.0% | 11.9% | 15.6% | 11.9% |
| 7位:福利厚生 | 13.9% | 12.9% | 14.9% | 16.7% | 18.1% | 11.7% | 12.5% | 10.6% |
| 8位:専門性が活かせる | 13.4% | 16.2% | 10.7% | 18.3% | 14.2% | 11.4% | 10.0% | 13.3% |
| 9位:勤務体制 | 11.1% | 7.8% | 14.3% | 11.7% | 9.7% | 10.0% | 11.1% | 12.8% |
| 10位:スキル・能力を伸ばせる | 10.8% | 12.1% | 9.4% | 16.4% | 12.5% | 7.2% | 9.2 | 8.6 |
上の資料をみると、「仕事を選ぶうえで重視すること」の回答として、最も多かった選択肢は「収入」でした。
2番目に多い回答が「仕事内容」、3番目が「やりがい」となっています。
次の項から、性別や年代によって回答内容にどのような違いがあるのか探っていきたいと思います。
出典:2023年 働き方に関するアンケート調査 | 調査研究・レポート | 明治安田総合研究所 (myri.co.jp)
性別による回答の違い
ここでは、性別による回答の違いをみていきます。
「仕事を選ぶうえで重視すること」の質問に対し、男女で回答に差が出たのは
- 「やりがい」
- 「勤務時間」
- 「勤務地」
の項目でした。性別による回答の違いを簡単にまとめると、以下のとおりとなります。
「Q.仕事を選ぶうえで重視すること」の質問に対し、
- 男性は、女性と比較すると、仕事に「やりがい」を求める傾向にある
- 女性は「やりがい」と同等以上に、「勤務時間」や「勤務地」などの勤務条件面を求める傾向にある
年代による回答の違い
また、同じ質問に対し、年代で回答に差が出たのは、
- 「専門性が活かせる」
- 「スキル・能力を伸ばせる」
- 「収入」
- 「勤務時間」
の項目でした。年代による回答の違いを簡単にまとめると、以下のとおりとなります。
「Q.仕事を選ぶうえで重視すること」の質問に対し、
- 20代・30代は、「専門性が活かせる」や「スキル・能力を伸ばせる」といった今後のキャリア形成を意識した回答の割合が高い
- 50代・60代など、年代が上がるにつれ、「収入」や「勤務時間」などといった勤務条件面を重視する傾向にある
なお、相対的に年代でのバラツキが出なかった回答として挙げられるのは、「やりがい」でした。
仕事に「やりがい」を求めているのは、年代に関わらず誰しもが感じていることなのかも知れません。
医療従事者が感じる仕事のやりがいとは

それでは、医療従事者は、仕事に対するやりがいについてどのように考えているのでしょうか。
日経メディカルプロキャリアが行った「仕事のやりがいに対する意識調査」(2020年5月、日経メディカル Onlineの登録会員332人対象)から、医療従事者の職業観について探っていきたいと思います。
出典:【第10回】仕事のやりがいに対する意識調査 | メディカル業界アンケート集計結果 | キャリアLabo | 日経メディカルプロキャリア (nikkeihr.co.jp)
約8割が「やりがい」を感じている
始めに、「やりがいはありますか?」という質問に対し、医療従事者は以下のとおり回答しています。
- 「頻繁にある」22.6%
- 「時々ある」57.5%
- 「ほとんどない」15.7%
- 「全くない」4.2%
この回答によると、約8割の医療従事者が今の仕事にやりがいを感じていることがわかります。
一方、やりがいが「ほとんどない」医療従事者が15%もいることにも少し驚かされます。
モチベーションアップが「やりがい」の原動力
次に、医療従事者に「仕事にやりがいが必要な理由」を尋ねたところ、以下のとおり回答しています。
- 1位 モチベーション維持・アップのため
- 2位 給与以外に自分の存在意義が必要だから
- 3位 仕事/人生・生活への満足度アップに必要だから
- 4位 社会貢献につながっている実感が必要だから
- 5位 スキルアップや自己研鑽を促すから
仕事にやりがいが必要な理由として、「モチベーション維持・アップのため」が1位になっています。
また、4位に「社会貢献」、5位に「スキルアップや自己研鑽」という理由が並びます。
他の職業に比べ、医療者は、他者への貢献意欲や使命感、倫理観が高い方が多いので、それがあらわれた結果だと考えます。
以下の記事では、医療従事者の働きがいをいかに高めていくか、その方策について解説していますので、併せてご参考ください。
なぜモチベーション管理が重要なのか
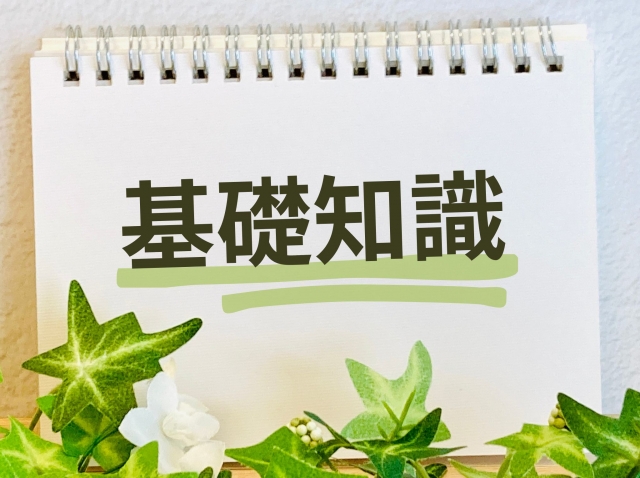
組織においてスタッフのモチベーション管理をいかに行っていくか。これはとても重要な経営課題と言えます。
ここでは、「モチベ―ション」という言葉について、少し掘り下げて考えていきたいと思います。
モチベーションとは
そもそもモチベーションとは、どのようなことを指すのでしょうか。
モチベーションとは、「目標達成のために努力しようとする個人の意思」と表現できます。
最初に紹介したアンケート(仕事選びで重視すること)を例に考えると、仕事に対するモチベーションは、ある人は「収入」であるし、また別の人は「やりがい」ということになります。
「強さ」、「方向性」、「持続性」の3要素が求められる
仕事に対するモチベーションには、以下の3要素が求められると言われています。
つまり、良質なモチベーションであるには、
その意思が
- 強いこと
- 適切な方向付けがされていること
- 持続されていること
が重要とされています。
仕事への向き合い方はスタッフによって様々
現実はと言うと、「上からやらされている仕事」と、「自らやりたくてやる仕事」では、モチベーションが大きく異なるのは言うまでもありません。
スタッフの置かれている環境も様々です。性別、経験年数、業務内容、待遇面、周りのメンバーなどで、各々仕事への向き合い方も変わってくると思います。
スタッフ個々により、「強さ」、「方向性」、「持続性」の3要素すべてにバラツキが出るのは、ある意味仕方のないことかも知れません。
3要素揃ったモチベーション管理で組織力強化を
組織の管理者としては、スタッフに対し適切なモチベーション管理を実践し、エンゲージメントを高め、生産性向上や組織力強化を図る必要があります。
医療機関において重要な経営課題とも言える離職防止を図るためにも、3要素揃った良質なモチベーションの維持・向上策が何より重要と言えそうです。
モチベーション向上の具体的な方策

それでは、スタッフ個々のモチベーションを向上させるには、どのような対策を講じればいいのでしょうか。
一般に、動機付けには以下のとおり2種類あると言われています。
- 内発的動機付け
- 外発的動機付け
それぞれ解説していきます。
内発的動機付けとは
内発的動機付けとは、仕事そのものの楽しさや有能感、満⾜感、⾃己決定の感覚など、自分の内から湧き上がるものを言います。
例えば、人のお世話が好きで看護師の仕事をしている場合、仕事の動機は「人のお世話をしたい」という内面から湧き上がる気持ちです。決して給料のためではありません。
外発的動機付けとは
内発的動機付けに対し、外発的動機付けとはどのようなものなのでしょうか。
外発的動機付けとは、報酬、昇進など、自分の外から与えられるものを言います。
例えば、他の職業より給料が高いから看護師の仕事をしている場合、まさに「給料」という自分の外から与えられる報酬の高さが仕事の動機になっています。
医療従事者には内発的動機付けを行いたい
それでは、医療従事者に対する動機付けはどのように考えるべきでしょうか。
前述したアンケートの”「仕事にやりがいが必要な理由」 TOP5”でも示されているとおり、そもそも医療従事者は、職業への使命感や社会貢献を仕事のやりがいに感じています。
つまり、自律的な働き方を志向する医療従事者全般に対しては、内発的動機付けを中心に行うことが有効だと考えられます。
先ほどの例で言うと、人のお世話が好きで看護師をしているスタッフに対しては、患者からの喜びの声を上司がスタッフ本人に届けたり、上司から感謝の言葉をかけることで、本人の内発的動機付けが促されます。
医療従事者に対する内発的動機付けの具体的な実践方法について、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
医療従事者の内発的動機付けに必要な基礎知識

実際、医療従事者に対して内発的動機付けを実践する際、どのようなことを考えればいいのでしょうか。
ここでは、J.R.ハックマンと G.R.オルダムの提唱した「職務特性モデル」を参考に考えていきたいと思います。
職務特性モデルとは
職務特性モデルとは、職務の特性そのものが内発的動機付けに影響を与える、というものです。
簡単に言うと、個人差はあるものの、重要でおもしろい仕事をしているときはやる気が上がり、活き活きと働ける、といったものです。
次に掲げる5つの特性が、モチベーション向上のための重要な要素となると言われています。
- ①技能多様性
-
単純作業ではなく、いろいろなスキルが必要な仕事のこと。
- ②タスク完結性
-
全体像を把握したうえで、一通りの流れに関わること。
- ③タスク重要性
-
他者に重要なインパクトを与えるような重要な仕事のこと。
- ④自律性(自己決定)
-
⾃分なりに⼯夫できる裁量度の高い仕事のこと。
- ⑤フィードバック
-
自分が手掛けた仕事の手ごたえを感じられること。他者からのものではなく、自分で成果を確認できること。
スタッフ個々に合わせた内発的動機付けが理想
ここで何より大事なのは、職務に対する5つの特性を踏まえ、スタッフ個人個人に適した内容で、きめ細かく内発的動機付けを行うことになります。
医療機関においては、スタッフ数も多く、性別も年代も職種も様々いるなかで、きめ細かく動機付けを行うことは、そう簡単にはいかないでしょう。
しかし、スタッフ個々のモチベーション向上を図り組織力を向上させるには、職務特性モデルを意識しながら、普段の声掛けの段階から内発的動機付けを実践していくことが理想だと言えます。
まとめ
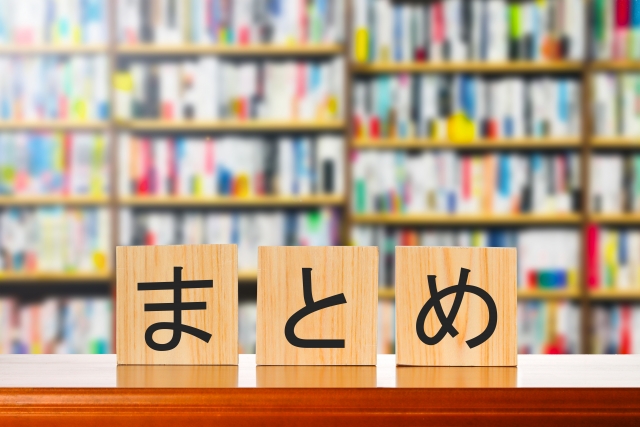
今回は、仕事に対する価値観や、組織におけるモチベーション管理の重要性について考えてきました。
最後に、本記事をまとめたいと思います。
- 今後は若い世代の特徴を十分理解すること、多様な考え方を受け止める姿勢が非常に重要
- 約8割の医療従事者が今の仕事にやりがいを感じている
- 医療従事者にとって「仕事にやりがいが必要な理由」の1位は「モチベーション維持・アップのため」
- モチベーションには「強さ」、「方向性」、「持続性」の3要素が求められる
- 離職防止を図るためにも、3要素揃った良質なモチベーションの維持・向上策が重要
- 医療従事者全般に対しては、内発的動機付けを中心に行うことが有効
- スタッフ個人個人に適した内容で、きめ細かく内発的動機付けを行うことが大事
日常業務からスタッフのモチベーションアップを図ることで、自院の生産性向上や組織力強化につながります。
そして、スタッフが活き活きと働く職場が実現すれば、離職率が下がり、経営の安定化も期待できるのではないでしょうか。
今回の記事が、院内のモチベーション管理について考えるきっかけになれば幸いです。








