2025年6月、労働施策総合推進法が改正され、事業主にカスタマーハラスメント防止対策の義務が課されるようになりました。
政府は、改正法の施行を2026年10月1日を目途に指針の整備等を進めていますが、それに伴い医療機関においても患者や家族等によるペイシェントハラスメント対策を組織的に講ずる必要が出てきています。
ペイシェントハラスメントは、医療従事者の身体又は精神に深い障害をもたらす可能性があります。また、医療機関の対応によっては、訴訟リスクの観点から経営に大きな悪影響をもたらす可能性もあります。
この記事では、元医療従事者の社労士の立場から、医療機関が認識しておくべきペイシェントハラスメントの問題点や具体的対応策、リスクマネジメント強化策などの総論について解説します。
実務編(①初動対応、②組織体制構築、③職員サポート)については、本記事の該当パートで紹介していますので、随時ご参照ください。
※ 本記事の内容は、実際に医療機関向け研修で使用している実務ノウハウをもとに整理しています。
ペイシェントハラスメントとは? 医療機関が知っておくべき現状と問題点
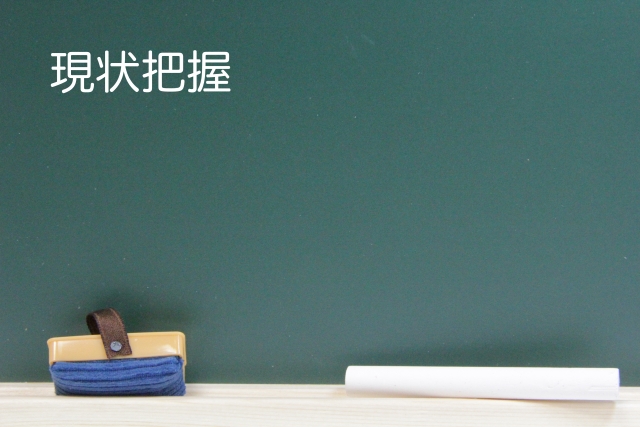
始めに、ペイシェントハラスメントの現状と問題点について解説します。
医療現場におけるペイシェントハラスメントの実態
- 「早く診察しろ!しばくぞ!」
- 「下手な注射のせいで腕がしびれた!土下座して謝らないと言いふらすぞ!」
その他、入院の必要はないと医師が告げているのに退院を拒み、激高する患者やその家族。
皆さまの医療現場でも、似たようなことが起きているのではないでしょうか。
近年、このような医療従事者に対するペイシェントハラスメントが後を絶ちません。
ペイシェントハラスメント(ペイハラ)とは、一般的に、ストーカー行為等を含めた患者等による暴言や暴力等の迷惑行為のことを言います。
迷惑行為を行う「患者等」には、患者のほか患者の家族などの関係者も含まれます。
ペイシェントハラスメントに対する国や自治体の取り組み
厚生労働省や各自治体は、こうした顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)の対策として、近年、以下の取り組みを行っています。
- 2022年2月:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」策定
- 2023年9月:労災認定における「業務による心理的負荷評価表」にカスハラを追加
- 2024年5月:新潟県病院局「ペイシェントハラスメント対策指針」策定
- 2025年1月:第1回カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議開催
- 2025年4月:東京都カスタマー・ハラスメント防止条例施行
- 2025年6月:「労働施策総合推進法」改正案(カスハラ対策を企業の義務とする内容含む)可決・成立→6/11公布(1年6ヶ月以内に施行)
カスハラ・ペイハラの定義
ここで、カスタマーハラスメント及びペイシェントハラスメントの定義について触れておきます。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、企業や業界によって態様が異なると前置きしつつ、以下のようにカスタマーハラスメントを定義づけています。
カスタマーハラスメントとは…
「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
引用:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省 000915233.pdf
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」策定を受けて、新潟県病院局は2024年5月に「ペイシェントハラスメント対策指針」を策定しました。
その中で、以下のようにペイシェントハラスメントを定義づけています。
ペイシェントハラスメントとは…
「患者・家族等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、病院職員の職場環境が害されるものをいう。」
引用:「新潟県病院局ペイシェントハラスメント対策指針」を策定しました – 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp)
上記の定義によると、どのような場合がペイシェントハラスメント(新潟県病院局定義)に該当するのか、その判断ポイントは以下の3点になります。
- クレーム・言動の要求の内容に妥当性があるか?
- 要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当なものか?
- 手段・態様により、病院職員の職場環境が害されていないか?
さらに、新潟県病院局の対策指針では、ペイシェントハラスメントを9つの類型に分類しています。
| 類型 | 行為例 |
| ①暴言型 | 大きな怒鳴り声をあげる。 |
| ②暴力型 | 殴る、蹴る、物を投げつける |
| ③セクハラ型 | ボディタッチ、性的な言動 |
| ④時間拘束型 | 居座りをする長時間電話をかける |
| ⑤リピート型 | 病院からの説明後、電話や面会で理不尽な要望を繰り返し求めてくる |
| ⑥威嚇・脅迫型 | 「仕事ができないようにしてやる」といった脅迫的発言 |
| ⑦権威型 | 謝罪文の提出や土下座を要求 |
| ⑧院外拘束型 | クレームの詳細が分からない状態で、院外の患者・家族等の自宅や特定の喫茶店等に呼びつける |
| ⑨SNS/インターネット上での誹謗中傷型 | 職員の名前をスマホで撮影し、それをSNSなどに投稿 |
※新潟県病院局「ペイシェント(患者)ハラスメント対策指針」より抜粋
職員が直面する心理的、身体的影響
患者やその家族からの過度な要求や威圧的な態度は、医療従事者のストレスの原因になっています。
日本医療労働組合連合会の『2022年看護職員の労働実態調査「報告書」』によると、患者や家族からのクレームに対して、約75%の看護師がストレスを感じているという調査結果が示されています。
- 「強く感じている」25.6%
- 「少し感じている」49.6%
- 「あまり感じていない」18.0%
- 「感じていない」6.9%
そして、年齢や勤務年数が上がるにつれてストレスを強く感じている人の割合が多い、との調査結果も示されています。
これは、ベテラン層や師長などの管理職が患者や家族のクレームに対応をする機会が多いことを示唆しています。
- 1年未満 12.9%
- 1~3年未満 18.5%
- 3~5年未満 23.0%
- 5~10年未満 26.1%
- 10~15年未満 27.7%
- 15~20年未満 29.8%
- 20~25年未満 29.1%
- 25~30年未満 34.1%
- 30年以上 32.0%
ペイシェントハラスメントは、医療従事者のメンタルヘルス不調やバーンアウトによる離職に少なからず影響していると考えます。
医療機関として無視できない3つの理由

職員の心身にダメージを与えるペイシェントハラスメントですが、医療機関として無視できない理由が以下3点あります。
①迷惑行為の多様な原因
患者からの一方的な迷惑行為や嫌がらせには、医療機関として毅然と対応すべきです。
しかし、ここで無視できないのは、迷惑行為の原因が医療機関自体にあるなど、様々な原因が想定されることにあります。
患者等の迷惑行為の原因として考えられるのは、大きく以下の3通り挙げられます。
- 患者側のみに原因
- 患者と医療側に原因
- むしろ医療側に原因
患者対応でバタバタしている医療現場では、医療機関側の配慮に欠けた対応によって、患者を怒らせてしまうことも確かにあります。
医療機関としては、事案が発生した際には、客観的な事実確認を行ったうえで慎重に対応をしないと、逆に患者から訴えられる可能性があることを認識しておかなければなりません。
②医師の応招義務
また、医師法による応招義務も認識しておく必要があります。
以下のとおり、医師は正当な事由なく診療拒否ができません。
ただし、医師の応招義務は、以下のような性格を持つとされています。
- 医師が個人として国に対して負担する「公法上の義務である」
- 医師の患者に対する「私法上の義務ではない」
医師の応招義務が、
- 国に対する公法上の義務であり
- 患者に対する私法上の義務ではない
とすると、問題になるのは、患者から迷惑行為を受けたときに、医師が診療を拒否できるか否かにあります。
これに関して、厚生労働省は、令和元年12月25日付通知にて、医師の応招義務の考え方を整理しています。
これによると、患者からの迷惑行為が継続し、医師と患者の信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化されるため、医師の診療拒否は認められることになります。
裏を返して言うと、患者の迷惑行為を理由に診療を拒否できるかどうかは、迷惑と感じる患者の行為が
- 正当なクレームの範囲内なのか、
- ペイシェントハラスメントに該当するのか、
組織として適切に見極める必要があるということです。
「応招義務に反するか否か」について
- 最も重要な考慮要素
緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度) - その他重要な考慮要素
・診療を求められたのが診療時間・勤務時間内であるか、時間外であるかどうか
・患者と医療機関・医師の信頼関係
「患者を診療しないことが正当化される事例」について
- 患者からの迷惑行為が継続し、信頼関係が喪失している場合
例)診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等 - 支払い能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合、他
出典:厚生労働省令和元年12月25日付通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」000581246.pdf
③使用者の安全配慮義務
さらに、使用者の安全配慮義務も無視できません。
医療機関は使用者として、労働契約法に基づき、職員に対して安全配慮義務を負っています。
医療機関が安全配慮義務違反を問われるのは、以下の場合です。
- 職員に対して安全配慮を行わなかった
- 職員に対して安全配慮を行ったが、配慮が不十分であった
患者の迷惑行為に対して医療機関が職員の安全配慮義務を違反し、職員に損害が生じた場合は、その職員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
つまり、医療機関は患者によるハラスメントが院内で発生しないよう、日頃から職場環境を整備する責任を負っているのです。
この「使用者の安全配慮義務」に関しては、次章で改めて解説します。
ペイシェントハラスメント対策と安全配慮義務の関係

これまで見てきたとおり、ペイシェントハラスメントは、単なるクレーム対応の問題ではなく、職員の心身の健康や就業環境に深刻な影響を及ぼすリスク要因です。
過度な精神的負荷が蓄積し、うつ病などの精神障害を発症した場合、医療機関にはその職員に対して安全配慮義務違反が問われる可能性があります。
そのため、ペイシェントハラスメント対策は、現場対応のマニュアル整備や個人スキルの問題にとどめず、組織としての安全配慮義務の一環として位置づけることが重要と考えます。
- メンタルヘルス対策
- 管理職によるラインケア
- 相談体制の整備
などを組織として一体的に進めることで、実効性のある対策につながります。
※ 法改正を見据えた体制整備研修の概要はこちら
安全配慮義務の観点から医療機関が取るべき対応については、以下の記事で体系的に解説していますので、併せてお読みください。
ペイシェントハラスメントへの具体的な対応策

次に、ペイシェントハラスメントの具体的な対応策について解説します。
現場で実施可能なハラスメント対応策とは
まず、医療機関がペイシェントハラスメント対策を考える際に重要となる2つの要点を解説します。
- 毅然とした対応で取り組む方針を立てる
- 管理体制を整え、現場関係者がこの体制下で備えをする
要点1:毅然とした対応で取り組む方針を立てる
まず、医療機関として毅然とした対応で取り組む方針を立てることが重要です。
ここでは、以下の事例を用いて考えていきます。
【事例】
- 仕事が不慣れで入院患者を怒らせてしまった新人看護師
- 入院患者から「土下座して謝れ」と言われた
- 新人看護師は「患者の怒りが収まるのなら土下座してもかまわない」と思っている
- ①職員へ周知する重要性
-
医療機関が患者の迷惑行為に対する取組の方針を何も示さなければ、上記の例のように、社会経験の少ない新人看護師では、土下座をしても構わないと思ってしまうかも知れません。
しかし、いくら治療中の患者でも、他人の権利を侵害するような権利を行使することを容認しなければならないことにはなりません。
職員を悩まさないためにも、医療機関は、迷惑行為を容認せず、毅然とした態度で臨むという基本方針を立て、スタッフに周知することが重要です。
そうすることで、もし事案が発生した時には周りに相談しやすくなるなど、職員全体が足並み揃えて対応することができます。
- ②患者等へ周知する効果
-
患者の迷惑行為に毅然とした対応を行う旨、医療機関が患者に周知を行うことで、迷惑行為を抑止できる可能性があります。
患者の大半は迷惑行為を行う訳ではありませんが、そのことにも留意しつつ、ポスターや書面の交付等をとおして、「患者でも容認しないこと」を周知することが重要です。
要点2:管理体制を整え現場関係者がこの体制下で備えをする
取組の方針ができたら、次に、管理体制の整備と備えを行います。
- ①規程の整備に向けた実態把握
-
規程の整備に向けて、まず、自院で生じている迷惑行為を把握する必要があります。
また、患者は一つの病院にだけかかるわけではないため、周辺の施設で生じている迷惑行為についても把握することが大事です。 - ②規程・指針・マニュアルの整備
-
多くの医療機関では、医療安全管理部門が中心となって医療安全管理規程を作成していると思います。
規程や指針、対応マニュアルには、前述した自院及び周辺施設の実態把握を踏まえて作成することが重要です。
さらに、対応マニュアルの中には、ペイシェントハラスメント発生時の担当者・責任者の「役割分担表」を作成しておくことをおすすめします。
役割分担表を作成しておくことで、責任を一人に押し付けず、チームで支える姿勢が現場に伝わり、安心感につながります。 - ③委員会の開催
-
医療安全管理委員会にて、指針や規程の整備に関することや迷惑行為の実態把握作業、実際発生した迷惑行為の分析を行います。
多面的な検討ができるよう多職種で組織し、使命感を持って対応することが大事です。
- ④職員研修の実施
-
全職員に対して規程等の周知、ハラスメントに関する知識の習得のための教育、課題解決のための実践的な教育を実施することが大事です。
なぜそのような対応が必要なのか、職員が取るべき行動の基礎となる考え方について教育します。 - ⑤事例の収集
-
実際に発生したハラスメント事例を収集し、それを基にした情報共有や規程見直しの検討、職員への研修内容の検討、それによる施設の構造の見直しを行います。
- ⑥具体的な実態把握、事例分析に基づく対策
-
発生した迷惑行為の実態把握を具体的に行い、事例を下記のように整理・分析し対策を講じます。
これにより、業務の動線の見直しに関する検討にも活用します。
前述したハラスメント発生時の「役割分担表」の具体例など、ペイシェントハラスメント防止に向けた組織体制の構築方法について、以下の記事(実務編②)でまとめています。

職員へのサポート体制構築のポイント

現場対応の体制構築とともに重要になるのが、職員へのサポート体制の構築です。
以下、「事前の対策」と「事後の対応」(被害職員への対応)について解説します。
事前の対策
前述した安全配慮義務の一貫として、医療機関は職場におけるハラスメント行為を受けた職員に対するサポート体制を構築する必要があります。
厚生労働省は、顧客等からの著しい迷惑行為に対し、
- 相談体制の整備
- 被害者への配慮の取り組み
- 被害防止の取り組み
の3項目の取り組みを事業主に促しています。
以下を参考に、自院に合った職員サポート体制を事前に構築しておくことが重要です。
参考:令和2年1月15日厚労省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」○厚生労働省告示第 号労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第
被害職員への対応
もし、院内で既に迷惑行為が発生し、職員に身体的・精神的被害が生じた場合には、以下のようなケアを行う必要があります。
- 相談体制を整備
- ためらわずに相談するよう周知
- カウンセリング、通院時間を確保できるよう勤務時間の調整
医療機関としては、被害者職員が、
「また同様の被害があるのでは…」
と恐怖感を抱いていることを想定し、今後も安心して仕事ができるように、検討した再発防止策を被害者本人に伝えることが非常に重要です。
また、現時点で既に行った対策やこれから行う予定の対策の両方を伝えると、被害者職員はさらに安心できるはずです。
ペイシェントハラスメント被害を受けた職員サポート実務について、以下の記事(実務編③)で詳しく解説しています。

ペイシェントハラスメント発生時の法的リスクと危機管理対策

ここでは、法的観点から医療機関におけるリスクマネジメント強化の方策について解説します。
訴訟リスクを最小限に抑えるための法的対応策
法的倫理的観点から患者等による迷惑行為をみたとき、以下の2パターンに分けることができます。
どちらに該当するかによって、医療機関は対応策を見極める必要があります。
パターン①:法的に問題がある行為
- 患者が医療従事者を殴って傷害を負わせるケース
- 患者が医療器具を蹴って破損させるようなケース
こうした事案が発生した場合は、その時点で毅然とした態度で対応する必要があります。
パターン②:法的に問題があるとまでは言えないが倫理的に問題のある行為
- クレームに対する説明が終了した後でも、繰り返しその患者が説明を求めるケース
- 待合室にいる患者が長時間にわたり携帯電話で大声で話すのを注意してもやめないケース
こうした事案も十分考えられますので、院内で定めた規定に沿って対応する必要があります。
迷惑行為者の法的責任
それでは、迷惑行為を行った患者等にはどのような法的責任が生じるのでしょうか。
これについては、大きく分けて、
- 民事責任
- 刑事責任
の2つの責任が生じると考えられます。以下、簡単に説明を加えます。
1.民事責任
民法第709条【不法行為による損害賠償請求】により、迷惑行為を行った患者は損害賠償責任が問われます。
2.刑事責任
刑法第204条【傷害罪】その他の規定により、迷惑行為を行った患者は犯罪者として処罰される可能性があります。
暴力行為等への厳格な対応
患者等の迷惑行為によってすでに損害が発生している場合は、医療機関として以下のとおり厳格な対応をとる必要があります。
- 損害の賠償を求める
- 加害者に対し退去を要求する
- 警察通報を行う
- 被害届や告訴を検討する
これらの対応は、その後の類似行為を減少させるためにも、医療機関にとって重要な対応だと言えます。
警察への事前相談
迷惑行為等による犯罪が起きる以前に、警察の助言を得て必要な対策を講じておくことも重要です。
そのメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 医療機関として予防措置が講じられること
- 犯罪発生時の具体的な対応策を想定できること
ペイシェントハラスメントが起きた場合の初動から事後対応を解説

ここでは、ペイシェントハラスメントが発生した場合の具体的な対応の流れをみていきます。
ペイシェントハラスメントにおける初動対応フローは以下のとおりです。
- 発生の認知
- 安全確保
- 記録・証拠化
- 上司・管理職への報告
- 組織的な初期対応
- 事案の評価・指示
- 記録保存・事後フォロー
上記を踏まえ、初動からの流れを確認します。
ここでは、以下の事例が発生したことを想定して、シミュレーションしていきます。
【事例】
- 診察室前で大声で電話している患者を看護師が注意した
- 注意した看護師に対して、その患者が携帯電話を投げつけた
①初動対応の2つの留意点
事件発生時には、以下の2点に留意して初動対応を行うことが重要になります。
- 落ち着いて毅然とした態度で臨む
- 被害者がいる場合、迅速に身体精神の両側面から被害の回復に向けた対応をとる
②現場対応で重要となる5つの共通事項
事件発生時は、落ち着いて毅然とした態度で臨むことが重要です。
対応内容は迷惑行為の類型(暴言、暴力、居座り、セクハラ、ストーカー、SNSへの書き込み)によって異なりますが、類型を問わず共通して重要な項目もあります。
主に以下5点の共通項目が挙げられます。
- 生命身体に危険が生じる可能性のある場合の安全確保
- 職員に身体的被害が出ている場合の迅速な受診対応
- 現場保存
- 証拠の収集・記録化
- 警察通報の検討など
これら5つの共通事項を踏まえ、現場対応で特に留意すべき点について解説します。
現場の保存
実態把握を行う必要があるため、迷惑行為があったそのままの状態を維持することが大切になります。
そのために、行為者である患者を別の場所に誘導することは、現場保存の観点からも意義があります。
警察官に出動を要請した場合
警察が到着するまで、現場をそのままの状態にしておく必要があります。
警察による実況見分が終わった後も、片づけていいか確認をとる必要があります。
証拠収集・記録化
事後対応のために、証拠収集と事案の記録化を直ちに行う必要があります。
特に、民事訴訟や、告訴・告発など捜査機関への対応でとても重要になります。
客観的証拠を収集し、証言の信頼性を高めるためにも、証拠収集・記録化には複数の手段(メモ、録音、写真等)を組み合わせることが有効です。
民事事件と証拠
民法第709条における損害賠償請求をする際には、以下の3点を被害者側で証明する必要があります。
- 加害行為があったこと
- 損害が生じていること
- 加害行為と損害の間に因果関係があること
被害者職員がこれらを証明しなければならないことを考えても、現場の保存や証拠収集、記録化が、医療機関の対応として非常に重要なことがわかります。
証拠の具体例
職員がケガをしている場合、損害賠償請求の証拠として以下の提示が必要となります。
- ケガ部位の写真
- 関係者へのヒアリング記録
- 診断書
- 領収書 等
ヒアリングの注意点
関係者にヒアリングを行う際に注意すべきポイントは、以下の4点です。
- 5W1Hを意識(Who【誰が】、When【いつ】、Where【どこで】、What【なにを】、Why【なぜ】、How【どのように】)
- 被害者を責める発言はしない
- 可及的速やかにヒアリング
- 生の発言を記録(例「うるさい」「何様だ」と大声で怒鳴る)
③事件発生後の対応
事件の発生後、医療機関として警察へ被害届を出すことや、加害者に対する損害賠償請求を行うことを検討します。
弁護士との顧問契約がある医療機関については、顧問弁護士へ相談した方が的確に対応が進むでしょう。
時間経過とともに事案の収集が困難になり、深刻化する可能性があるため、早めに相談することが大事です。
迷惑行為を行った者への対応
迷惑行為を行った患者に対し、以下の2つの観点から対応を検討します。
医療機関の毅然とした対応は、問題解決や再発防止のためにも重要になります。
- 1.民法上の責任
-
携帯電話を投げつけられたことにより職員がケガを負った場合、行為者である患者に対して損害賠償請求を検討します。
- 2.刑法上の責任
-
職員に携帯電話を投げつける行為は刑法第208条の暴行罪に、またケガを負っている場合には刑法第204条の傷害罪に該当する可能性があります。
この場合、警察に対する被害届の提出を検討します。刑法
(傷害)
- 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行)
- 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
迷惑行為の分析
事件発生後、医療安全委員会等で事件の原因分析を行うとともに、再発防止策の検討を行います。
ここで重要なのは、現場任せにせずに、医療安全委員会等を中心とした組織的な対応を行うことです。
以上、ハラスメント発生時の現場対応について解説してきましたが、ペイシェントハラスメントの最前線に立たされやすい受付や事務職を守るための初動対応について、以下の記事(実務編①)で詳しく解説しています。

ペイシェントハラスメントを組織的に対処した医療機関の成功事例
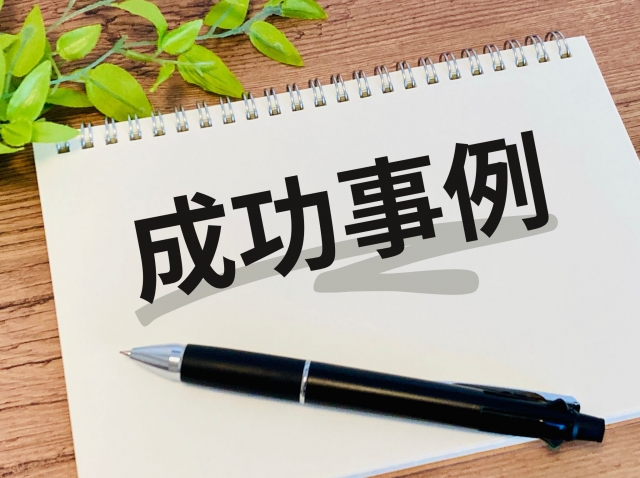
最後に、患者等からの迷惑行為やペイシェントハラスメントに対して組織的に対応した医療機関の事例を2つ紹介したいと思います。
事例①:医療メディエーターの配置と相談・苦情対策検討会議の設立
まず、厚生労働省が運営する「いきいきと働く医療機関サポートWEB いきさぽ」から以下の事例を紹介します。
【施設概要】
- 施設名:神奈川県立がんセンター
- 病床数:395床
- 職員数:736人(平成29年度数値)
【テーマ】
- 「医療メディエーター」の配置と「相談・苦情対策検討会議」の設立による、医療職が働きやすい環境の整備
【取組のきっかけ】
- 近年、患者や家族からの苦情や暴言が増加。
- 相談部門における窓口対応職員が大変苦慮し疲弊している状況。
- 組織全体で対応する仕組みがなく、がん相談員や各部署、事務職員などでその都度、初期対応を行っていた。
- 患者家族からのクレームは、職員や職種間の人間関係などにも影響していた。
【取組内容】
- 平成27年4月より県立病院機構5病院に医療メディエーターを配置。
- 当該病院は医療メディエーターを専従配置とした。
- 医療メディエーターは、病院長の指示のもと組織横断的に活動。
- 医療職と患者の中立的な立場を保ち、患者と医療職双方の意見を聴きつつ対応。
- 基本は各部署で初期対応。第三者が介入すべき事例のみ医療メディエーターが介入。
- 職員に医療メディエーターの役割を理解してもらう取り組み実施。
- 病棟や部署ラウンドで、早めに情報収集しコンフリクトになりうる事柄の早期発見に努めた。
- 平成30年12月に組織した「相談苦情対応検討会議」にて月1回、事案共有と対策の検討。
【取組の成果】
- 医療職全体(特に医師)の精神的負担の軽減
- 苦情解決件数の増加
- クレームやハラスメントの早期対応解決(期間の短縮)
- クレームやハラスメントの問題が大きくなることへの予防
- 医療メディエーターが介入してからは、訴訟案件がゼロ
【院内の反応】
- 主に医師からの介入要請が増加。
- 早期に医師や看護師から介入依頼が来るようになっており、医師や看護師の精神的負担軽減につながった。
- それまで医師の精神的負担が看護師等の医療職にも影響していたが、その他医療職の精神的負担が減少した。
- 職員同士の対立も第三者的な立場で解決策を見いだせるような場作りができた。
- 医療メディエーターの院内での認知向上は、上席医師からの依頼がきっかけになった。
- 上席医師の体験が後輩医師へ伝わり、他の医師や看護師等に広まった。
【課題】
- 医療メディエーターだけではなく、医療職自身が患者とのコミュニケーションスキルを高め、相談・苦情対応を円滑に対応していく。
- 毎年中堅管理職以上の職員に医療メディエーション基礎研修を行い、日常業務からメディエーターマインドで対応できる職員育成を継続して行う。
出典:いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ) (mhlw.go.jp) Microsoft PowerPoint – R3年度好事例集
事例②:トップ主導によるマニュアル策定とHPへの対応方針公開、患者相談室発足
次に、厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」から以下の事例を紹介します。
【施設概要】
- 施設名:A病院
- 職員数:約1,000人
【テーマ】
- トップの意識の高さからマニュアル策定やHPへの対応方針を公開
【取組のきっかけ】
- 件数は多くないものの、患者やその家族によるクレームや迷惑行為が発生していた
- 従業員の相談先も必要となっていた
- 病院として患者・家族による迷惑行為を重要かつ深刻な問題と捉えていた
- 理事会ではかねてよりペイハラ対策の必要性について議論されていた
【取組内容】
- トップ主導による方針公開とマニュアル策定
①2017年より「迷惑行為に関する対応方針」を病院HPで公開
②医療の質を維持しつつ、患者・家族に守ってほしいルールを明確に提示
③理事の経験をもとに対応マニュアルを策定し、HPでも案内 - 窓口の統合と患者相談室の発足
①従来患者向けだった相談室を、患者・従業員双方の相談窓口として統合
②2023年4月、患者相談室を発足
③週1回の現場巡回・ヒアリングで情報収集・現場との連携強化 - 相談対応と事実確認の徹底
①相談は現場スタッフ・患者双方から情報収集
②相談事案は月1回の検討会で協議し、慎重な対応を実施
③必要に応じて院長・医療安全センターとも連携 - 院内周知・院外発信の工夫
①方針を院内の目立つ場所に掲示し、患者・家族にも視覚的に周知
②HPで対応方針を公開し、他医療機関にもマニュアルを提供
③外部医療機関との情報交換・ネットワークづくりにも寄与
【取組の成果】
- 管理者間の情報共有が活発化
- 現場巡回でコミュニケーションが円滑化、現場把握も向上
- 他院との情報交換の機会が増加
【課題】
- 患者相談室への情報集約・全職員への周知が今後の課題
- トラブル事例をマニュアルに反映し、継続的な改訂を推進
- 医療提供側のサービス品質向上を重視し、クレームそのものの減少を目指す(クレーム対応研修・接遇教育)
まとめ:経営者として職員を守る! ペイシェントハラスメントへの長期的な防止策
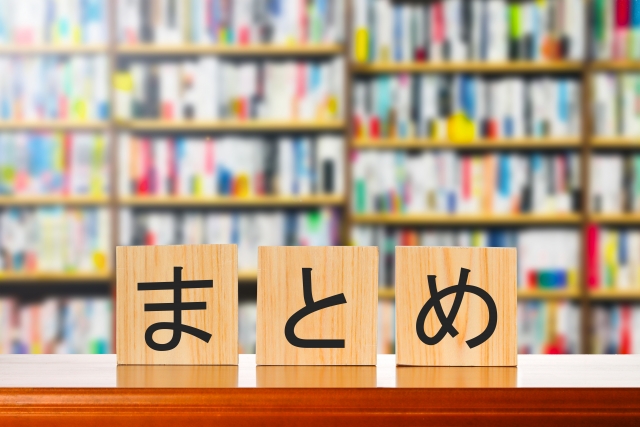
今回は、ペイシェントハラスメントの具体的対応策やリスクマネジメント強化の方策について解説しました。
ここまで見てきたとおり、ペイシェントハラスメント対策は「マニュアル」や「体制」を整えただけでは機能しません。
現場の職員が声を上げやすく、管理職が異変に気づきやすい土壌があってこそ、初動対応や組織対応が実際に回り始めます。
こうした土壌づくりの根幹にある考え方が「心理的安全性」です。
ペイハラ対策・安全配慮義務・離職防止を横断する上位概念としての心理的安全性については、以下の記事で詳しく整理しています。
▶ 医療機関における心理的安全性とは?ペイシェントハラスメント・安全配慮義務・離職リスクを下げる実務設計
患者やその家族による一方的な迷惑行為は決して許されるものではありません。しかし、こうした残念な行為が医療現場で増えているのもまた事実です。
医療機関が考えなければならないことを以下にまとめます。
- ハラスメント行為に毅然とした立場を示すこと
- 組織的にハラスメント対策を講じ、職員が安心して働ける職場環境を作ること
- 全職員に対して継続的な教育を行い、組織全体でハラスメント防止の意識を向上させること
- 職員のメンタルヘルスケアサポート体制を充実させ、離職防止を図ること
これらを実行していく前提には、トップが高い意識を持ち、患者やその家族、診療に関わる全ての関係者に対し、強いメッセージを発信し続けていくことが重要です。
本記事で整理した内容を、院内でどのように具体化するかが次の課題となります。
法改正を見据え、医療機関として“体制整備”を進めるなら

2026年10月に予定されている労働施策総合推進法改正施行を見据え、ペイシェントハラスメント対応は「努力義務」ではなく、実質的な組織責任の問題になりつつあります。
現場対応に委ねたままでは、管理職の判断も曖昧なままで、対応が属人化し、結果として職員の疲弊や離職、さらには安全配慮義務上の問題へと発展しかねません。
経営・管理職が整えるべき3つのポイント
- 初動対応の判断基準を統一すること
- 管理職が迷わないフローを可視化すること
- 職員に「守られている」と伝わる体制を整えること
これらは、マニュアル配布だけでは実現できません。
組織としての共通理解が不可欠です。
実務に落とし込むための研修設計
当事務所では医療機関向けに、
- 初動対応の実践フロー整理
- 安全配慮義務との関係整理
- 心理的安全性を踏まえた組織設計
- 院内周知と管理職向け判断基準づくり
を含む実践型研修を行っています。
単なる講義ではなく、「院内で実装できる形」に整理することを目的としています。
研修内容はこちらからご覧いただけます。
次年度(4月以降)の研修計画をご検討中の医療機関様へ
この時期は、多くの医療機関で次年度の研修計画や体制整備方針が検討される時期です。
昨年度も、本記事をご覧になった医療機関様から研修のご依頼をいただいています。
法改正を機に、ペイシェントハラスメント対応を体系的に整理したい場合は、早めのご相談をおすすめします。
▶ ペイシェントハラスメント対応研修のご相談フォームはこちら





