精神障害の労災請求件数が増加の一途をたどっています。
特に医療・福祉業界では、直近5年間で労災請求件数が2倍を超えるなど、医療従事者の精神疾患が増えています。
恐らく皆様の職場でもメンタル不全のスタッフが増え、どのようにサポートしていいか悩みが尽きないのではないでしょうか。
医療機関におけるメンタルヘルス対策は、制度を整えるだけでは機能しません。
実際に職員と日常的に接している管理職が、早期に変化に気づき、適切に対応できるかどうかが鍵になります。
それが「ラインケア」です。
ラインケアは、単なる気配りではなく、医療機関における安全配慮義務を具体化する重要な実務対応の一つです。
今回は、医療機関の管理職が認識しておくべきラインケアの具体的な実践方法やメリットについて、安全配慮義務の視点も含めて解説します。
ラインケアの基本とは?今すぐ始めるラインケア
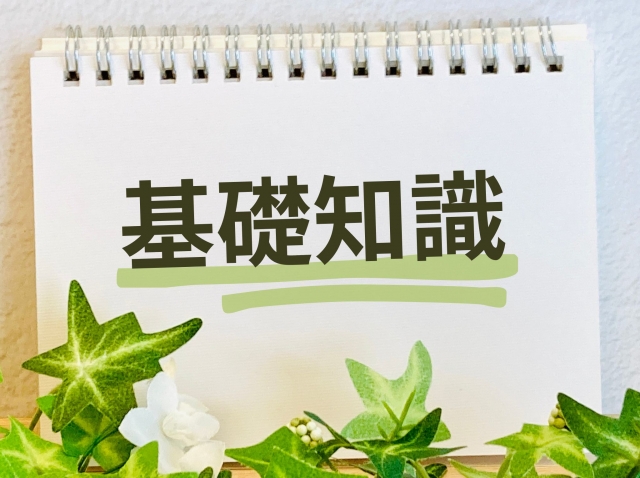
ラインケアとは?
ラインケアとは、職場の管理職が、職場環境の改善や従業員のメンタル不全に気づき、相談を行い、産業医との連携を図ることを言います。
ラインケアは、厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(以下、「メンタルヘルス指針」と言う)で示す「4つのケア」のひとつとして定められています。
厚生労働省が示すメンタルヘルス指針では、「ライン」を以下のとおり定義しています。
「ライン」の定義
ラインとは、「日常的に労働者と接する、職場の管理監督者(上司その他労働者を指揮命令する者)をいう。」
引用:職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
「4つのケア」の中のラインケア
厚生労働省が示すメンタルヘルス指針の「4つのケア」とは、以下の4項目です。
- セルフケア(労働者による)
- ラインによるケア(管理監督者による)
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(産業医・衛生管理者等による)
- 事業場外資源によるケア(事業場外の機関・専門家による)
「4つのケア」のうち2番目に挙げられている「ラインによるケア」が、本記事のテーマです。
「1.セルフケア(労働者による)」に関しては、看護師のストレスマネジメントの重要性に関する以下の記事で解説してます。
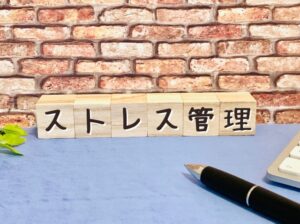
なお、「4.事業場外資源によるケア」の代表例が外部EAPです。
特に人材不足の医療機関による外部EAPの効果的な活用方法について、以下の記事で解説しています。

ラインケアの重要性:安全配慮義務とは?
冒頭でも触れたとおり、医療機関の管理者は法令上の義務として、従業員のメンタルケアを行わなければなりません。
その根拠は、
- 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
- 労働安全衛生法第3条(事業者等の責務)
によって定められている「安全配慮義務」です。
安全配慮義務とは、労働者が健康かつ安全に働ける環境を提供するために、雇用者が負う法的義務のことです。
安全配慮義務には、
- 「健康配慮義務」
- 「職場環境配慮義務」
の2つがあります。
医療機関は、この安全配慮義務によって、ラインケアを始めとするメンタルヘルスケアの体制を職場に整備する必要があるのです。
| 安全配慮義務 | |
| 健康配慮義務 | 職場環境配慮義務 |
| 健康診断の実施、勤務時間管理、メンタルヘルス対策など | 作業環境の整備、過重労働防止、職場におけるいじめ防止、ハラスメント対策など |
ラインケアは、安全配慮義務を現場で具体化するための重要な取り組みです。
この点について、医療機関における安全配慮義務の法的視点と体制整備の実務対応をまとめた総論記事で詳しく解説しています。
ラインケアの概要
ラインケアで行うべき項目は、主に以下の4点です。
- 教育研修、情報提供
- 職場環境等の把握と改善
- メンタルヘルス不調者への気付きと対応
- 職場復帰における支援
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.教育研修、情報提供
メンタルヘルス指針によると、事業者は、労働者自身が行うセルフケアを促進するために、全ての労働者に対して、教育研修や情報提供を行うこととされています。
また、労働者のほか、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対しても、それぞれの職務に応じた教育研修・情報提供を実施する必要があります。
2.職場環境等の把握と改善
日常業務から職員の意見聴取をすることや任意のアンケート実施、定期的なストレスチェックを実施して、職場環境の現状把握を行います。
事業者はその結果を活用し、職場環境の評価や問題点を洗い出し、改善を図るとともにメンタルヘルス不調の未然防止を図る必要があります。
3.メンタルヘルス不調者への気付きと対応
職員のメンタルヘルス不調に対しては、早期発見と適切な対応が重要です。
そのために、事業者には以下の体制整備が望まれています。
- 労働者による自発的な相談とセルフチェック
- 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応
- 労働者の家族による気付きや支援
4.職場復帰における支援
メンタルヘルス不調で休業した労働者が復職する際、円滑に職場復帰し、就業を継続できるような取組が大事です。
そのために、事業者には以下の取り組みが望まれています。
- 安全衛生委員会等での調査審議
- 職場復帰支援プログラムの策定・体制整備
- プログラム実施による労働者支援
兆候を見逃さない!部下のメンタルヘルス問題に早期対応する方法

医療従事者特有のメンタルヘルス問題
近年、医療従事者の職場での精神障害が増えています。
以下のとおり、2024年度の医療・福祉業の精神障害労災請求件数は983件で、5年前の2019年度の426件と比較すると2倍以上の伸びになっています。
全業種のうちの割合をみても、26.0%と全体の4分の1以上が医療・福祉業であることがわかります。
なお、2024年度の労災請求件数全体の15.6%が介護事業が占め(全業種で最多)、医療業は全業種で2番目に多い10.3%となっています。
| 全業種 | 医療・福祉 | 割合 | |
| 2019年度 | 2,060件 | 426件 | 20.7% |
| 2024年度 | 3,780件 | 983件 | 26.0% |
また、職種別にみても、看護職が全ての職種の中で2番目に多い職種になっています。
- 1位:一般事務従事者
- 2位:保健師・助産師・看護師
- 3位:商品販売従事者
医療従事者の精神障害の実態については、下記の記事で詳しく取り上げています。

精神障害の要因となる出来事とは?
前掲のデータが示すように、医療機関では職員のメンタルヘルスケアについて、特に注意深く、組織的に実践していく必要があることがわかりました。
それでは、職場で起きたどのような出来事が、職員の精神障害につながっているのでしょうか。労災の資料から要因を探っていきます。
2024年度全業種の精神障害における労災支給決定の要因となった具体的な出来事トップ3をまとめると、以下のとおりとなりました。
| 具体的な出来事 | 支給決定件数 | うち自殺 | |
| 1位 | 上司等からパワハラを受けた | 224件 | 10 |
| 2位 | 仕事内容・仕事量の大きな変化 | 119件 | 21 |
| 3位 | 顧客等から著しい迷惑行為を受けた | 108件 | 1 |
原則として、ラインケアでは、管理監督者である上司が、直属の部下に対するメンタルヘルスケアのキーパーソンになります。
上記のデータをみると、その原則に反して、上司との関係が部下の精神障害の発症に大きく影響していることがわかります。
医療機関の管理者や所属長はこの現実に目を向けて、組織的なメンタルヘルスケアの体制づくりを行うことが重要になります。
部下の不調を早期発見するポイント
繰り返しになりますが、ラインケアでは、管理監督者が職場のメンタルヘルスケアのキーパーソンとなります。
ラインケアのポイントは、「いつもと違う」部下に上司が早く気付くことです。
そのためには、日頃から部下の業務の進捗はもちろんのこと、言動や人間関係についても関心を持つことが大事です。
もし下記の様子が部下に見受けられたら、上司として速やかな対応が求められます。
- 遅刻・欠勤(無断欠勤含む)の増加
- 業務効率の低下
- 「報・連・相」の頻度の減少や遅れ
- 会話の減少(またはその逆)
- 表情や動作に活気がない(またはその逆)
- 不自然な言動やミスの増加
- 服装や容姿の乱れ など
部下の不調に適切に対応するポイント
「いつもと違う」部下に気付いたら即対応
上司は、部下の体調や様子の異変に気付いたときは、直接の声掛けや産業保健スタッフとの連携をとおして、適切な対応をとる必要があります。
早急な対応が求められますので、下記の流れを職場に根付かせることが大事です。
「いつもと違う」部下に気付いたら…
①まず部下の話を聴く(積極的傾聴)
↓
②部下を産業医等へ案内
もしくは
上司が産業医等へ相談に行く
部下からの相談への積極的対応
上司は部下の体調面を含めて、日常業務から積極的に声掛けに努めることが大事です。
また、普段から相談しやすい雰囲気をつくるなどして、部下から自発的な相談を促すよう努めることも大事になります。
以下の記事では、医療機関での1on1導入によるコミュニケーション活性化の方策について解説しています。
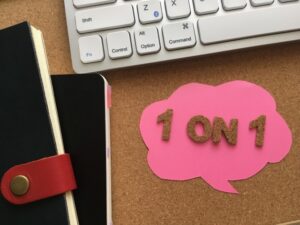
メンタルヘルス不調の部下に対する職場復帰支援
メンタルヘルス不調で休職をした部下が復職する際、上司は休職者の気持ちを汲み取って、精神的な負担を軽減することが望まれます。
もしかすると休職者は心の声で、このようなことをつぶやいているかも知れません。
- 「周りのスタッフに自分はどう思われているのか…」
- 「復職してうまく適応できるのか…」
- 「復職して病気がまた悪くなるかも知れない…」
上司は休職者の心の声にも耳を傾けながら、職場復帰の支援をすることが大事です。
ラインケアを組織文化として根付かせるための効果的な戦略

組織文化に根付かせることの重要性
増え続ける医療従事者のメンタルヘルス不調に適切に対応することは、医療機関にとって重要な経営課題です。
ラインケアを含めたメンタルヘルス対策の取り組みを医療機関全体の組織文化として根付かせることは、医療人材の確保や生産性向上の面からも非常に重要と考えます。
今後さらに人材不足が進展していく医療業界において、メンタルヘルスケアの文化が根付いた組織は、職場としての相対的な強みにもなり得ます。
組織全体での取り組みが必須条件
組織文化として職場にメンタルヘルスケアを根付かせるためには、医療機関をあげて全職員で取り組む必要があります。
そのためには、まず、管理者層によるトップ会議でメンタルヘルス対策の重要性を共通認識として持ち、院長によるトップダウンで強い意思をもって取り組んでいくことが大切です。
【事前準備】トップ会議で決定
↓
【事前準備】安全衛生委員会で運用審議
↓
【改善STEP➊】職場環境の現状把握
↓
【改善STEP➋(1)】リーダー会議で説明
↓
【改善STEP➋(2)】ワーキンググループ編成
↓
【改善STEP➋(3)】ラインケア研修(管理職向け)
↓
【改善STEP➌~❺】職場環境改善計画の作成・実行・効果測定
職場環境改善の5つのステップ

ここでは、メンタルヘルス対策に向けた職場改善の5つの手順を解説していきます。
改善STEP➊:職場環境の現状把握
職場環境を改善するためには、部署ごとにストレス要因の現状を知る必要があります。それには、所属長による日々の観察や声掛け、ストレスチェックの診断結果などが判断材料になります。
さらに、職場の快適度を測るチェックツール「職場の快適度チェック」を活用して、職場環境の現状の判断材料とすることもできます。
「職場の快適度チェック」は、職場のソフト面(人間関係等心理的側面)における現状把握や問題点の発見、具体的な職場全体の取り組みに活用するためのツールです。
厚生労働省が運営するサイト「こころの耳」で詳しく解説していますので、以下のリンクからご参照ください。
- 手順1:職場の快適度チェックの実施
現場の管理者と従業員双方で調査実施 - 手順2:集計結果の評価・分析
各職種・部署、全体の平均値を集計、問題点抽出 - 手順3:評価・分析結果の報告等
安全衛生委員会等に報告・承認後、速やかに職場へフィードバック
改善STEP➋:職場環境改善に向けた組織づくり
「職場の快適度チェック」等で現状把握ができたら、改善につなげるための組織づくりを行います。組織づくりの主な手順は以下のとおりです。
- (1)リーダー会議で説明
-
組織づくりで重要になるのは、職場改善のカギを握る各部署の所属長の理解と協力です。リーダー会議等で所属長に「職場の快適度チェック」の結果報告と今後の方針を説明し、改善への協力を促します。
- (2)ワーキンググループ編成
-
また、現場に即した具体的な施策を推進するために、安全衛生委員会の下部に、職場環境改善のワーキンググループを組織し、定期的にミーティングを行います。
- (3)ラインケア研修(管理職向け)
-
次に、ラインケアのカギを握る管理職に対してラインケア研修を行います。そこで注意しなければならないのは、管理職に対する精神面への配慮です。
管理職の多くはプレイングマネージャー化しています。マネジメント業務の傍ら自身が抱える業務に追われています。
そうした状態で、新たな取り組みとしてメンタルヘルス対策が重なれば、管理職にとって大きな負担になる可能性があります。
ラインケア研修を企画する際には、管理職への動機付けがポイントになります。以下の2点に意識して研修を企画することが大事です。ラインケア研修における管理職への動機付けのポイント
- 管理職の負担の大きさへの理解
トップ層が管理職の日常業務と職員のマネジメントに苦慮していること、ラインケアの負担の大きさを理解する。 - 管理職の経験と知恵を活かして「良好なサイクルを回す」
研修ではグループワークを取り入れ、これまで管理職として蓄積してきた経験と知恵を活かして、「良好なサイクルを回す」こと伝える。
グループワークでは、以下の手順で動機付けできれば、管理職に精神的な負担を余分にかけずに取り入れることができると考えます。
グループワークで「良好なサイクルを回す」方法
- 今までしてきたことを振り返る
- うまくできている点を評価する
- できていることは意識して続ける
- 周りから聞いた良い行動を取り入れる
- 取り入れた行動を継続する
- 再び1の振り返りからサイクルを回していく
また、グループワークでは、同じ職位(課長同士など)でグループ分けすることもポイントのひとつです。
以下のように、同じ立場にいる職員との意見交換は腹落ちしやすく、新たな行動として受け入れやすくなるからです。グループワーク参加者の気づき
- 「なるほど、彼はそんな風にしてるんだ…」
- 「あのやり方は自分も使えそうだな…」
- 「自分が体験談として話したことも周りはうなずいてくれたな…」
なお、医療機関における管理職のストレス対策については、以下の記事で詳しく取り上げていますのでご参考ください。
あわせて読みたい 医療機関の管理職が抱えるストレスとは?組織にもたらす影響と対策 管理職が「罰ゲーム化」していると言われています。近年、現在の会社で管理職になりたいと思う人の割合は低下傾向を続け、全体の2割を切る状況です。直近の調査によると…
医療機関の管理職が抱えるストレスとは?組織にもたらす影響と対策 管理職が「罰ゲーム化」していると言われています。近年、現在の会社で管理職になりたいと思う人の割合は低下傾向を続け、全体の2割を切る状況です。直近の調査によると…参考:令和2年度「ラインによるケアの実践」|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)
- 管理職の負担の大きさへの理解
改善STEP➌:職場環境改善計画の作成
ワーキンググループを中心に職場環境改善計画を立てます。
改善計画は実施期間を定め、期間終了後に効果測定を行うよう計画します。
計画作成の際には、ストレスチェックや「職場の快適度チェック」などのツールを活用し、労働者や所属長の代表者の意見を組み入れながら議論のうえ立案することが望まれます。
改善STEP❹:職場環境改善計画の実行
立案した改善計画を実行に移します。
ワーキンググループで計画どおり施策が進んでいるか、運用上の問題点が発生していないかなど、進捗を確認していきます。
忙しい医療現場において最大の懸念は、計画倒れになることです。そうならないためにも、ワーキンググループの定期開催時に、必ず進捗確認を議題のひとつとして進行することが重要です。
改善STEP❺:職場環境改善計画の効果測定
改善計画の実施期間が終了したら、効果測定を行います。
取り組み前に実施した「職場の快適度チェック」を再度行い、結果を比較して取り組みに対する成果面を数値で確認します。
また、取り組みのプロセス面についても、ワーキンググループで
- 計画どおりにできた施策
- 計画通りにできなかった施策
を挙げて評価を行い、今後の取り組みの課題とします。
ラインケアがもたらす職場全体の生産性向上と働きやすさの改善

ラインケアが職場にもたらすメリット
ラインケアは、医療現場で働く職員のメンタル不全を防止する側面だけではなく、職場全体にポジティブな影響を与えます。
メリット➊:職場に安心感が生まれる
ラインケアを含めたメンタルヘルスケアの組織的な取り組みは、職員が悩みを抱えた場合の拠り所ができるとともに、職員に対して働いていくうえでの精神的な安心感を与えます。
メリット➋:働きやすさが向上する
集中して業務に取り組むことができ、職員個々の能力を最大限に発揮して、いきいきと働くことができるようになります。
メリット➌:生産性が向上する
職員の能力が発揮されることで、職場全体の生産性が向上し、医療の質の向上や経営の安定化につながります。
メンタルヘルス・マネジメント検定受験の組織的取組
メンタルヘルスケアを職場に根付かせ、医療機関の生産性向上を図る方法のひとつとして、「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」の受験促進があります。
ここでは「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」の概要と、企業の取り組み事例を紹介します。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験の概要
試験の概要は以下のとおりです。
- 主催
大阪商工会議所 - 試験区分
公開試験及び団体特別試験がある - 受験コース
職位・職種別(対象別)に3つのコースを設定
※どのコースから受験してもよい
①Ⅰ種(マスターコース)
人事労務担当者・経営者向け
受験料:11,550円
②Ⅱ種(ラインケアコース)
管理職向け
受験料:7,480円
③Ⅲ種(セルフケアコース)
一般職員向け
受験料:5,280円 - 試験日
年2回 (3月:Ⅱ種・Ⅲ種 11月:Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種)
参考までに、2025年11月に実施した公開試験の合格者等をまとめましたのでご覧ください。
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| ①Ⅰ種(マスター) | 1,710人 | 331人 | 19.4% |
| ②Ⅱ種(ラインケア) | 12,887人 | 6,160人 | 47.8% |
| ③Ⅲ種(セルフケア) | 5,139人 | 3,347人 | 65.1% |
※「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」ホームーページより引用
メンタルヘルス・マネジメント検定試験の組織的取組事例
次に、メンタルヘルス・マネジメント検定試験を活用して、組織的な取り組みを行っている企業の事例を紹介します。
| 企業名 | 取組事例 |
| 日本郵便㈱ | 合格者に報奨金支給 |
| 大同生命保険㈱ | 職位任用者全員Ⅱ種【ラインケアコース】」を取得。Ⅰ種・Ⅲ種も、希望者には受験料を補助し取得を推奨。 |
| ㈱日立ソリューションズ・クリエイト | Ⅱ種の管理職(課長職)100%取得を全社的に推進 |
| 川田工業㈱ | Ⅱ種の合格を管理職要件に設定 |
| 日本情報通信㈱ | 管理職全員Ⅱ種取得を必須とし、報奨金を支給 |
| 大和ハウス工業㈱ | Ⅱ種の合格者には祝金を支給 |
| アライ興産㈱ | 入社後、管理職に就くまでにⅢ種、管理職でⅡ種の取得を推進。受験料を補助。 |
※「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」ホームーページを参考に筆者作成
ラインケアが機能しない医療機関の共通点

ラインケアは制度として導入していても、実際には十分に機能していない医療機関も少なくありません。
その背景には、いくつかの共通した構造的課題があります。
①面談が「業務確認」に終始している
定期面談が行われていても、内容が業務進捗やシフト調整の確認にとどまり、心理的負担や職場環境への違和感まで踏み込めていないケースがあります。
ラインケアは「問題が起きてからの対応」ではなく、「小さな変化に気づくための対話」です。
面談の目的を明確にし、メンタルヘルスの観点を組み込んだ質問を用意する必要があります。
②管理職への教育機会が不足している
「管理職が気づくことが大事」と言われながら、実際にはラインケア研修を受けていないケースも多く見られます。
- 不調の初期サインとは何か
- 声のかけ方の具体例
- 対応後の記録方法
- 産業医や外部資源へのつなぎ方
これらを体系的に学ぶ機会がなければ、ラインケアは属人的対応にとどまります。
教育と実践機会のセット化が不可欠です。
③不調者対応が「個人の力量」に依存している
経験豊富な管理職のいる部署では対応できていても、異動や退職によりノウハウが失われるケースがあります。
ラインケアは「人に依存する仕組み」ではなく、「組織として再現可能な仕組み」でなければなりません。
- 対応フローの明文化
- 相談記録の標準化
- 判断に迷った場合のエスカレーションルート整備
これらを整えることで、組織としての安全配慮義務履行の裏付けになります。
④記録が残っていない
ラインケアを実施していても、記録が残っていなければ、後日トラブルが発生した際に「組織として何をしていたのか」を説明できません。
安全配慮義務の観点からは、
- いつ
- 誰が
- どのような対応を行ったのか
- 次のフォローはどうするのか
を最低限記録する仕組みが必要です。
これは管理職を守るためでもあり、組織を守るためでもあります。
ラインケアを「仕組み」として設計できているか
ラインケアが機能しない医療機関の多くは、「大切だと分かっている」状態で止まっています。
重要なのは、
- 教育
- 実践
- 記録
- エスカレーション
を組み込んだ体制整備として設計することです。
ラインケアは、管理職の善意に任せる取り組みではなく、医療機関としての安全配慮義務を具体化するための実務対応の一部であるという認識が不可欠です。
実践者に学ぶ!ラインケア導入で成果を上げた施設の事例
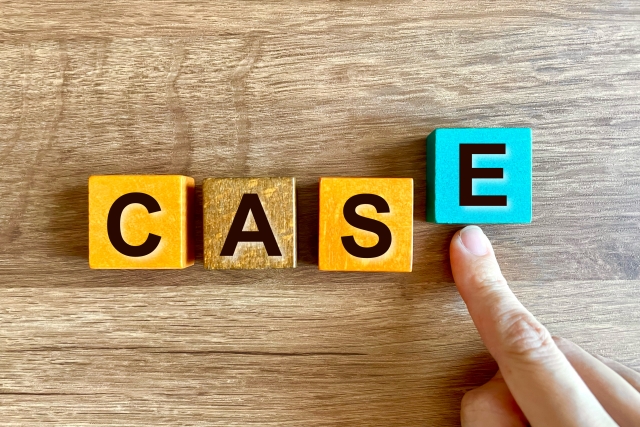
最後に、ラインケアを導入して職場改善の体制整備に取り組んだ介護福祉施設の事例を紹介します。
- 導入事業所
・社会福祉事業(介護福祉施設)
・労働者数307名(男性63名・女性244名)
・平均年齢42.5歳 - テーマ
「組織全体で取り組むための体制づくりと、“めんたる案内所”の開設」 - 取り組みのきっかけ
・めまぐるしい制度改正と慢性的な職員不足で、職員は多大なストレス要因を抱えて仕事をしている
・職員の心と体が健康でなければ、良い介護サービスは提供できない
・サービス利用者のためにも、職員の「心の健康づくり」に取り組まなければならない - 組織全体で取り組むために行った施策
・心の健康づくり体制図の作成
・ライン管理者を中心とする相談体制の確立
・メンタルヘルス委員会発足、「めんたる案内所」の開設
・産業医の役割の明確化
・地域の医師会相談窓口との連携体制整備
・ラインケアマニュアル、セルフケアマニュアル作成
・ラインケア研修、セルフケア研修実施」 - 取り組みの効果
『メンタルヘルスについてさまざまな情報が飛び交う中で、マニュアルや研修で正しい知識を身につけ、ストレス対策に意識が向いたことは大変大きな効果であると思います。』 - 今後の課題
『整備した体制を維持していくと共に、突発的な出来事に対応できる、更なる体制整備が必要であると感じます。不調を訴える職員が出なくても、「予防」「早期発見」の視点で、メンタルヘルス推進委員会をはじめライン管理者が、常に新しい情報に耳を傾けていることが大切です。』
引用:厚生労働省「心の健康づくり事例集~職場におけるメンタルヘルス対策~」
<83818393835E838B8E9697E18F575044462E706466> (mhlw.go.jp)
まとめ
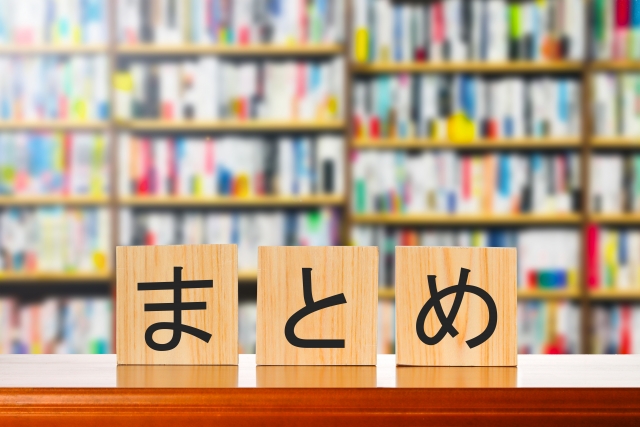
今回は、医療機関が認識しておくべきラインケアの具体的な実践方法や、職場環境全体に与えるメリットについて解説しました。
人の命を扱う医療従事者は、どんなに忙しくても常に緊張度を高く保ちながら、正確に業務を遂行しなければなりません。
こうした業務の性質そのものに加え、不規則な勤務や長時間労働、職員同士や患者・家族との人間関係などで精神的に思い悩む職員がいてもおかしくない状況です。
職員を守るために医療機関をあげてメンタルヘルス対策に取り組むことは、組織運営上の義務を果たすことでもあり、経営上の重要課題達成の原点にもなるのです。
ラインケアは「努力義務」ではなく体制整備の一部
前述したように、ラインケアは管理職の善意に委ねるものではありません。
医療機関として体制整備を行い、教育・仕組み・記録を含めて「実装」することが、安全配慮義務を果たすうえで不可欠です。
▶ 医療機関における安全配慮義務違反のリスクと体制整備の実務対応は、以下の総論記事で詳しく解説しています。

今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。









