管理職が「罰ゲーム化」していると言われています。
近年、現在の会社で管理職になりたいと思う人の割合は低下傾向を続け、全体の2割を切る状況です。
医療・福祉・教育分野も同様に低下傾向が続いています。直近の調査では全体の1割強の人しか管理職を希望していないとの結果が出ているようです。
いまの管理職は、人材育成などのマネジメント業務はもとより、働き方改革の対応を始めとしたコンプライアンス遵守や事業における自部署の成績向上まで求められています。
以前より管理職に与えられた課題は確実に増加していると言えます。その一方で、管理職に対する組織的なケアが行われているとはとても言い難い状況です。
今回は、医療機関が管理職自身のメンタルヘルスケアをいかに実践していくべきか、解説していきたいと思います。
世の管理職の負担感を探る

実際、世の管理職にはどのくらいの業務負荷がかかっているのでしょうか。
始めに、パーソル総合研究所が行った「中間管理職の就業負担に関する定量調査」(2019年2~3月実施・【中間管理職調査】n=2000【企業調査】n=300)を参考に、管理職の業務負荷の実態について探っていきたいと思います。
働き方改革が進むほど「中間管理職の負担感は増している」
この調査は、働き方改革が始まった2019年とその前年の2018年において、「働き方改革が進んでいる企業群」と「働き方改革が進んでいない企業群」を比較して行っています。
調査の結果、「働き方改革が進んでいる企業群」の方が、「中間管理職の負担感は増している」ということがわかりました。
| 働き方改革が進んでいる企業群 | 働き方改革が進んでいない企業群 | |
| 中間管理職自らの業務量の増加 | 62.1% | 48.2% |
| 組織の業務量の増加 | 69.0% | 36.3% |
| 人手不足 | 65.7% | 44.2% |
| 時間不足から付加価値を生む業務に着手できない | 56.9% | 42.3% |
パーソル総合研究所「中間管理職の就業負担に関する定量調査」を参考に著者作成
負担感が高い管理職ほど「残業が増えた」「仕事の意欲が低下した」
また、中間管理職を負担感の高さに応じて「高群」、「中群」、「低群」に分けて調査が行われました。
その結果、負担感が「高群」の管理職の方が「低群」の管理職と比べて、「残業が増えた」などの様々な問題点を高い割合で抱えていることがわかりました。
| 高群 | 低群 | |
| 管理職になって残業が増えた | 47.7% | 40.2% |
| 管理職になって仕事の意欲が低下した | 23.8% | 18.6% |
| 転職したい | 27.0% | 20.0% |
| 学びの時間が確保できていない | 63.0% | 41.1% |
| 時間不足から付加価値を生む業務に着手できない | 64.7% | 38.7% |
パーソル総合研究所「中間管理職の就業負担に関する定量調査」を参考に著者作成
管理職に対するメンタルヘルスケアは医療機関の重要課題
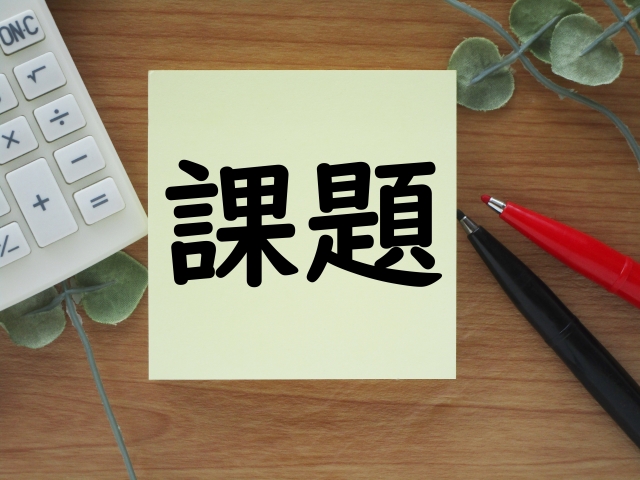
前掲の資料をみて、医療機関で働く管理職の皆さんはどのように感じたでしょうか。
「自分も同じだ」と感じた方がほとんどではないでしょうか。
業務の複雑性によって重圧がかかる管理職
医療機関では、日々の患者対応や自部署のマネジメントの他にも、医療制度の改正への対応、医療安全や感染対策、医療の質向上などの要素も加わり、業務の複雑性がさらに高まっています。
管理職としてのプレッシャーや責任感から、多くの人が少なからずストレスを抱えていると思います。
- 「このストレスにどう対処すればいいのか…」
- 「将来にわたって管理職としてのキャリアを続けていけるのだろうか…」
このような不安を抱えている人が大半なのではないでしょうか。
管理職層のメンタル不調がもたらす組織の不安定化
医療機関にとって管理職層は、経営の中核とも言えます。
経営の中核をなす管理職層のメンタル不調は、組織の不安定化を招き、これから待ち受ける地域医療構想等、医療制度の改正への対応を難しくさせるでしょう。
医療機関としては、いかに管理職が抱える業務負荷を軽減し、管理職自身のメンタルヘルスケアの支援を組織的に実行できるかが、経営上の大きな課題と言えます。
なお、管理職に限らず、職員のメンタルヘルスケアは事業主に課せられた安全配慮義務のひとつです。医療機関における安全配慮義務の重要性について、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

医療機関で管理職が直面するストレスの原因

次に、医療機関の管理職が直面しているストレスの原因について考えていきたいと思います。
原因①:人手不足と業務過多
人手不足と業務過多は表裏一体の関係と言えます。これは、看護師不足を始めとした多くの医療機関の管理職が抱える大きな悩みとなっています。
人手不足によって職員一人当たりの業務量は増え、業務量が増えるとそれに耐え切れず、休職者や退職者が増えていくという悪循環に陥ります。
不足している職員の仕事のカバーを管理職を含めた部署のメンバーで行う必要がありますので、管理職には人員と業務調整のストレスが当然かかってきます。
以下の記事では、看護師に対するストレスマネジメントの方策について詳しく解説していますので、併せてご参考ください。
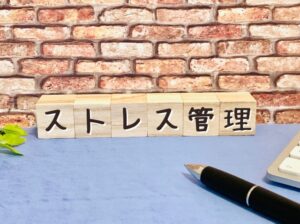
原因②:患者対応のプレッシャー
患者の命を預かる職業であるがゆえに、そもそも緊張から逃れるのは難しいと言えるでしょう。職員それぞれが研鑽を積み、患者ひとりひとりと真摯に向き合う義務があります。
そのなかで、患者本人やその家族からの過度な要求などにも対峙していかなければいけません。患者や家族からのクレームには、管理職が対応することが多くなります。
日々の管理業務と並行して患者のクレーム対応に時間を取られることは、精神的にも身体的にも疲弊していく原因になります。
原因③:経営面での責任感
医療機関は、地域医療の担い手として、安定的な経営を続けなければなりません。そのためには、人材確保と人材育成を進め、医療機器を随時更新し、質の高い医療を提供し続ける必要があります。
医療制度の変化が激しいなか、自部署のマネジメントに留まらず、経営上の参画も管理職には当然求められています。医療の専門性発揮と組織運営遂行の両面への対応に負担感が増していきます。
原因④:マネジメント業務と付随業務の負担
精神障害の労災請求件数が、全業種の中で最も高いのが医療・福祉業と言われています。医療機関の管理職は、人手不足のなか、自部署のメンタル不調者の対応もしなければなりません。
そうした管理業務もありつつ、管理業務以外にも組織全体の委員会活動や各部門で設けた委員会や研修、学会活動があります。それらの付随業務の負担ものしかかっているのが、医療機関の管理職の現状と言えます。
医療業における精神障害労災請求件数の増加について、以下の記事で詳しく紹介しています。併せてご参考ください。

原因⑤:交代制勤務による疲労
管理職と言えども交代制で宿日直勤務や夜勤が発生します。不規則な勤務になれば体調面にも影響を与え、ストレスの要因になっていきます。
不規則な交代制勤務は、年齢を重ねれば重ねるほど、体にこたえてくるものです。
ストレスが管理職自身に及ぼす影響

これまで、医療機関の管理職が抱えるストレス要因についてみてきました。
ここでは、それらのストレスが管理職に及ぼす影響について考えたいと思います。
影響①:心身の不調
日々の業務の過度なストレスにより、疲労感や睡眠障害、うつなど心身の健康に影響を及ぼすことが考えられます。胃潰瘍や高血圧、更年期障害や自律神経失調症など、ストレス関連疾病と呼ばれる病気にもなりかねません。
さらには、近年になって免疫機能の低下やホルモン分泌異常による癌の懸念も叫ばれているようです。
影響②:業務パフォーマンスの低下
ストレスを抱えることで、管理職自身の業務パフォーマンスの低下が懸念されます。管理職自身のパフォーマンスが低下すると、周りのメンバーのパフォーマンスにも影響を与えます。
ストレスを抱えると自分に余裕がなくなるため、自部署の職員に対して、報告・連絡・相談を受ける時間が減る可能性があります。
管理職とメンバーとのコミュニケーションの時間自体が減るのと同時に、コミュニケーションの質の低下もおきます。
そうなると、部署全体のパフォーマンス低下と職場の雰囲気の悪化を招き、医療機関全体の生産性低下ももたらしかねません。
影響③:バーンアウトの危険性
ストレス要因が心身にもたらす影響から、管理職自身のバーンアウトも危惧されます。
業務過多と業務の複雑化、それらに人材不足が重なり、今の管理職自身はプレイングマネージャー化している状況です。身体的にも精神的にも疲弊しきって、退職を決意するケースも十分考えられます。
管理職が自身に実践していきたい5つのストレス対処法

それでは実際、医療機関の管理職はどのようにストレス対策を行えばいいのでしょうか。
以下の5つのストレス対処法を順に解説していきたいと思います。
- 部下に頼る
- セルフケアを実践する
- 健康相談支援を受ける
- キャリアコンサルタントに相談する
- 他の管理職に相談する
ストレス対処法①:部下に頼る
自部署の職員への負担軽減を考えて、管理職自らが仕事を抱えるケースが多いと思います。しかし、それが原因で管理職が体調を崩し、自部署の職員への負担感が逆に増えてしまう悪循環も想定できます。
そうした悪循環がおこらないように、早いうちから部下に頼っていくことが重要です。
「それができれば悩みなんかないよ!」という声が聞こえてきそうですが、部下に頼ることは、結局は部下のためにもなることなのです。
主任や係長クラスへの権限移譲を徐々に進めることができれば、部下の経験値やスキルの向上が期待できます。部下のレベルが上がればその分管理職自身の負荷が軽減され、心身の健康を保つことができます。
ストレス対処法②:セルフケアを実践する
自部署の職員に対するメンタルヘルスケアは、管理職の大事な仕事のひとつです。
しかし、その前に、管理職自身のセルフケアがしっかりできていないと、部下のケアは十分には行えません。
セルフケアとは、労働者自身がストレスのことを知り、予防や対処を行い、健康の保持増進に努めることを言います。
以下にセルフケアの具体例を挙げておきます。
- リラクセーション
- ストレッチ
- 適度な運動
- 快適な睡眠
- 親しい人たちと交流
- 笑う
- 仕事から離れた趣味を持つ
また、カウンセラーの岩崎久志氏は著書のなかで、ストレス対処(ストレス・コーピング)のポイントとして以下のことを挙げています。
- 「あまり大げさに考えないで色々試してみる」
- 「気分転換できる為のツールを身近に用意しておく」
- 「大事なのは質より量」
参考:岩崎久志著「ストレスとともに働く」・晃洋書房
ストレス対処法③:健康相談支援を受ける
最近眠りが浅い、疲れやすい、やる気が出ない、という気持ちが少しでも出たら、カウンセラーへの相談を考えてみるのも一つの方法です。
今の管理職は孤独な戦いを強いられていることが多いと思います。さらに医療の専門家は他人に自身の健康上の相談を持ち掛けづらいという意識も働くようです。
信頼できる誰かに心の内を話すことができれば、精神的にもずいぶんと楽になれるのではないでしょうか。
思い切って産業医などの健康相談支援を受けることや、自院の福利厚生でEAPの制度があれば利用の検討をおすすめします。
ストレス対処法④:キャリアコンサルタントに相談する
身内の人間に自身の相談をするのは気が引ける、という方も多いと思います。このような場合には、外部の専門家に相談してみるのも選択肢の一つです。
キャリア形成支援の専門家・キャリアコンサルタントは、相談者一人一人の悩みや想いに寄り添い、主体的なキャリア形成を支援します。
全国47か所のキャリア形成・リスキリング支援センター及び全国のハローワークに設置しているキャリア形成・リスキリング相談コーナーでは、キャリアコンサルタントによるコンサルティングを無料で受けられるサービスを提供しています。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
ストレス対処法⑤:他の管理職に相談する
同じ職場の管理職も、必ず同じ悩みを抱えています。周りの管理職に相談を持ち掛けるのも、自身のストレス対策に有効だと考えます。
他部署のマネジメント方法や管理職自身のセルフケアの方法まで、成功や失敗事例を含めて管理職同士で情報交換することで、業務上の気づきが得られたり、人に話すこと自体がストレス解消につながるかも知れません。
医療機関が取り組むべき4つの職場のストレス軽減策

最後に、医療機関が組織として取り組むべき対策を4点挙げたいと思います。
- 心身の健康を意識した経営
- 管理職自身のメンタルヘルスケア研修実施
- 健康支援体制の充実や外部EAPの導入
- コミュニケーションの促進
職場の取組①:心身の健康を意識した経営
医療機関で働く職員の心身の健康を守ることは、患者の命や健康を守るための前提として、とても重要な課題と言えます。
前述したとおり、そもそも医療・福祉業は、精神障害の労災請求件数が全業種のなかで最も高い業種であるため、なおさら職員のメンタルヘルスケアに注力しなければなりません。
ここで大事なのは、医療機関がストレスを抱えやすい職場であることを、まず経営トップ層がしっかり認識することから始めることです。
もし、ストレスでメンタル不調に陥った職員が役職者であればあるほど、その職員が経営に与える影響は大きくなります。その職員が院長や副院長だったことをイメージすると分かりやすいでしょう。
健康経営を自院の経営方針に掲げるなどして、経営トップ層から職員の心身の健康維持・増進を啓蒙していくことが重要です。
なお、職場に健康意識を啓蒙するために健康経営アドバイザー資格を活用するのもひとつの方策です。
健康経営アドバイザーは東京商工会議所が認定する資格で、ホームページ内で以下のとおり説明されています。
「健康経営アドバイザーは、健康経営の必要性を伝え、自社内の健康経営への取り組みに必要な情報を提供し、健康経営の実践へのきっかけを作る普及・推進者です。」
出典:健康経営アドバイザー |東京商工会議所
例えば安全衛生委員会の主要メンバーに資格取得を奨励し、職場全体に健康意識や改善の取り組みへの積極的な関与を動機付けしていくことなどが方策として考えられます。
以下の記事では、医療機関に課せられた安全配慮義務のひとつであるラインケアをいかに実践していくべきか、詳しく解説していますので併せてご参考ください。

職場の取組②:管理職自身のメンタルヘルスケア研修実施
メンタルヘルス研修は一般的に行われている研修のひとつですが、管理職自身のメンタルヘルスケアをテーマにした研修はあまり見かけません。
そのため、管理職自身のためのメンタルヘルス研修を、一般のメンタルヘルス研修に組み入れて実施していくことが重要だと考えます。
研修のなかで、同じ悩みを抱えた管理職同士でグループワークを行い、それぞれの情報共有を行うことで、これまでの一般的な研修では得られなかった気づきや学びが得られる可能性があります。
職場の取組③:健康支援体制の充実や外部EAPの導入
院内に職員の健康支援体制が整備されていれば、体制を充実させるとともに定期的なアナウンスで利用促進を図っていくことが大事です。
もし同様の機能が院内になければ、外部EAPの導入を検討します。外部EAPのメリットは、職場に自身の悩みを知られずにカウンセリングなどの利用ができることにあります。
いずれも、管理職を含めた職員全体の心の健康の維持・増進を図り、長期的なキャリア形成に寄与する取組となるでしょう。
医療機関における外部EAPの導入施策について、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。

職場の取組④:コミュニケーションの促進
後にも先にもコミュニケーションが大事になります。風通しの悪い職場は、職位を問わず職員の健康にも悪い影響を与えると言ってもいいでしょう。
忘年会や慰安旅行など医療機関主導のイベントや、部署内での親睦を深める取り組みでもいいと思います。職員同士の交流を促すことで、信頼関係が構築されていきます。
そうすれば、組織全体で権限移譲や業務移管なども進めやすくなり、全体の業務レベルが向上するとともに管理職の業務負担も軽減されます。
上記の取り組みは、職員個人に心理的安全性をもたらし、組織全体の生産性向上にも寄与します。医療機関における心理的安全性の高め方について、以下の記事で解説していますので、併せてご参考ください。
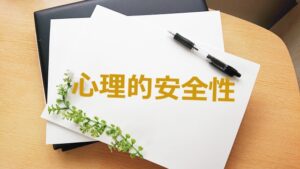
まとめ
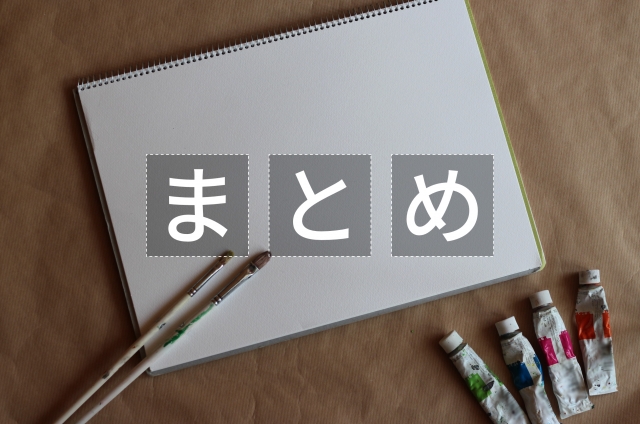
今回は、医療機関における管理職自身のメンタルヘルスケアについて考えてきました。
最後に、管理職自身のストレス対処法と職場の取組をまとめたいと思います。
| 管理職自身のストレス対処法 | 職場の取組 |
| 部下に頼る セルフケアを実践する 健康相談支援を受ける キャリアコンサルタントに相談する 他の管理職に相談する | 心身の健康を意識した経営 管理職自身のメンタルヘルスケア研修実施 健康支援体制の充実や外部EAPの導入 コミュニケーションの促進 |
多くの医療機関の使命は地域医療を守ることにあります。その医療機関で働く職員が心身ともに健康でなければ、地域の患者の命や健康を守ることは難しいでしょう。
地域医療を守るためには、まず医療機関のトップ層や管理職層が、自身の健康に気を配って活き活きと業務に励み、穏やかに職員と接することが重要です。
それができて始めて、医療機関全体が安心して地域の患者へ医療サービスを提供することができるようになり、また、地域の患者は安心してその医療機関から医療サービスを受けることができるようになるのではないでしょうか。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。







