現在、6割以上の看護師が今の仕事に「強い不満・悩み・ストレス」を抱えていると言われています。
医療機関におけるメンタルヘルス対策は、もはや努力目標とは言えなくなりました。
安全配慮義務の観点から、組織としてどのような体制を整えているかが問われる時代になっています。
特に、メンタルヘルス領域では、内部対応だけで十分とは言い切れないケースもあります。
その中で、「EAP(従業員支援プログラム)」というサービスの利用が徐々に浸透してきました。
内部対応のみで完結している体制と、外部専門機関と連携している体制とでは、リスク管理の厚みが大きく異なります。
人材不足の医療機関において、EAPは、その体制を補強する外部資源の一つと言えます。
本記事では、医療機関が安全配慮義務を踏まえた体制整備を行ううえで、EAPをどのように位置づけ、選択すべきかを整理します。
EAPとは?その基本概念と機能
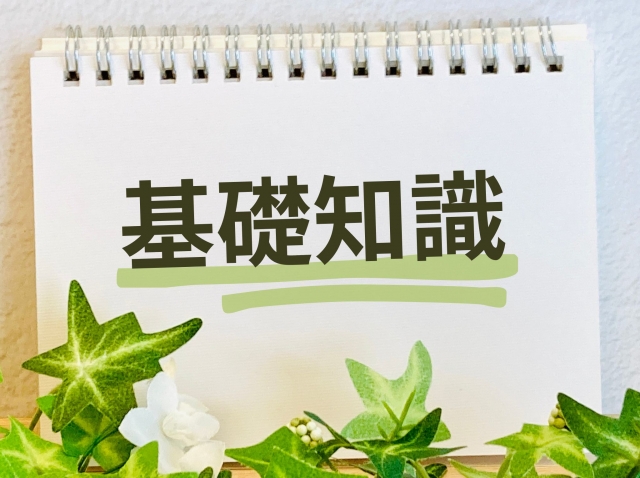
そもそもEAPとはどのようなサービスなのでしょうか。
始めに、EAPの基礎知識を確認していきます。
EAPとは、従業員支援プログラムのこと
EAP(Employee Assistance Program)とは、メンタルヘルス不調の従業員を支援するプログラムのことを言います。
そもそもEAPは、1960年代のアメリカでアルコールや薬物依存が深刻化した際に、業務に支障をきたす従業員の対応をするためのシステムとして発展したと言われています。
内部EAPと外部EAP
EAPには、「内部EAP」と「外部EAP」があります。
内部EAPとは
内部EAPは、事業所内に健康管理室を設置し、産業保健スタッフを配置して従業員の相談に応じることや、メンタルヘルス対策の推進を行います。
内部に設置するメリットは、主に2点あります。
- 相談員が事業所内部の事情を理解していること
- スムーズな対応が期待できること
外部EAPとは
外部EAPは、EAPサービス機関との外部委託によって、事業所内の従業員へのメンタルヘルスケアを行います。
外部に委託するメリットも、主に2点あります。(詳細後述)
- 事業所内に知られずに相談できること
- 相対的に低コストで相談対応の仕組みがつくれること
外部EAPは4つのケアの中の「事業場外資源によるケア」
厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示す4つのケアのひとつに、「事業場外資源によるケア」があります。
外部EAPはここに含まれます。
4つのケアを表にまとめます。
| ①セルフケア | 労働者が、自身のストレスのことを知り、予防や対処を行い、健康の保持増進に努めること |
| ②ラインによるケア | 職場の管理職が、職場環境の改善や従業員のメンタル不全に気づき、相談を行い、産業医との連携を図ること |
| ③事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 職場の産業医などの健康管理室が、随時の相談や職場復帰の判定を行うこと |
| ④事業場外資源によるケア | 職場外の専門機関から、メンタルヘルスの支援を受けること |
4つのケアの「①セルフケア」については、医療機関におけるストレスマネジメントの重要性とセルフケアの実践方法について解説した以下の記事が参考になります。
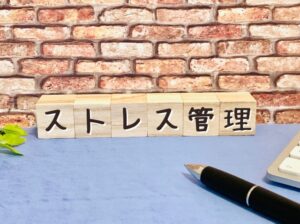
また、「②ラインによるケア」については、以下の「医療機関におけるラインケアの実践方法」の記事で詳しく解説しています。

なぜ医療機関に外部EAPが必要なのか

高ストレス職場で課される安全配慮義務
医療従事者は、業務の特性上、慢性的に高ストレス環境に置かれています。
人命を扱う緊張感、不規則勤務、患者・家族対応などを含めた対人関係の摩擦…
精神的負荷が重層的に存在しています。
こうした環境において、医療機関には労働契約法・労働安全衛生法上の安全配慮義務が課されています。
つまり、職員の心身の健康を損なわないよう、組織として必要な配慮を行う法的責任があるということです。
後手に回る医療現場での実務対応
しかし、医療現場の実務を考えると、次のような限界が生じやすいのが現実です。
- 管理職がメンタル不調の兆候に気づけない
- 相談窓口があっても「同じ組織内では相談しづらい」
- 産業医との接点が限定的で、日常的フォローが弱い
- 不調が顕在化した段階で初めて対応が始まる
内部体制のみで完結しようとすると、どうしても対応が後手に回る構造になりやすいのです。
求められる外部資源の活用
ここで重要になるのが、EAP(従業員支援プログラム)という外部資源の活用です。
EAPは、職員が匿名で専門家に相談できる外部窓口を確保する仕組みです。
第三者機関が介在することで、
- 早期相談の心理的ハードルが下がる
- 重症化前の段階で専門的助言が得られる
- 管理職の対応負担を軽減できる
- 組織として「相談体制を整備している」ことを客観的に示せる
といった効果が期待できます。
特に医療機関では、「患者のために我慢する」という文化が根強く、職員自身の不調が後回しにされやすい傾向があります。
だからこそ、内部だけに依存しない相談ルートを持つことは、体制整備の観点からも重要だと考えます。
外部EAPは安全配慮義務を果たすリスク管理手段
EAPは単なる福利厚生のひとつに留まりません。
安全配慮義務を実効性あるかたちで履行するための「外部連携型リスク管理手段」と位置づけるべきものです。
内部のラインケアやストレスマネジメント施策と組み合わせることで、はじめて多層的なメンタルヘルス体制が構築されます。
外部EAPの活用はメンタルヘルス対策の一つですが、導入するだけでは安全配慮義務を果たしたとは言えません。
この点は、総論記事「医療機関における安全配慮義務違反のリスクと体制整備の実務対応」の中で、安全配慮義務の全体像と外部資源活用を含めた実践的な対応について解説しています。
内部のメンタルヘルスケアだけでは不十分な理由

メンタルヘルス対策の中核は内部ケア
ラインケアや事業場内スタッフによるケアは、医療機関におけるメンタルヘルス対策の中核とも言えます。
管理職が部下の変化に気づき、声をかけ、必要に応じて専門職につなぐ
この仕組みが機能すれば、多くの不調は早期に対応できるでしょう。
しかし実際の職場では、内部のケアだけで十分とは言い切れないケースも少なくありません。
内部ケアだけでは不十分な3つの理由
理由は以下3つあります。
- 理由①:管理職はメンタルヘルスの専門家ではない
-
不調の兆候を察知できても、どこまで踏み込むべきか、どのタイミングで専門家につなぐべきか判断に迷う場合がある。
- 理由②:「同じ組織内での相談」には心理的な壁がある
-
評価や人事への影響を懸念し、本音を話せない職員もいる。
特に医療機関では責任感が強く、「迷惑をかけたくない」という思いから不調を抱え込む傾向が見られる。 - 理由③:管理職自身が疲弊している
-
人員不足や業務過多の中で、部下のケアまで担うことが重荷となり、結果として形だけの面談に終わることもある。
内部と外部の役割分担が重要
前述のとおり、内部ケアは重要である一方で、
- 専門性の限界
- 組織内相談の心理的制約
- 管理職の負担増大
という構造的な問題点を抱えています。
特に人材不足を抱える医療機関においては、自院に産業保健スタッフを置くこと自体が困難になります。
この場合、内部体制と併せて外部資源も活用し、それらの役割分担を意識することが重要です。
| 内部対応 | ラインによるケア・産業保健スタッフ | 気づき・初期対応 |
| 外部対応 | 事業場外専門機関・専門家・EAP | 専門的支援・匿名相談 |
この二層構造ができれば、メンタルヘルス対策はより実効性を持つでしょう。
内部対応のみで完結している状態より、外部対応としての相談ルートを確保している体制の方が、組織として安全配慮義務を具体的に示しやすくなります。
医療機関に適した外部EAPの選び方

外部EAPは提供会社ごとにサービス内容が大きく異なります。
形式上の導入では、実効性ある体制整備はできません。
医療機関としては、次の観点から検討することが重要です。
①医療業界への理解・実績があるか
医療機関には特有の業務特性があります。
- 夜勤体制
- 急変対応
- 対人ストレス
- 専門職間の力関係など
これらを理解していない相談窓口では、実態に即した助言が難しい場合があります。
医療業界での支援実績や、医療職対応経験の有無は重要な判断材料です。
②匿名性とアクセスのしやすさ
職員が「本当に匿名で相談できる」と感じられる仕組みかどうかは、利用率に直結します。
- 電話だけでなくオンライン相談に対応しているか
- 勤務時間外や夜間の利用が可能か
- 個人情報の取り扱いが明確に説明されているか
医療現場の勤務形態に合わせた柔軟性が求められます。
③組織へのフィードバック体制
個別相談内容には守秘義務がかかりますが、利用傾向や課題の傾向を統計的にフィードバックしてもらえる仕組みがあるかどうかは、体制整備の観点で重要です。
- ストレス要因の傾向
- 利用率
- 管理職向け助言内容など
これらを把握できれば、組織改善につなげることが可能になります。
④産業医・内部体制との連携可能性
外部EAPが単独で機能するのではなく、
- 産業医
- 衛生委員会
- 人事・労務担当
- 管理職ライン
との連携が可能かどうかも検討ポイントです。
内部体制とつながりを持たない外部資源、ではなく、「多層的な支援構造の一部」として組み込めるかどうかが重要です。
⑤契約形態と費用構造の透明性
費用対効果を判断するには、サービス範囲を具体的に確認する必要があります。
- 人数連動型か定額型か
- 利用回数制限はあるか
- 管理職研修等が含まれるか
実効性の確保には利用促進の努力も必要
EAPの導入は、単なる福利厚生の追加として考えるのではなく、安全配慮義務を実効性ある形で履行するための外部資源選定という位置づけで検討することが重要です。
「導入している」こと自体ではなく、医療機関の体制整備にどう組み込まれているか
この視点を持つことが、実効性を左右します。
実効性の確保には、利用率の随時確認や定期的な効果測定をとおして、職員に対する利用促進の努力を続けることが大事になります。
制度の導入目的を必ず明確にして、導入後も管理者層がその目的に立ち返り、目的達成に向けた施策を講じ続けることが重要です。
制度の導入目的(例)
- 職員の健康維持・増進
- 働きやすい職場づくり
- 離職率低下を目指す
参考:Q6:EAPプログラムの費用対効果について:専門家が事例と共に回答~職場のメンタルヘルス対策Q&A~|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)
外部EAP導入で期待できる組織的効果
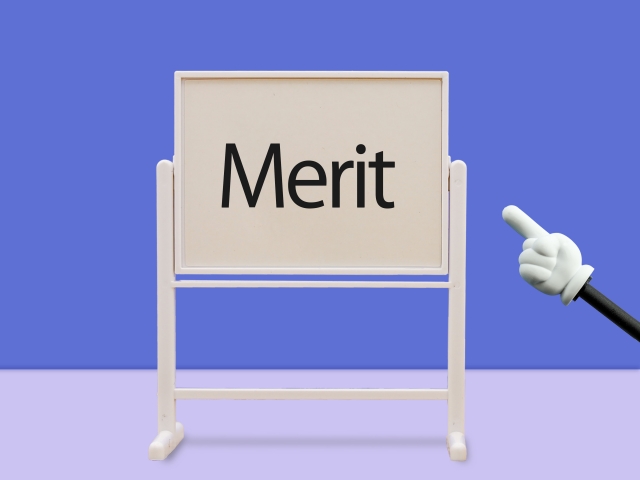
外部EAPは万能ではありません。
しかし、内部体制だけでは補いきれない部分を補完することで、医療機関のメンタルヘルス対策をより実効性の高いものに引き上げます。
外部EAPを適切に導入し、内部体制と連動させることで、次のような組織的効果が期待できます。
①早期相談の促進と重症化予防
匿名で専門家に相談できる窓口があることで、不調が深刻化する前段階での支援につながりやすくなります。
休職や長期離脱に至る前に介入できれば、本人の回復可能性を高めるだけでなく、組織全体の業務負担の増加を防ぐことにもつながります。
24時間365日対応しているサービス事業者も多く、困ったときにすぐ相談に応じてもらえるメリットもあります。
②管理職の心理的・実務的負担の軽減
ラインケアを担う管理職にとって、「専門家に相談できる先がある」という安心感につながります。
すべてを自分で抱え込むのではなく、
- 判断に迷うケースの相談
- 対応方針の助言
- 面談後のフォロー支援
といった外部サポートがあることで、管理職の疲弊を防ぐことができます。
結果として、組織全体のマネジメント力の安定にも寄与します。
医療機関における管理職のストレスケアの重要性について、以下の記事で詳しく解説しています。

③離職防止と職場定着率の向上
医療現場では、
「辞めるほどではないが、限界に近い…」
という状態が長く続くことがあります。
こうした段階で相談機会を持てることは、離職の抑制に一定の効果が期待されます。
特に若手職員や中堅層にとって、第三者に話せる環境があることは心理的安全性の向上にもつながります。
以下の記事では、増加傾向にある医療従事者の精神障害の現状と組織として取るべき対策について解説しています。

④他院との差別化
健康推進の取組や制度の充実が他院との差別化となり、人材確保の強化が図りやすいメリットもあります。
職員は、自己負担を気にせずサービスを受けることができるため、経済面においても利用のハードルが下がり、早期の健康問題解決が期待できます。
⑤安全配慮義務履行の客観的基盤
メンタルヘルス不調をめぐる労務問題が生じた場合、組織としてどのような体制を整えていたかが問われます。
- 相談窓口の設置
- 外部専門家との連携
- 利用実績の把握
- 管理職研修への反映
これらが整備されていれば、組織体制を問われた場合でも、安全配慮義務の履行を客観的に示しやすくなります。
つまり、外部EAPは予防的効果だけでなく、体制整備の証拠性を補強する要素にもなり得ます。
サービスのひとつとして、ハラスメント対策のサービスを提供している事業者もあります。
人間関係の複雑化で総務部門の負担が増えるなか、外部EAPの活用は職場のコンプライアンス向上と法的リスク回避の期待にもつながります。
外部EAP導入の注意点

外部EAP導入には期待効果がある反面、以下のような注意点もあります。
①コストの増加
まず、事業者との契約費用や運用コストがかかります。
中小規模の医療機関にとっては、既存の経費の追加コストになるため、経営上の負担が大きくなる可能性があります。
職員の利用率が低い場合、費用対効果が得られにくいことも留意点です。
②職員の利用率低迷
せっかく外部EAPを導入しても、職員がその存在を知り価値を理解しなければ利用につながらず、導入効果が発揮されません。
導入内容の周知や積極的な利用を促すために、継続的なアナウンスなどの施策が必要です。担当委員会や総務部門において追加的な労力がかかることも想定しておく必要があります。
③健康情報の漏洩リスク
外部EAPの導入には、職員の健康情報や相談内容の漏洩リスクがつきまといます。
個人情報の取扱いを誤ると職員の不信感を招き、EAPの利用を敬遠され、そもそもの導入目的を達成することができません。
また、個人情報の漏洩は、膨大な要配慮個人情報を扱う医療機関にとって社会的な信用を失うきっかけにもなります。
外部EAPを導入する際は、より慎重に、より適切な情報管理が求められます。
④外部依存による職員サービス低下
事業者が提供するサービスの質や対応スピードが自院の期待と合わないことがあります。
自院に適したカスタマイズが難しい場合、導入目的を完全に満たすだけのサービスが受けられない可能性があります。
⑤既存の院内制度との重複
メンタルヘルス対策を担当する部署や制度がすでにある場合、機能の重複により効果的な運用が難しくなることが考えられます。
外部EAP導入前には、院内での運用ルールの見直しや利用の切り分けが必要になります。
EAPのサポート内容とは

ここで、EAPのサポート内容にはどのようなものがあるのか確認していきます。
EAPの主なサポート内容
サービス提供機関ごとに異なりますが、一般的には以下のサービスが提供されます。
導入時には、自院の目的とコストとの見合いで契約内容を検討する必要があります。
- カウンセリング(対面、オンライン、電話等)
- ストレスチェック
- 各種研修実施(メンタルヘルス、マネジメント等)
- ハラスメント対策
- 産業医連携
- 各種支援サービス(定着、職場復帰支援等)
EAP提供機関のサービス比較
人材開発・育成、組織開発に関する情報サイト「日本の人事部」から一部抜粋し、サービス内容の比較表を作成しました。
| ㈱パソナセーフティネット | ㈱エムステージ | ダイヤル・サービス㈱ | |
| 内容 | 「なんでも相談窓口」 24時間相談可能 相談方法は電話、メール、面談 面談カウンセリングは全国対応可能 相談内容はメンタルヘルス・健康、職場、家庭、プライベートなどに加え、人事労務部門からメンタルヘルス不調者に関する相談も可能 海外駐在員、帯同家族や日本に住む外国籍社員の相談も可能 | ①電話健康相談(ファミリー健康相談) ②メンタルヘルスカウンセリング ③ハラスメント外部相談窓口 ④ベストドクターズ・サービス | トータルEAPサービス「こころと暮らしのほっとライン」 電話カウンセリングメールカウンセリング 対面カウンセリング ストレスチェック メンターサービス 訪問カウンセリング 社労士・弁護士相談 産業医紹介 |
| 企業規模 | 全て対象 | 全て対象 | 全て対象 |
| 費用 | 800円~/人(年)(規模により異なる) | ①年55万円~②年30万円~③年26万4千円~④年30万円~※全て税別 | スタンダードプランは月額3万円から導入可 |
※人材開発・育成、組織開発のナレッジコミュニティ「日本の人事部」
メンタルヘルス対策・EAPのサービス一覧より抜粋
外部EAPの導入プロセス

最後に、外部EAPを導入する際の手順を解説します。
具体的には、以下の6ステップを踏んで導入・運用していくことが望まれます。
- 外部EAP導入議論や目的の明確化
- サービスの範囲や運用方法決定
- 管理職への啓発
- 職員への周知
- 利用状況の確認と効果測定
- 継続的アナウンスによる利用率向上の努力
順番に説明していきます。
管理者会議等でEAP導入の是非を議論のうえ導入を決定します。その際には導入目的を明確にしたうえで、関係委員会(安全衛生委員会等)へ運用方法の策定等を委任します。
安全衛生委員会等にて、委託サービスの範囲や運用方法を議論のうえ決定します。
幹部会議にて、管理職に対しEAPの内容や活用方法に関する啓発を行います。
院内報や定例会議をとおして、職員へ外部EAP導入の周知を行います。
利用状況を随時確認し、定期的に導入前後での数値を比較することにより効果測定を行います。
【効果測定の項目例】サービス利用率、メンタル不調による休職者数、休職率等
利用率向上を図るため、継続的に職員に利用のアナウンスを行います。院内メールや供覧、休憩室への掲示など複数の手段で行うことが理想です。
まとめ
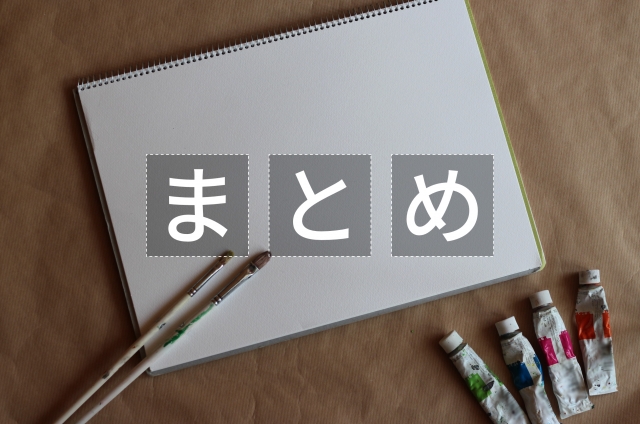
今回は、安全配慮義務を踏まえた体制整備に向け、外部EAPの位置づけや選択のポイント、導入効果などについて解説しました。
医療現場は、長時間労働や交代制勤務、関係スタッフや患者との人間関係の摩擦、職業上の責任感やプレッシャーにより日常からストレスを抱えやすい職場です。
組織的かつ計画的にメンタルヘルスケアを推進していくことは、いま医療機関に強く求められている安全配慮義務のひとつです。
外部EAPは、医療機関が安全配慮義務を実効性ある形で履行するための貴重な外部資源と言えます。
組織としての体制整備を見直す際は、安全配慮義務の総論を解説した以下の「医療機関における安全配慮義務違反のリスクと体制整備の実務」もあわせてご確認ください。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。








