「人生100年時代」と言われるなか、生涯現役という生き方を目指す人も多くなりました。
常に人手不足を抱える医療業界において、高齢者雇用は今後の人材確保策の重要課題になります。
しかし、どのような対策を立てればいいのか、お悩みの医療機関も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、人手不足の現状や医療機関が認識すべき高齢者雇用のメリットについて解説し、シニア世代を活用した労働力強化の具体的な実践方法を提案します。
人手不足解消の鍵?高齢者雇用の可能性と労働力としての強み

2021年4月に施行された高齢者雇用安定法改正により、事業者は労働者に対して70歳まで就業機会を確保することが努力義務化されました。
これを受けて一部の民間企業では、定年年齢の引き上げや定年制度自体を廃止するなどの動きが活発化しているようです。
ここでは、医療業界における人手不足の現状と、高齢者雇用の可能性について解説したいと思います。
人手不足の現状
医療業界における人手不足は深刻です。医師については、近年、地域や診療科による偏在が問題視され、すでに定年年齢を引き上げている医療機関も少なくないと思います。
看護師については年間約3万人ずつ就業者が増えているという調査もあります。しかし、それでも疾病構造や人口動態の変化によって、2025年には人員不足に陥るというデータが出ています。
以下、医療業界における人手不足の現状について確認していきたいと思います。
看護職における需給ギャップの懸念
2017年7月の社会保障審議会医療部会では、看護職員が「2025年に約200万人」必要であると試算しました。
そして、看護師の就業者数は年間3万人ペースで増えているものの、「2025年で約3万人~約13万人分の需給ギャップが生じる見込み」と報告しています。
医療機関の職員の半数を看護師が占めます。多くの医療機関では、2025年を待たずに、すでに看護師不足に陥っていることが想像できます。
<現状及び課題>
- 看護職員の就業者数は、近年3万人/年ペースで増加している。
- 社会保障・税一体改革の試算による看護職員の必要数は「2025年に約200万人」。
- 就業者数が3万人/年で増加しても2025年で約3万人~約13万人分の需給ギャップが生じる見込み。
引用:医療業 高齢者雇用推進ガイドライン(令和2年)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
看護職における50歳以上率の高まり
看護職員の高年齢化も、医療機関が認識しておくべきことのひとつとして挙げられます。
社団法人全日本病院協会医療業高齢者雇用推進委員会がまとめた「高齢医療従事者の雇用・働き方ハンドブック」では、看護職員の50歳以上率について報告されていますので、ここで紹介したいと思います。
| 看護職 | 看護補助職 | |
| 急性期 | 14.9% | 48.5% |
| ケアミックス | 21.1% | 36.3% |
| 慢性期 | 49.0% | 40.4% |
「高齢医療従事者の雇用・働き方ハンドブック」より引用
資料をみると、医療機関の特性によって特徴が異なることがわかります。
急性期病院については、看護職の50歳以上率は14.9%と低い割合を示していますが、看護補助職については48.5%で全体の5割近くを占めます。
一方で、慢性期病院については、看護職の50歳以上率は49.0%と全体の5割弱を、また看護補助職は40.4%で全体の4割強を占めるなど、いずれも高い割合を示しています。
相対的にみると、慢性期病院の方が職員の高年齢化が進んでいることがわかります。
人手不足が医療機関に与える影響
人手不足は、医療機関に以下の4つの影響を及ぼす可能性があります。
影響①:医療サービスの質の低下
人手不足に陥ると、職員一人当たりの仕事量が増えます。職員個々の業務過多が続くと、医療安全の確保が難しくなり、医療ミスやインシデントの発生の可能性が高まります。
影響②:離職者の増加
人手不足により職員一人当たりの仕事量が増えると、長時間労働や過重労働による身体的な不調やメンタルヘルス不調の原因となり、離職者が増える可能性が高まります。離職者が出始めると、さらなる離職が増える悪循環を招く恐れもあります。
以下の記事では、過重労働等による医療従事者の精神障害について解説しています。併せてご参考ください。
影響③:減収による経営の不安定化
離職者が増えると、それまで確保できていた施設基準が満たせずに、大幅な収入減を招きかねません。収入の減少は医療機関の経営を不安定にし、事業の継続に大きな足かせとなる可能性があります。
影響④:地域医療の後退
医療機関の人手不足は、地域医療に少なからずマイナスの影響を及ぼします。医療人材が不足することにより診療時間の短縮や診療科の縮小、救急患者への非対応などの可能性が高まり、地域医療の後退につながりかねません。
高齢者雇用の可能性
今後も少子化は進行することが予想されます。現役世代が減少すれば、医療の担い手も減少することは明らかです。
医療業界においては、潜在的な人材の掘り起こしが必要とされています。そのなかで課題となるのは、女性やシニア世代を労働力としていかに確保していくかにあります。
ここでは高齢者雇用の可能性について、資料を参考に探っていきたいと思います。
平均寿命と健康寿命の延伸
近年、日本人の平均寿命が延伸していることはご存知かと思います。そして、平均寿命とともに健康寿命についても年々延伸する傾向にあります。
「令和7年版高齢社会白書(概要版)」を基に、健康寿命と平均寿命の推移について表にまとめると、以下のとおりとなります。
| A平均寿命 (男性) | B健康寿命 (男性) | A-B (男性) | A平均寿命 (女性) | B健康寿命 (女性) | A-B (女性) | |
| 2001年 | 78.07 | 69.40 | 8.67 | 84.93 | 72.65 | 12.28 |
| 2004年 | 78.64 | 69.47 | 9.17 | 85.59 | 72.69 | 12.90 |
| 2007年 | 79.19 | 70.33 | 8.86 | 85.99 | 73.36 | 12.63 |
| 2010年 | 79.55 | 70.42 | 9.13 | 86.30 | 73.62 | 12.68 |
| 2013年 | 80.21 | 71.19 | 9.02 | 86.61 | 74.21 | 12.40 |
| 2016年 | 80.98 | 72.14 | 8.84 | 87.14 | 74.79 | 12.35 |
| 2019年 | 81.41 | 72.68 | 8.73 | 87.45 | 75.38 | 12.07 |
| 2022年 | 81.05 | 72.57 | 8.48 | 87.09 | 75.45 | 11.64 |
資料のとおり、2022年の健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳となっています。
男性も女性も70歳過ぎまでは健康に生活できることを示しており、シニア世代の労働力としての可能性を示唆しています。
健康寿命と地域の医療機関の関係について、以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。
年齢階級別就業率の推移
ここでは、シニア世代の就業率について確認したいと思います。
総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)平均結果」によると、10年前と比較してシニア世代の就業率が各年代とも上昇していることがわかります。
| 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75歳以上 | |
| 2014年 | 60.7% | 40.1% | 24.0% | 8.1% |
| 2024年 | 74.3% | 53.6% | 35.1% | 12.0% |
シニア世代が考える就業終了希望年齢
次に、シニア世代の就業意欲について確認したいと思います。
パーソル総合研究所が行った「働く10000人の成長実態調査2023」の回答結果をご覧ください。
Q.あなたは人生で何歳まで働きたいと思いますか。希望する年齢をお知らせください。
| 年齢区分 | 71歳以上と回答 | 就業終了希望年齢平均 |
| 55~59歳就業者 | 15.4% | 68.1歳 |
| 60~64歳就業者 | 17.2% | 69.8歳 |
| 65~69歳就業者 | 40.7% | 73.5歳 |
パーソル総合研究所の調査「働く10000人の成長実態調査2023」を基に筆者作成
この調査によると、シニア世代の多くが70歳前後まで働きたいと示しており、71歳以上と回答したのは各年齢区分とも15%以上回答しています。
また、年齢区分が上がるにつれて就業終了希望年齢が上がっており、なんと65~69歳の就業者のうち4割以上の人が、70歳を超えるまで働き続けたいと回答しています。
参考:~働く10,000人成長実態調査2023~シニア就業者の意識・行動の変化と活躍促進のヒント- パーソル総合研究所 (persol-group.co.jp)
就業終了希望年齢まで働き続けたい理由
それでは、なぜシニア世代はそこまで長く働き続けたいと考えているのでしょうか。
以下の資料からわかるとおり、働き続ける理由として、収入や年金不安が上位にくる一方で、自身の健康維持ややりがい、社会貢献のためという意見が多いことが確認できます。
| 順位 | 71歳以上まで働き続けたい理由 | 回答割合 |
| 1位 | 働くことで健康を維持したいから | 57.8% |
| 2位 | 生活を維持するために収入が必要だから | 47.6% |
| 3位 | 働かないと時間をもてあましてしまうから | 39.9% |
| 4位 | 将来の年金生活が不安だから | 39.7% |
| 5位 | 仕事をとおしてやりがいを得たいから | 35.8% |
| 6位 | 働くことで社会に貢献したいから | 26.6% |
| 7位 | 趣味などに充てる資金を得たいから | 25.2% |
| 8位 | 体力的に限界の年齢だと思うから | 24.9% |
| 9位 | 仕事を通じて友人や仲間を得ることができるから | 24.3% |
| 10位 | 仕事を通じて成長していきたいから | 21.4% |
パーソル総合研究所の調査「働く10000人の成長実態調査2023」を基に筆者作成
高齢者にみる労働力としての強み
前項では、シニア世代の就業意欲の高さについて確認しました。
ここでは、シニア世代が医療機関の労働力としてどのような強みを持っているのか確認したいと思います。
強み➊:安定した業務遂行能力
医療機関においては専門性の高い人材が求められます。シニア世代は長年の経験に基づく専門知識の多さや医療技術の高さから、安定して業務遂行能力を発揮できることが強みだと言えます。
強み➋:患者に与える安心感
シニア世代は若い世代に比べ、社会経験や業務経験が豊富にあります。患者の高齢化も進んでいるなか、患者と年齢が近い立場にあるシニア世代の医療スタッフは、患者やその家族の立場に立って振る舞うことができます。
そうした振る舞いは、患者に対するの安心感や信頼感につながり、医療機関の患者満足度向上に貢献できる強みとなります。
高齢者の力を活かす!医療機関が得られる3つのメリット

これまで医療業界の人手不足や高齢者雇用の可能性についてみてきました。
ここでは、医療機関における高齢者雇用のメリットについて考えたいと思います。高齢者雇用のメリットとして、主に以下の3点が挙げられます。
- 労働力不足の解消
- 若手育成の強化
- 多様な人材活用による組織活性化
このメリット3点について、詳しく解説したいと思います。
メリット➊:労働力不足の解消策としての高齢者雇用
今後も進行していく医療業界の人手不足や高齢者雇用の可能性の大きさを考えると、シニア世代の雇用推進は、医療機関にとって必要不可欠な施策となります。
現状は定年を60歳に定めている医療機関は7割以上あり、ほとんどの医療機関が継続雇用を導入していますが、65歳を在職の区切りにしています。
法令上、今後は70歳までの就業機会の確保が求められています。シニア世代の雇用推進は、人手不足の解消とともに労働力の安定的な確保につながります。
メリット➋:経験と知識の継承による若手育成の強化
シニア世代の雇用推進は、ベテランとして蓄積された業務経験やスキルを、若い世代に継承し育成強化を図ることができるメリットがあります。
ベテラン職員の豊富な経験やスキルは暗黙知であり、医療機関にとって非常に価値の高い無形資産と言えます。この暗黙知を形式知化して、いかに若い世代に継承していくかが重要となります。
すでに高齢者雇用を実践している医療機関では、経営課題として管理職中心にベテラン職員の経験を集積したマニュアル作りを進めているようです。
ベテラン職員の知見が詰まったマニュアルでの業務継承は、業務の標準化とともに業務レベルの高度化を図ることができます。
これにより若手育成の強化が進めば、医療現場の生産性向上による業務負担の軽減や、医療の質向上による患者満足度向上にもつながります。
メリット➌:多様な人材活用による組織活性化
高齢者雇用はダイバーシティ経営にもつながると言えます。ダイバーシティとは「多様性」のことを表します。
経済産業省は、ダイバーシティ経営を以下のとおり定義しています。
「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」
引用:ダイバーシティ経営の推進 (METI/経済産業省)
同じ組織内に、同じような年代や考え方の人材が集まっても、なかなか新しい発想は生まれません。ひとつの組織内に、若手や中堅、ベテランなど異なる視点を持った人材を構成することで組織は活性化されます。
活性化された組織では、個々のスタッフの個性が活きることで、創造的かつ革新的なアイデアが生まれやすくなります。そして、職場の生産性が向上し、医療機関の価値の継続的な向上につながります。
なお、人材の多様性を活かすには、個々のスタッフが活き活きと働くことができる職場環境づくりが必要になります。一例として、以下のような取り組みが有効であると考えられます。
- ワークライフバランスの改善
- 勤務時間や雇用形態など柔軟な働き方の普及
- 年功序列に偏った人事制度の見直し
- 多様な人材のコミュニケーション活性化に向けた管理職のマネジメント能力向上
高齢者雇用のデメリットや問題点を考える

前項では高齢者雇用のメリットに確認しましたが、反対にデメリットはあるのでしょうか。
高齢者雇用で想定されるデメリットや問題点として、以下の4点が挙げられそうです。
- 人件費の増加
- 若い世代のモチベーション低下
- 体力・体調面に関する不安
- 変化への対応力に関する不安
これらデメリット4点について、詳しく解説していきます。
デメリット➊:人件費の増加
年功賃金が導入されている医療機関にとっては、職員の高齢化は人件費の増加につながります。
シニア世代の雇用推進策として定年年齢の引き上げを行う場合は、年功序列に偏った賃金制度や評価制度を見直し、個々の能力に見合った賃金や評価設定を行うなど、人件費を抑制する施策をセットで行うことが重要となります。
なお、年功序列に関して医療機関がとるべき施策について、以下の記事で取り上げていますのでよろしければご参照ください。
デメリット➋:若い世代のモチベーション低下
年功序列制度を取り入れている医療機関にとっては、役職者の高齢化も問題になります。
役職者の高齢化は、次世代を担うべきミドル層や若手職員の昇進・昇格が停滞し、若い世代のモチベーション低下を招きます。
シニア世代の雇用維持を図り、事業を継続していくためには、年功序列に偏った人事制度の見直しが必要になります。
役職定年制度を導入するほか、個々の能力を正当に評価し、若い世代からも役職者に抜擢するといった公平性を担保した人事制度を導入することが重要です。
デメリット➌:体力・体調面に関する不安
年齢を重ねるごとに、体力の低下や身体的な疾患を抱えやすくなるのは仕方ないと言えます。若い頃と比べて、不規則なシフト勤務や夜勤が重なると体力的に厳しくなるのは当然です。
また、腰痛に悩む看護師が多いのも事実です。看護業務においては、中腰での患者対応が多いことから、シニア世代の雇用推進においては、補助具の整備など腰痛対策を含めた職場環境の配慮やケアの充実が重要となります。
デメリット❹:変化への対応力に関する不安
新しい制度や取り組み、システム導入に際しては、シニア世代が苦慮する場面が多くなります。
また、医療技術の進歩はめざましく、働いていくうえでは、専門知識や新しい技術のアップデートは必須事項となります。
シニア世代の雇用を推進し、長く勤めてもらうには、組織運営について丁寧に説明して協力を促すとともに、専門知識や新しい技術を学ぶ機会の提供を行う施策が重要になります。
高齢者雇用で医療機関の労働力を強化する方法

ここでは、高齢者雇用で医療機関の労働力を強化する具体的な方策として、以下の5点を挙げて説明したいと思います。
- 柔軟な勤務時間の設定
- 業務内容の適正化
- サポート体制の強化
- 研修制度の充実
- 労働意欲の喚起
方策➊:柔軟な勤務時間の設定
シニア世代の雇用を進めるうえで重要になるのは、柔軟な勤務制度の導入です。
実際に高齢者雇用を実践している医療機関の取組事例として、以下の施策を紹介します。
柔軟な勤務時間の設定(例)
- 夜勤回数の軽減
- 早朝勤務、深夜勤務の軽減
- 半日勤務の導入
- 隔日勤務の導入
方策➋:業務内容の適正化
シニア世代の雇用を進めるうえでは、業務内容の適正化が重要になります。
そのためには、シニア世代の声に耳を傾け、個々の適正に見合った業務配分や配置を行う必要があります。
ここでも実際の取組事例として、以下の施策を紹介します。
業務内容の適正化(例)
- 高齢職員の意見を反映させた業務改善制度の導入
- 高齢職員の体力、能力に応じた業務設定
- 業務改善アンケートで各職場の課題を抽出し改善活動実施
- 退職者アンケートで退職事由を抽出し職場風土や人間関係を改善
方策➌:サポート体制の強化
シニア世代の雇用を進めるうえでは、体力面に配慮したサポート体制の強化が重要となります。
シニア世代は体調や体力面で不安を抱えています。前述したとおり、腰痛を抱えながら業務に励むシニア世代の医療従事者も少なくないと思います。
補助具等の整備は病棟単位になることも多いと思いますが、シニア世代に限らず全職員の作業環境改善のため、病院全体での導入が重要です。
実際の取組事例として、以下の施策を紹介します。
サポート体制の強化(例)
- 介護支援用ロボットの導入
- 補助ベルトなど用具の整備
- 高齢職員が使いやすい給食運搬車への更新
- ナースステーションを病棟の中心に配置し動線短縮
方策❹:研修制度の充実
シニア世代が戦力として活躍するには、日々進化していく医療技術や知識のアップデートが欠かせません。
医療機関全体の研修参加と併せて、シニア世代に特化したフォロー制度を取り入れるなど、研修制度の充実が重要となります。
実際の取組事例として、以下の施策を紹介します。
研修制度の充実(例)
- 研修テキストやスライドの文字を拡大し、イラストを多用するなど見やすさを工夫
- 高齢職員向けの教育訓練、研修参加の機会を提供
- 院長主催の定期カンファレンスで治療や看護のあり方の共有を図りチーム医療の質向上
方策❺:労働意欲の喚起
年齢を重ねるうちに現状維持バイアスが働きやすくなる傾向にあります。
医療機関として、シニア世代の雇用を推進していくためには、モチベーション管理やコミュニケーション活性化を図り、ベテラン職員の労働意欲を喚起することが重要になります。
実際の取組事例として、以下の施策を紹介します。
労働意欲の喚起(例)
- 顧問制度による後継者育成
- トレーナー制度の導入
- 若手職員とのペア就労
- 毎年度末の研究事例発表会でベテラン看護師が若年職員とチームで発表
なお、医療機関におけるモチベーション管理やコミュニケーション能力向上の方策については、別の記事で詳しく解説しています。併せてご参照ください。
助成金を活用して高齢者雇用を充実させる

国は助成金を設定して、高齢者雇用の推進を後押ししています。
ここでは、高齢者雇用に関わる主な助成金について簡単に紹介します。申請方法などの詳細については、厚生労働省のホームページ等から確認するようにしてください。
高齢者雇用に関わる助成金には、大きく分けて以下の2つがあります。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 65歳超雇用推進助成金
以下、それぞれ概要を解説します。
➊特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金には、以前「生涯現役コース」というものもありましたが、2022年度末で廃止となり、こちらで紹介する特定就職困難者コースで申請することになっています。
- 助成金内容
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の職業紹介により、継続雇用労働者を雇い入れる事業主に対して支給される助成金 - 助成金額【高年齢者(60歳以上)】
60万円(大企業50万円)・短時間40万円(大企業30万円) - 対象者
正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※対象者が望む限り更新できる契約のみ)
➋65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金には、以下の3種類のコースが設定されています。個別に概要をまとめましたので、参考にしてください。
65歳超雇用推進助成金
- Ⅰ.65歳超継続雇用促進コース
- Ⅱ.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- Ⅲ.高齢者無期雇用転換コース
Ⅰ.65歳超継続雇用促進コース
Ⅰ.65歳超継続雇用促進コース
- 助成内容
下記のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
A.65歳以上への定年引上げ
B.定年の定めの廃止
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入 - 助成金額
対象者数・措置の内容・年齢の引上げ幅等に応じて以下の金額を支給
【A・B】
65歳 15万円~
66歳~69歳 20万円(5歳未満引上)・30万円(5歳以上引上)
70歳以上 30万円
定年廃止 40万円~
【C】
66歳~69歳 15万円~
70歳以上 30万円~
【D】
66歳~69歳 10万円上限
70歳以上 15万円上限
Ⅱ.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
Ⅱ.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 助成内容
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース(実施期間1年) - 対象となる措置
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等 - 助成金額
上記の支給対象経費の額に以下の助成率を乗じた額を支給
・中小企業 60%
・中小企業以外 45%
※初回は30万円支給(中小企業以外22.5万円)
2回目以降は支給対象経費a・b合計50万円を上限に助成率を乗じた額を支給
a.専門家・コンサルタント経費 b.機器ソフトウェア経費
Ⅲ.高齢者無期雇用転換コース
Ⅲ.高齢者無期雇用転換コース
- 助成内容
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース(実施期間:2年~3年) - 助成金額
対象労働者1人につき以下の金額を支給
・中小企業 30万円
・中小企業以外 23万円
※ 1支給申請年度1適用事業所あたり10人まで
医療機関における高齢者雇用の実際の成功事例
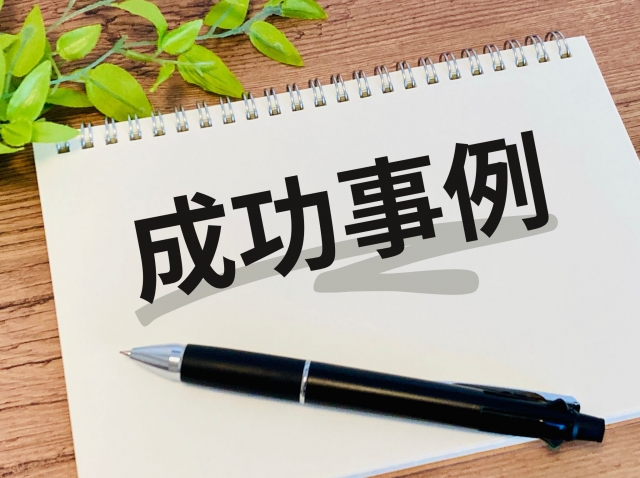
最後に、高齢者雇用を実践している医療機関から、実際にあった2つの成功事例を紹介したいと思います。
成功事例①:60歳定年制を改め65歳定年・70歳継続雇用制度を導入した事例
1つ目は、60歳の定年制から、65歳定年・70歳継続雇用制度を導入した医療法人社団の事例になります。
- 事例施設の概要
医療法人社団 五色会
【従業員数】554人
【平均年齢】60~64歳:8.6%, 65歳~69歳:2.9%, 70歳以上:1.1%
【60歳以上】12.6% - 取組のポイント
「高齢者の豊かな経験を活かし心に寄り添う医療・介護・福祉サービスを実現」
①定年年齢、雇用上限年齢を5歳引き上げ65歳定年、70歳までの継続雇用制度に
②定年・継続雇用制度改定に伴う人事管理制度の変更は行わず、モチベーションを維持
③改善提案制度を通して職場環境の改善と理事長と職員との意思疎通を円滑に - 高齢職員を活用するための工夫
①制度面の工夫:
短時間正職員制度の導入
②業務面の工夫:
機械設備の導入、高齢職員の意見を反映させた業務改善、高齢職員の体力・能力に応じた業務設定
③意識・風土面の工夫:
改善提案制度の導入と職場コミュニケーションの推進
④能力開発の工夫:
顧問制度による後継者育成、トレーナー制度の導入、若手職員とのペア就労
⑤健康対策:
永年勤続表彰の適用範囲の拡大
引用:医療法人社団 五色会 | 事例検索 | 高年齢者活躍企業事例サイト| 独立行政法人高齢·障害·求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
成功事例②:定年制を廃止した事例
2つ目は、定年制を廃止した医療機関の事例になります。
- 事例施設の概要
医療法人 信和会 高嶺病院
【従業員数】107人
【平均年齢】53.1歳
【60歳以上】42.0% - 取組のポイント
定年の廃止が看護師の人材難解消、看護技術向上にもつながる
①看護師の採用難から1992年に定年を廃止。
②その結果、高い看護技術と若手に対する指導力をもったベテラン看護師が多数応募してくるようになり、人材難の解消ばかりでなく、看護技術の底上げにも寄与。 - 高齢職員を活用するための工夫
①柔軟な勤務制度の導入:
本人の希望に応じて、隔日勤務、半日勤務など多様な勤務形態を認めている
②就業環境の改善:
ナースステーションを中心に病棟を配置することで動線を短縮、高齢者であっても働きやすい環境の整備
③人材育成の仕組み:
定期的に職員を集め、院長主催のカンファレンスを行い、治療や看護のあり方を確認、看護師ごとに異なった方法でアプローチすることもあったが、これによりチーム医療の質が向上 - 課題
①定年廃止により、人材難は解消しつつある。高齢のベテラン看護師の確保・活用に成果を上げてきたが、年齢構成のバランスに偏りがあるのも事実。
②治療において、ベテラン看護師と若手看護師が補完し合い、チーム医療をさらに活性化。
引用:医療法人 信和会 高嶺病院 | 事例検索 | 高年齢者活躍企業事例サイト| 独立行政法人高齢·障害·求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
まとめ
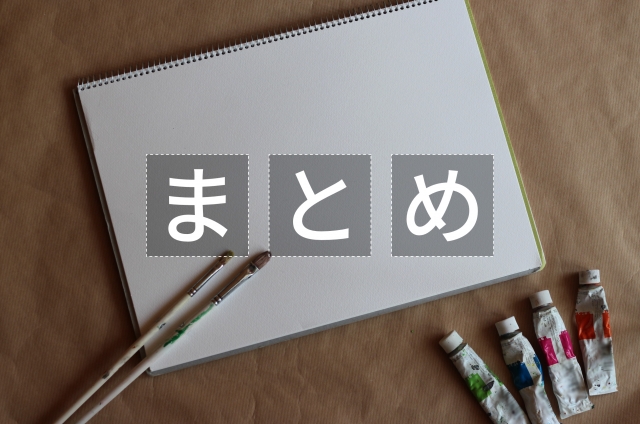
今回は、医療機関における高齢者雇用のメリットや労働力強化に向けた具体的な実践方法について解説しました。
最後に、高齢者雇用で医療機関の労働力を強化する具体的な方策5点をまとめます。
- 柔軟な勤務時間の設定
- 業務内容の適正化
- サポート体制の強化
- 研修制度の充実
- 労働意欲の喚起
この先も少子高齢化は進行し続けます。医療業界において、人手不足はさらに深刻化するでしょう。
そのなかで自院を存続させていくためには、経験豊富な質の高いシニア世代を戦力としていかに確保していくかが重要課題となるのです。
今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。








