退職代行サービスをご存知でしょうか?
ゴールデンウィーク明けに利用者が増えるとメディアでも大きく取り上げられることから、ご存知の方も多いかも知れません。
医療機関においても、退職代行サービス業者から突然電話がかかってくるケースも出てきています。
しかし、突然業者から電話がかかってきたら、どう対応していいのか判断に迷うこともあるのではないでしょうか。そこでもし対応を誤ると、場合によっては法的リスクを負う可能性も出てきます。
今回の記事では、医療機関が退職代行を使われた際の適切な対応と法的リスクの回避方法、さらには医療機関での職場環境改善に向けた提案を行いたいと思います。
退職代行サービスとは?
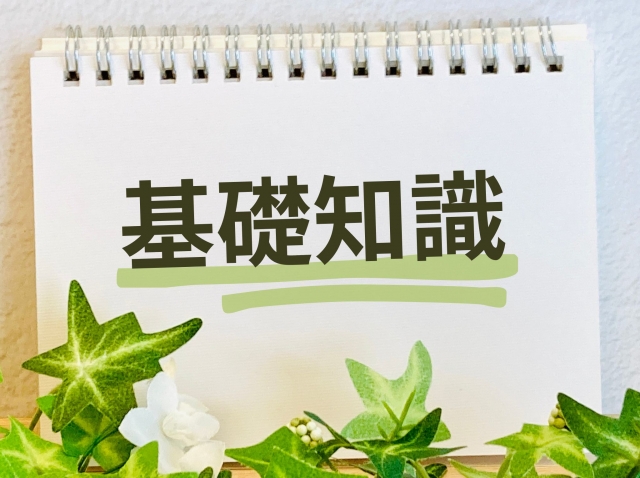
実際の対応方法を解説する前に、退職代行サービスとはどのようなものなのか、簡単にサービス内容と業者の特徴について解説したいと思います。
退職代行のサービス内容とは?
退職代行サービスには、主に以下の3つの項目があります。
- 依頼者の退職意思を事業者へ伝達
- 有給や未払い賃金などに関する事業所との交渉
- 事業所への訴訟対応
次に説明するサービス運営元の種類によって、行うことができる項目の範囲が異なります。
退職代行の3つの運営元とその特徴とは?
退職代行サービスには以下の表のとおり
- 民間業者系
- 労働組合系
- 弁護士系
という3種類の運営元があり、その種類によってサービスの可否が異なります。
資料のとおり、民間業者系は「➊退職意思伝達」までしかできませんが、弁護士系は「➊退職意思伝達」から「➋退職条件交渉」を経て「➌訴訟対応」まで行うことができます。
これは次に説明する弁護士法等による法律の制限があるためです。
| サービス内容 | 1.民間業者系 | 2.労働組合系 | 3.弁護士系 |
| ➊退職意思伝達 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ➋退職条件交渉 | × | 〇 | 〇 |
| ➌訴訟対応 | × | × | 〇 |
| 料金の相場 | 1~3万円 | 2~3万円 | 3~7万円 |
| 特徴 | ・退職の意思を伝えることしかできない | ・事業所との退職交渉までできる ・有給休暇や未払い賃金の請求が想定される | ・全て対応できる ・労働者からの訴えも想定される(ハラスメントや違法な長時間労働等) ・事業所からの訴えに備える場合もあり得る(労働者が原因の業務上の損害賠償請求等) |
退職代行を受ける前に知っておきたい法律の予備知識

次に、退職代行を受ける前に知っておくべき法律の知識について解説します。
退職代行における非弁行為とは?
退職代行業者の運営元によってサービスの範囲が異なる根拠は、弁護士法、憲法及び労働組合法が条文に示しています。
弁護士法によると、弁護士資格を持たない退職代行業者が、退職意思の伝達のほか、退職条件の交渉をすることは「非弁行為」に該当します。
非弁行為とは、弁護士以外の者が報酬を受け取って弁護士業務を行うことを言います。
しかし、労働組合系の業者については、労働組合法によって交渉権限が与えられているため、事業所との退職に伴う有給取得や未払い賃金等の交渉が可能となります。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
- 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
労働組合法
(交渉権限)
- 第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
雇用期間の定めの有無で対応が変わる
退職代行を受ける場合、サービスを利用する労働者と医療機関との雇用関係が「無期」か「有期」かによって対応が異なります。
民法上、雇用関係は「契約」として扱われ、期間の定めの有無により条文で分けて定められています。
つまり、正規職員のような「期間の定めのない雇用」(無期雇用)については、雇用主である医療機関の了承を得ずに労働者から一方的に解約(退職)の申入れをすることができる規定になっています。
一方、非正規職員のような「期間を定めた」(有期)雇用については、契約期間中は原則、労働者から一方的に契約解除(退職)することはできません。例外として、「やむを得ない事由」がある場合にのみ直ちに契約解除(退職)することができます。
そのため、もしも退職代行業者から連絡を受けた場合、対象労働者の雇用が「有期」であるか「無期」であるかの確認が、特に重要になります。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
退職代行は無視できるのか?
もし、退職代行業者から連絡が入った場合、真っ先に対象労働者と直接やり取りしたくなるでしょう。
それでは、実際、退職代行は無視できるのでしょうか。
これについても、運営元の種類によって対応を変える必要があります。
民間業者系が退職条件交渉などの非弁行為までしてきた場合、対応する必要はないと考えます。
もし、非弁行為に応じて退職手続きを進めてしまうと、場合によっては後になって退職無効にしなければならないなど、何らかのトラブルに発展するケースも考えられます。
労働組合系、弁護士系からの連絡は、無視せず対応する必要があります。
もし、民法等に照らして合法的な退職の申入れに医療機関側が取り合わず、対象労働者に直接連絡を取るなどの行為をした場合、労働者本人を不利益な状況におくものとして損害賠償請求などのトラブルに発展する可能性も考えられます。
退職代行通知を受けたらどうするべきか? 初動対応の5つのポイント

それでは、もし退職代行業者から連絡を受けた場合、どのように対応するべきでしょうか。考えられる初動について以下のとおりまとめました。
- 電話の場合は折り返し対応とする
- 業者の運営元を確認
- 委任状等の提示を求める
- 対象職員との雇用契約、就業規則、関係法令の確認
- 退職代行業者を通した退職意思受入の判断
以下、項目ごとに解説していきます。
初動対応➊:電話の場合は折り返し対応とする
退職代行を名乗る業者から電話連絡が来た場合は、対象労働者の氏名、委任状の有無、先方の連絡先などの概要を聞いて、一旦折り返しの対応にすることが望ましいでしょう。
初動対応➋:業者の運営元を確認
業者の運営元を確認することが重要です。
前述のとおり、退職代行業者の運営元によって対応できる範囲が異なるため、運営元に応じた対応の見極めが必要になります。
ホームページ等で業者の身元を確認して、運営元が前掲の3種類(民間業者系・労働組合系・弁護士系)のうちどこに該当するのか確認します。
初動対応➌:委任状等の提示を求める
職員本人から本当に依頼されているのか確認する必要があります。
念のため、職員と業者との関係を示す委任状や委託契約書などの提示を求めます。もし提示があれば、医療機関側の対応も明らかになりますが、提示がない場合は、本人に連絡して確認する流れになります。
ただ、業者をとおしての退職申し入れのため、本人との連絡は取れないことがほとんどだと思っておいた方がいいかも知れません。
初動対応❹:対象職員との雇用契約、就業規則、関係法令の確認
対象職員の雇用形態が、「無期」なのか「有期」なのか確認します。
期間の定めがない雇用の場合、民法第627条により解約の申入れの日から2週間経過後に雇用は終了します。
有期雇用の場合は、民法第628条により、ハラスメントや違法な長時間労働などやむを得ない事由がある場合は、雇用期間を待たずに退職を認めることになるため注意が必要です。
初動対応❺:退職代行業者を通した退職意思受入の判断
初動対応➊~❹まで全て確認を終えたら、退職代行業者を通した退職意思を実際に受け入れるのか、組織としての判断を行います。
とはいえ、代行業者を利用しての退職申出のケースでは、すでに労使の関係性はこじれていることが想定されます。業者の運営元に関わらず、基本的には退職の申し出を受け入れて、粛々と退職手続きを進めていく流れになることが多いのではないかと考えます。
医療機関に顧問弁護士や社労士などの専門家がいる場合は、相談しながら対応を進めていくことが安心につながるでしょう。
以下、受入判断のポイントについて、運営元が「弁護士系・労働組合系」のケースと「民間業者系」のケース、それぞれ解説したいと思います。
受入判断①:運営元が弁護士系、労働組合系のケース
運営元が弁護士系、労働組合系の場合は、退職希望日や有給休暇の取得の有無、未払い賃金の支払いなど退職に関わる条件確認を行います。
なお、弁護士が相手の場合、代行サービスに訴訟対応が付随しますので、対象労働者からハラスメント等による慰謝料請求がなされないか注意が必要です。
受入判断②:運営元が民間業者系のケース
民間業者系の場合、相手方は退職条件を交渉する権利がありません。委任状等の提示がなければ、業者からの連絡を受け付けずに、本人に直接連絡することを第一に考えます。
ただ、本人への連絡は難航することが予想されます。本人へ直接連絡が取れなければ、やはり民間業者をとおして粛々と退職に向けた手続きを進めていく流れになると思われます。
退職代行を利用した職員への対応ポイント

退職代行の対象職員に対しては、どのような対応を行うべきでしょうか。考えるべきやり取りのポイントを解説します。
対象職員との適切なコミュニケーションとフォローアップ
もし本人と直接電話で連絡を取ることができれば、そこで最終的な退職の意思確認を行います。それに加え、退職に向けた諸手続きの流れや業務引継ぎの確認を行います。
多くの場合、本人と直接やり取りすることが難しくなると思います。その際には、退職代行業者を窓口にして退職手続きを進めていきます。
先方とのやり取りには記録が残るメールや配達記録郵便が望ましいでしょう。
- 退職希望日確認
- 年次有給休暇残日数確認
- 退職届等書類発送・返信依頼
- デスク周りやロッカー等私物の有無確認
- 職場からの貸与品返却の確認など
退職後の引き継ぎと業務整理の方法
退職代行サービスを利用された場合に問題になるのが、対象職員からの業務の引継ぎです。
可能性は低いですが、直接本人と引継ぎできるようであれば、双方に負担がかからないよう短時間で効率的に行うよう計画します。
退職者本人と直接引継ぎできない場合は、本人に書面で引継ぎ事項を書き起こしてもらい、それを上司や同僚がチェックして不明箇所があれば質問を添えてバックする。これを繰り返して引き継ぎ書を完成させる流れになるでしょう。
再発防止のための組織内改善策
有給休暇は計画的に通年で分散して取得
退職代行の利用の有無を問わず、退職時にまとめて有給休暇を消化するケースが多くみられます。
5日間の有給休暇取得義務が2019年から行われていますが、義務となる5日を含め、職員ごとに1年を通して計画的に分散して取得させていく体制を作ることが理想と言えます。
これができれば、退職代行を利用された場合も含め、退職時にまとめて有給取得された際の業務上のダメージが軽減されます。
業務の属人化を防いで引継ぎのリスクを減らす
業務が属人化している場合、退職代行を利用されると医療機関の運営に支障が出る可能性があります。
平時から業務の属人化が進まないように、担当業務ごとに業務標準化を進め、マニュアルを整備し部署内で共有しておくことが大事になります。
医療機関で退職代行を使われたとき:実際の体験談
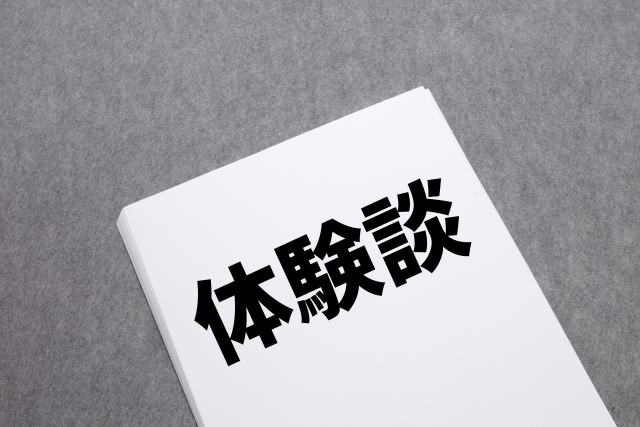
ここでは、筆者が実際に退職代行業者と行ったやり取りの一部を体験談として共有します。
退職代行業者から突然の電話が…
筆者が医療機関の総務部門在籍時に、実際、退職代行サービス業者から電話を受けたことがあります。本当に突然のことでした。
電話で職員の退職を通知してきたのは労働組合系の代行業者です。その職員は退職を希望しており、基本的には業者をとおして連絡のやり取りをしたいとのことでした。
退職を申し出ている職員の所属長に情報共有すると、すでに体調不良で欠勤が続いていたことや業務継続が難しいことについて認識していたとのことでした。
業者とのやり取り開始、そして退職を了承
こちらから折返しの連絡を入れ、電話やメールで業者とのやり取りが始まりました。その職員は残りの有給休暇を使って、〇月〇日に退職したいと希望を示しました。
病院でもその職員の年次有給休暇残日数を確認し、希望の退職日での退職を了承しました。辞職願の記載など、退職に必要な本人との諸手続きは郵送で行いました。
辞職願にはハラスメントの文字が…
本人から辞職願が返送されてきました。記載内容をみると、部署内でハラスメントを受けて勤務継続困難と書かれています。それを受け、関係者へハラスメントの事実確認のため聞き取り調査を開始しました。
しかし、被害を訴えている本人からの聞き取りができない以上、事実確認が取れずにやむなく調査終了となりました。
コミュニケーションの重要性を認識
退職手続き自体は粛々と進めていきました。ただ、訴えのあったハラスメントの断定はできず、直接職場改善につなげることができませんでした。
代行業者をとおした退職はとても後味が悪いものです。職場の風とおしや、コミュニケーションの重要性が改めて認識できた事案となりました。
退職代行の背景を理解する

これまでみてきた退職代行サービスですが、なぜ退職代行が利用されるのか、その背景について各種調査をもとに解説したいと思います。
なぜ退職代行を使われるのか? 背景にある問題とは
退職代行が利用される背景には、どのような問題があるのでしょうか。
問題の多くは、人手不足とそれに伴う長時間労働、職場からの強引な引き留めや退職届を受理してくれないという理由で、仕事を辞めたくても辞められない労働者がいるということが背景にあります。
つまり、辞めたくても辞められない労働者に代わって、事業所に退職の意思を伝えるのが退職代行サービスとなります。
その一方で、仕事に対する意識や価値観の変化に伴い、手軽に仕事を辞められる手段として用いられるケースもあるようです。
ここでは退職代行サービスの認知度や利用の考え方について、エン・ジャパン㈱が行ったアンケートをもとに探っていきたいと思います。
『7,700人に聞いた「退職代行」実態調査』(調査期間:2023年8月29日~9月26日、有効回答数:7,749名)から抜粋して調査結果を紹介します。
退職代行サービスの認知度は7割強
退職代行サービスの認知度と利用の有無に関する調査です。
7割以上の認知度があるものの、実際の利用は7%に留まっています。
- 「知っている」72%
- 「知らない」18%
- 「ある」7%
- 「ない」93%
退職代行サービスを利用しない理由で世代間格差が顕著
Q.退職代行を利用しない理由を教えてください。(複数回答可)
| 回答 | 全体 | 20代 | 30代 | 40代 |
| 1位:退職意向は自分で会社に言うべきだと思うから | 44% | 35% | 43% | 49% |
| 2位:金銭的な負担があるから | 26% | 34% | 28% | 22% |
| 3位:お世話になった会社や同僚に失礼だから | 24% | 23% | 25% | 25% |
| 4位:円満退社にならないから | 20% | 21% | 21% | 20% |
| 5位:モラルや礼儀がない、無責任だと思われるから | 18% | 16% | 19% | 19% |
退職代行を利用しない理由として、1位の「退職意向は自分で会社に言うべきだと思うから」と回答した割合を年代別にみると、20代が最も低く、40代が最も高くなっています。
それとは逆に、2位の「金銭的な負担があるから」と回答した割合は、20代が最も高く、40代が最も低くなっています。
この回答割合からも、若年層の仕事に対する認識の変化や世代間の意識のギャップが見て取れます。
退職代行利用者は2つに分類される
弁護士で社会保険労務士の小澤亜季子氏は、著書「退職代行 『辞める』を許さない職場の真実」のなかで、退職代行サービスの利用者は大きく分けて
- 「ヘビーな問題を抱えた相談者」
- 「ライトな問題を抱えた相談者」
の2つに分類されると言っています。この2つのタイプの特徴は、以下の表のとおりまとめることができます。
| ヘビーな問題を抱えた相談者 | ライトな問題を抱えた相談者 |
| 社長や上司がパワハラを行う 退職届を受け取ってもらえない 辞めると言ったら報復を示唆される、報復を受ける 会社から不利な内容の書面にサインを求められる 体調不良、メンタル不全である 残業代を請求したい | 面倒くさい 周囲を気にしすぎてしまう、過剰な忖度をしている |
引用元:小澤亜季子著「退職代行 『辞める』を許さない職場の真実」(SB新書)
退職代行利用の経緯と退職理由
民間業者・退職代行モームリが行った「15,934件の退職代行モームリ利用者の極秘データ公開」(調査期間:2022年3月15日~2024年7月31日、調査対象者:15,934名)から、サービス利用の経緯や利用者の属性データの特徴を探っていきたいと思います。
参考:退職代行モームリ累計利用者15,934名分のデータ・利用された企業情報を公開 | 株式会社アルバトロスのプレスリリース (prtimes.jp)
Q.退職代行モームリ利用の経緯・退職理由
退職代行サービス利用の経緯と退職理由をみてみると、上司からのハラスメントやサービス残業などが上位を占めていることがわかります。
- 1位:上司から各種ハラスメントを受けている(33.9%)
- 2位:上司から退職を止められる(30.2%)
- 3位:サービス残業がある(24.7%)
- 4位:勤務外での仕事がある(18.7%)
- 5位:有給が使えない(圧力がある)(13.0%)
Q.性別年齢別利用者数
退職代行サービスを利用する年齢層は、20代が60.9%と圧倒的に多いことがわかります。性別については大きな特徴はみられませんが、男性の割合が若干高いことが分かります。
【年齢別】
- 10代 769名(4.8%)
- 20代 9,708名(60.9%)
- 30代 3,583名(22.4%)
- 40代 1,353名(8.4%)
- 50代 469名(2.9%)
- 60代 52名(0.3%)
【性別】
- 男性 8,182名(51.3%)
- 女性 7,562名(47.5%)
- (回答なし190名)
Q.職種別利用者数(正社員・契約社員等)
職種別にみると、「サービス業」が12.5%で最も利用率が高いことが分かります。「医療関連」は9.1%で3番目に高くなっています。
- 1位:サービス業 1,564名(12.5%)
- 2位:製造業 1,514名(12.1%)
- 3位:医療関連 1,139名(9.1%)
- 4位:営業 1,065名(8.5%)
- 5位:事務関連 879名(7.0%)
Q.勤続年数別利用者数
サービス利用者の勤続年数をみてみると、「1ヶ月~6ヶ月」が38.7%で最も多くなっています。「1ヶ月未満」と合計すると、全体の63.2%のサービス利用者が6ヶ月以内の勤続年数であったことがわかります。
- 1ヶ月未満 3,903名(24.5%)
- 1ヶ月~6ヶ月 6,169名(38.7%)
- 6ヶ月~1年 1,890名(11.9%)
- 1年~3年 2,433名(15.3%)
- 3年以上 1,539名(9.7%)
医療機関特有の職場環境と退職理由
前掲した退職代行モームリの調査では、退職代行サービスの職種別利用者数は医療関連が3位で、全体の約10%を占めていることがわかります。
医療機関で多い退職理由として、
- 過重労働
- 人員不足
- 少ない給料
が挙げられます。また表に出てこない理由として、
- 職場の人間関係の悪化
- 人間関係に伴う体調不良
が多くを占めています。
医療機関は労働集約型産業と言われています。医療機関にとって重要なのは、職場環境の改善をとおして、その医療機関で働く職員の満足度をいかに向上させられるかにあると言えるでしょう。
職場環境の見直しと職員満足度向上の方法
医療機関にとって人材確保は、経営上の重要課題です。職員の定着を図り人材確保を推進するには、以下の施策をとおして職員満足度を向上させることが重要だと考えます。
方法①:職場環境の整備
過重労働や人員不足を解消するためには、運営に必要な人材を確保することが重要になります。その他以下の施策も必須となります。
- 雇用形態やシフトの柔軟化による人員確保
- 業務負担の平準化
- 計画的な有給休暇取得の取り組み
- 業務標準化による生産性向上
- ハラスメント防止対策
「4.業務標準化による生産性向上」のきっかけづくりについて、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
方法②:福利厚生の充実
医療機関においても、メンタル不全で休職や退職に至るケースが増えています。職員の福利厚生を充実させるために、以下の取り組みを検討する必要があります。
- 研修会でメンタルヘルスの重要性を啓蒙
- 職員各自で行うセルフケア促進
- 上長によるラインケア充実
- 院内でのメンタルヘルス相談体制整備
- 外部EAP導入
職員のメンタルヘルスケアに関する施策については、以下の3つの記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
未来への対策とコミュニケーション改善

退職代行を防ぐための効果的なコミュニケーション戦略
退職代行の利用を防ぐためには、職場のコミュニケーションを活性化して上司と部下の信頼関係を構築することが非常に重要です。
そのためには、職員の心理的安全性を確保する必要があります。
部署内での朝礼・終礼、定期的なミーティングを実施し、職員間でのコミュニケーションの機会を設けることが大事になります。
メールやラインなどコミュニケーションツールの発達により、組織の人間関係は希薄になりがちですが、上司と部下、スタッフ同士の対面でのやり取りは、職場の雰囲気や風通しを良くするきっかけとなります。
心理的安全性の確保の方策については、以下の記事で解説していますので、是非ご確認ください。
信頼関係を築くためのリーダーシップとフォロワーシップ
信頼関係を構築して組織を発展させるためには、リーダーシップとともにフォロワーシップも求められています。
フォロワーシップとは、フォロワーとなる部署の職員が能動的にリーダーや関係職員の支援を行うことを言います。
また、従来から必要とされてきた支配型のリーダーシップは、指示待ち型の職員を生み組織を閉塞させる要因になります。上司は職員の支援者として振る舞い、職員から意見を挙げやすい雰囲気を作ることが重要です。
支援型のリーダーシップとフォロワーシップの醸成を図ることで、風通しのいい職場風土をつくり、組織の連帯感を高め、職員の定着を推進させることが期待できます。
定期的な従業員フィードバックの重要性と実践方法
目標管理制度を取り入れている医療機関においては、定期的な面談の機会は設けていると思います。少なくとも年に1~2回は面談を行っていると思いますが、可能であれば月に1回程度、1on1ミーティングを取り入れて、上司と部下との会話の機会を設けることが理想です。
1on1ミーティングは、業務の進捗管理が目的ではなく、部下の悩みを傾聴しながら上司がアドバイスを行うことで、職場のコミュニケーション促進の機会となります。1on1の時間をとおしてお互いの信頼関係が高まれば、退職代行を利用されるリスクも軽減されるはずです。
医療機関における1on1の導入施策については、以下の記事で解説していますので、併せてご参考ください。
個々の価値を活かす施策で未来の「人財」確保を目指す
人手不足のいま、民間企業では人的資本経営が求められています。
医療機関においても職員個々の特徴を理解し、職員の価値を最大限に活かす施策をとおして、組織の持続的価値向上を図ることが重要になります。
組織の持続的価値向上は、未来の優秀な「人財」を確保するきっかけにもなるのです。
医療機関における人的資本経営の考え方について、以下の記事でも解説していますので、併せてご参考ください。
まとめ
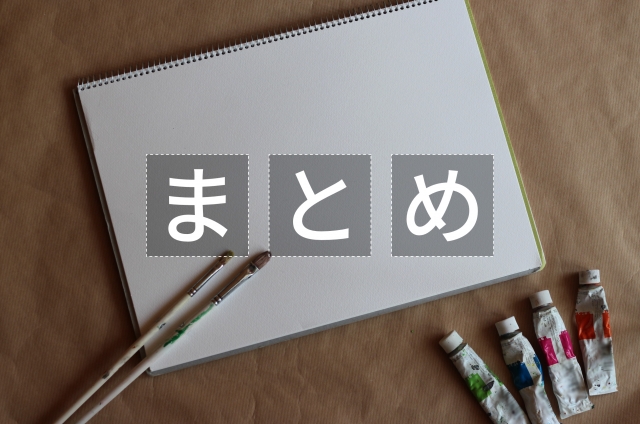
今回は、退職代行を使われた際の対応方法や、医療機関での職場環境改善の方策について考えてきました。
最後に改めて、退職代行を使われた場合の初動対応と受入判断をまとめたいと思います。
- 電話の場合は折り返し対応とする
- 業者の運営元を確認
- 委任状等の提示を求める
- 対象職員との雇用契約、就業規則、関係法令の確認
- 退職代行業者を通した退職意思受入の判断
・運営元が弁護士系、労働組合系のケース
⇒退職希望日や有給休暇の取得の有無、未払い賃金の支払いなど退職に関わる条件確認を行う
・運営元が民間業者系のケース
⇒退職条件の交渉権利がないため、委任状等の提示がなければ代行業者への対応はせずに、本人に直接連絡することを第一に考える
本記事の内容のなかで、退職代行が利用される背景には、過重労働やコミュニケーション不足などによる職場環境の悪化が原因となることがわかりました。
離職防止や人材確保が重要課題となる多くの医療機関においては、後にも先にもコミュニケーションの強化が何より重要だと言えるでしょう。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。








