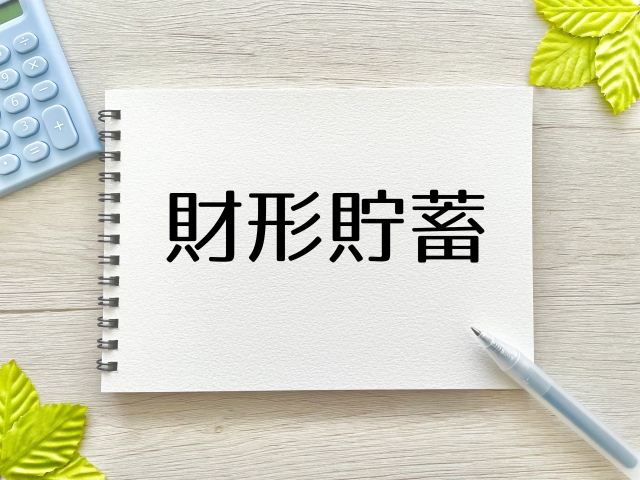皆さまの職場には、財形貯蓄制度はありますか?
給料の使い方は人それぞれです。コツコツと貯金に回す人もいれば、生活費を除いた分を全て使ってしまう人もいるでしょう。
色々な人がいるなかで、この財形貯蓄制度は、社会人にとって、計画的に資産形成を行うことができる最初の選択肢となるかも知れません。
今回は、財形貯蓄の制度内容や、利用する際のメリットやデメリット、注意点などについて考えていきたいと思います。
財形貯蓄の特徴を紹介

これまで、「財形」という言葉を聞いたことがあったとしても、詳しいことまでは知らない、という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、財形貯蓄の特徴について、簡単に紹介したいと思います。
特徴1:雇用される人が利用できる
財形貯蓄制度を利用できる人は、「勤労者」とされています。
「勤労者」とは、職種を問わず事業主に雇用される人です。条件が合えば、パートタイマーや派遣社員も利用することができます。
特徴2:給与天引きで積立できる
財形貯蓄制度とは、毎月の給料から天引きして積み立てることができる貯蓄制度です。
特徴3:1,000円から手軽に始められる
財形貯蓄制度は、1,000円から積み立てを始めることができます。
ボーナス時に増額の設定もできますし、経済的な事情から給与天引きが難しくなったときは、積み立ての中断(2年間)もできます。
特徴4:3種類の方法がある
財形貯蓄制度には、以下の3種類の方法があります。
- 一般財形貯蓄
- 財形住宅貯蓄
- 財形年金貯蓄
それぞれポイントをみていきたいと思います。
➊一般財形貯蓄
1つ目は「一般財形貯蓄」です。
一般財形貯蓄は、使い方自由で、幅広く使える財形貯蓄です。
- 目的を定めない積立貯蓄(旅行・結婚・出産費用など何でも)
- 積立の期間は、原則3年以上(1年経過後は払い出し自由)
- 積立の限度額なし
- 非課税の適用なし(非課税の恩恵が受けられない)
- 年齢制限なし
➋財形住宅貯蓄
2つ目は「財形住宅貯蓄」です。
財形住宅貯蓄は、マイホーム購入やリフォーム費用の資金づくりのための財形貯蓄です。
- 住宅資金のための積立貯蓄
- 積立の期間は、5年以上
- 合計550万円までの非課税措置あり(財形年金貯蓄と合わせて)
- マイホーム取得時やリフォーム時に「財形持家融資」を利用できる
- 目的外の払い出しでペナルティあり(5年間遡って課税される)
- 申込は55歳未満まで
➌財形年金貯蓄
3つ目は「財形年金貯蓄」です。
財形年金貯蓄は、老後の資金づくりのための財形貯蓄です。
- 60歳以降に年金として受け取るための積立貯蓄
- 積立の期間は、5年以上
- 合計550万円までの非課税措置あり(財形住宅貯蓄と合わせて)
- 目的外の払い出しでペナルティあり(5年間遡って課税措置あり)
- 申込は55歳未満まで
財形貯蓄のメリットやデメリット、注意点とは

次に、財形貯蓄制度のメリットとデメリット、注意点についてみていきたいと思います。
財形貯蓄制度のメリット5つ
財形貯蓄制度には、以下の5つのメリットがあります。
- 着実・手軽に貯蓄できる
- 計画的に貯蓄できる
- 安全性が高い
- 利子が非課税(一般財形を除く)
- 財形持家融資が使える
それぞれ簡単に説明したいと思います。
メリット➊:着実・手軽に貯蓄できる
給与天引きのため、自動的かつ着実に貯蓄ができます。
1,000円から積立できるので、手軽に始められます。
メリット➋:計画的に貯蓄できる
結婚やマイホーム購入、老後など、自身のライフイベントに向けて計画的に貯蓄できます。
メリット➌:安全性が高い
「貯蓄型商品」を選べば、元本割れのリスクがありません。
反対に、「保険型商品」を選ぶと元本割れのリスクが生じるため、注意が必要です。
メリット❹:利子が非課税(一般財形を除く)
「財形住宅」と「財形年金」の場合、利子に対して非課税の恩恵を受けることができます。
つまり、原則は利子に対して一律20.315%の源泉分離課税が適用されるところ、その分が非課税となるため、より効率的な資産運用が可能となります。
メリット❺:財形持家融資が使える
財形持家融資制度とは、「国と事業主が協力して、勤労者の財産の主要な柱である持家の取得を促進しようとする融資制度」です。
「一般財形」・「財形住宅」・「財形年金」の合算貯蓄残高50万円以上、1年以上継続の積立があれば、財形持家融資制度を利用できます。
貯蓄残高の10倍の金額(最高4,000万円)、かつ物件価格の9割の範囲内まで融資を受けられます。
制度のメリットや詳細については、以下の厚生労働省のホームページに掲載されていますので、是非ご参照ください。
財形貯蓄制度のデメリット3つ
一方で、財形貯蓄制度には、以下の3つのデメリットがあります。
- 誰もが利用できない
- 金利が低いと制度のメリットが活かせない
- 元本割れリスクがある
それぞれ簡単に説明します。
デメリット➊:誰もが利用できない
勤務先に財形貯蓄制度がなければ利用できません。
デメリット➋:金利が低いと制度のメリットが活かせない
近年の低金利政策においては、制度のメリットとなる非課税の恩恵が活かされません。
その中で、2024年3月に日銀はマイナス金利政策を解除しました。それ以降、政策的な利上げが続いていることから、今後は以前より非課税メリットを享受できる可能性が高まっていると考えられます。
デメリット➌:元本割れリスクがある
保険型商品を選ぶと、元本割れのリスクがあります。(貯蓄型商品を選べば元本割れリスクなし)
財形貯蓄制度の注意点4つ

財形貯蓄を利用する場合、どのような点に注意すべきでしょうか。
ここでは、以下の4点を挙げたいと思います。
- 引き出しに時間がかかる
- 目的外の払い出しはペナルティあり
- 転職時の移管で課税扱いになるケースあり
- 転職先の制度次第で貯蓄継続不可
それぞれ簡単に説明します。
注意点➊:引き出しに時間がかかる
職場をとおした手続きが必要になるため、急な入用で引き出しする場合は、1週間程度の時間をみておく必要があります。
注意点➋:目的外の払い出しはペナルティあり
「財形住宅」と「財形年金」は、目的外で払い出した場合、ペナルティとして、過去に遡って利子に課税されます。
注意点➌:転職時の移管で課税扱いになるケースあり
転職先に財形制度がある場合でも、前の職場の退職後、2年以内に新しい勤務先で財形制度を再開できない場合は、目的外の払い出しとして課税扱いとなります。
注意点❹:転職先の制度次第で貯蓄継続不可
転職先に財形制度がなければ、前職の貯蓄を継続できません。
医療従事者と医療機関、それぞれが考えておきたいこと

医療機関で働く方々は、日々の診療業務の忙しさから、自身のお金に向き合う機会もなかなか取れないのではないでしょうか。
特に医師の方々は、給与明細すら見ない方も少なくないと思います。
ここでは、医療機関の運営者やそこで働く医療従事者が、スタッフ個々の資産形成の面においてどのようなことを考えるべきなのか、解説したいと思います。
医療従事者が考えておきたい3つのこと
まず、医療従事者として考えておきたいことについて説明したいと思います。
医療従事者として考えておきたい3つのこと
- 自律的なキャリア形成は、自身の経済的な自立からもたらされる
- 自身の経済的自立は、計画的な資産形成からもたらされる
- 計画的な資産形成は、安全で確実に積立が継続できる財形貯蓄が適している
医療の専門家として、自律的に働いていくには、経済的な不安が解消された状態であることが望ましいと考えます。
そのためには、リスクを極力減らしながら、着実に積み立てが続けられる財形貯蓄を利用して、計画的に資産形成を行うことが第一の選択肢となりそうです。
資産形成の成功体験を少しずつ積み重ねることは、金融リテラシーの向上にもつながります。
なお、財形貯蓄よりリスクを取った資産形成の方法として、iDeCoやNISAの利用が考えられます。制度の拡充が続いているこれらの内容について、以下の2つの記事でそれぞれ解説していますので、併せてご参考ください。
医療機関が考えておきたい3つのこと
一方、多くの医療機関では、利便性の高い福利厚生の制度はあるものの、継続的に職員にアナウンスし続けて、利用を促すことがなかなかできていないのが現状ではないでしょうか。
ここでは、医療機関として考えておきたいことについて、説明したいと思います。
医療機関として考えておきたい3つのこと
- 医療機関の価値の向上は、人材の価値の向上からもたらされる
- 人材の価値の向上は、スタッフの経済的自立が一つの要因となる
- スタッフの経済的自立を後押しするために、施設の福利厚生として財形貯蓄制度の導入が有効であると考えられる
医療機関側がスタッフの経済的自立を後押しできれば、スタッフが経済面において安心して働くことが可能になります。
経済的な安心感は、スタッフの幸福度を上げ、職場に対する愛着や貢献意欲が向上します。
人材が定着し、人材の質の向上が医療機関の価値そのものを向上させる要因にもなり得るのです。
以下の記事では、医療従事者の金融リテラシー向上とエンゲージメント向上の関係性について解説しています。併せてご参考ください。
お金が勝手に溜まっていく仕組みこそが最大のメリット

ここまで、財形貯蓄制度のメリットやデメリット、利用上の注意点や医療機関の福利厚生としての意義について解説してきました。
筆者が感じる財形貯蓄の最大の長所は、いざ給与天引きを始めたら、言わば半強制的に積み立てが継続されて、勝手にお金が溜まっていく仕組みにあると考えています。
何ごとも、継続こそが力の源になります。
そして、商品の選択を間違わなければ元本割れするリスクも排除でき、安全に貯蓄が続けられ、スタッフはその分仕事に集中することができます。
まとめ
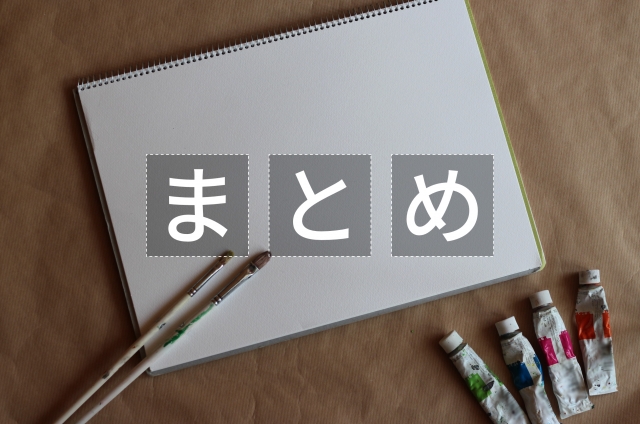
最後に、財形貯蓄のメリット・デメリット・注意点を一覧にまとめたいと思います。
| メリット | デメリット | 注意点 |
| 着実・手軽に貯蓄できる 計画的に貯蓄できる 安全性が高い 利子が非課税(一般財形を除く) 財形持家融資が使える | 誰もが利用できない 金利が低いと制度のメリットが活かせない 元本割れリスクがある | 引き出しに時間がかかる 目的外の払い出しはペナルティあり 転職時の移管で課税扱いになるケースあり 転職先の制度次第で貯蓄継続不可 |
今はNISAやiDeCoなど、非課税メリットを享受できる制度も整ってきています。
しかし、安全かつ着実に資産形成をしていきたい人は、まずは、財形貯蓄からスタートして、ある程度資金がまとまった段階で、NISAやiDeCoなどの制度を使って資産運用を始めてみてもいいかも知れません。
医療機関においては、福利厚生面で他の医療機関との差別化を図るうえでも、財形貯蓄制度の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。