医師の働き方改革や地域医療構想の対応など、医療機関にとって頭を悩ませる問題が次々と押し寄せてきています。
人材が限られる多くの医療機関にとって、外部の専門家の手を借りることは、激動の医療業界を確実に歩んでいくための重要な選択肢のひとつと言えるでしょう。
今回は、医療機関における社労士との顧問契約の必要性やその活用方法について考えていきたいと思います。
社労士は「ヒト」に関する専門家

社労士とは?
実際、社労士(社会保険労務士)とはどのような職業なのでしょうか?
社労士とは、一般的に、事業で必要な経営資源とされる「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち「ヒト」に関する専門家と言われ、社会保険労務士法で定められた国家資格者となります。
社労士は、1968年(昭和43年)に制定された比較的新しい国家資格です。いわゆる8士業のひとつに数えられ、医師や看護師と同様、有資格者以外の者が携わることが禁止された業務独占資格とされています。
社労士に依頼できる業務
それでは、社労士にはどのようなことを依頼できるのでしょうか。
社労士の業務範囲については、社会保険労務士法第2条で定められています。下表にまとめ、簡単に解説していきたいと思います。
| 業務区分 | 業務内容 | 主な業務例 |
| 1号業務 【独占業務】 | 労働及び社会保険に関する申請書等の作成、提出 | 採用・退職時の健康保険・雇用保険の処理、労災手続 |
| 2号業務 【独占業務】 | 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成 | 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・就業規則の作成 |
| 3号業務 | 労務管理・社会保険に関する相談、指導 | 働き方改革、賃金制度、安全衛生管理、ハラスメント対応 |
労働及び社会保険に関する申請書等の作成、提出(1号業務)
これは1号業務と言われる社労士の独占業務です。
例えば、職員の採用・退職時に生じる健康保険や雇用保険の申請書類を作成して、提出する業務がこれにあたります。
その他、職員が仕事中にケガをした場合の、労災手続の書類を作成する業務もあります。
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)
これは2号業務と言われる社労士の独占業務です。
例えば、職場の法定三帳簿と言われる労働者名簿や賃金台帳、出勤簿の作成がこれにあたります。
また、職場のルールブックとなる就業規則の作成も社労士の独占業務となります。
労務管理・社会保険に関する相談、指導(3号業務)
これは3号業務と言われる業務で、1・2号業務と異なり社労士以外の人でもできる業務となります。
例えば、賃金制度や安全衛生管理、どこの事業所でも頭を悩ませているハラスメント対応など、人事・労務の多岐にわたるコンサルティング業務があります。
働き方改革関連法における企業支援
働き方改革関連法は、2019年から一般企業に適用されており、適用以前から社労士による企業への支援が行われてきました。
勤務医に対しては5年間の猶予が与えられていましたが、2024年4月から医療機関で働く医師にも適用開始となりました。それを見越して、準備段階から社労士の助言を得ながら勤務管理等の対応をしている施設もあります。
しかし、大半の医療機関は、通常業務と並行して自力で働き方改革の対応を迫られているのが実情だと推察します。しかもこの対応は一時のものだけではなく、今後も継続的に管理し続けなければなりません。
限られた戦力で継続的な対応をし続けなければならない状況を考えると、外部の専門家の意見を取り入れながら自院で管理しやすい運用を早い段階で確立することは、施設にとってとても重要な選択肢になると考えます。
医療機関における社労士活用のメリットとは?
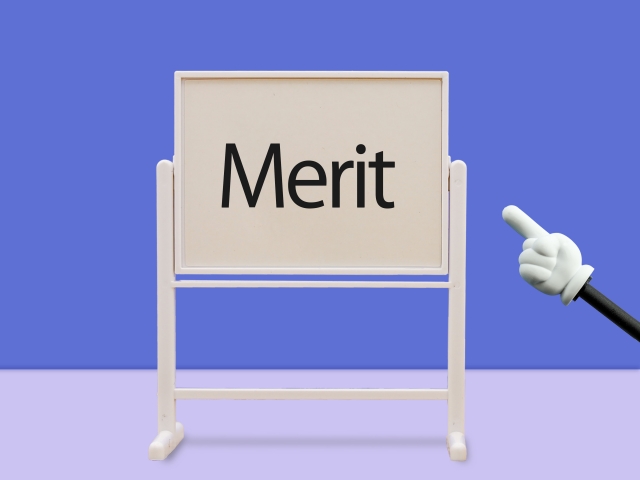
医業へ注力するためにも社労士活用を
これまで、一般的に社労士ができる仕事内容について確認してきました。
医療機関でも、採用から退職までの労働・社会保険に関する諸手続のほか、就業規則の作成、給与計算の代行など、多くの業務を社労士に依頼することができます。
後にも触れますが、これらをアウトソーシングすることで、業務に余裕を持たせ、何より大事な診療内容の充実や患者サービスの向上、医療安全、感染防止対策などの時間を増やすことができるのです。
次項では、具体的な社労士活用の期待効果についてみていきたいと思います。
社労士を活用する5つの期待効果
患者サービス向上など本来の業務に力を注ぐためにも、社労士の活用は施設にとって有益だと考えます。
それでは、社労士を活用することで具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、以下の5点を挙げたいと思います。
- 働き方改革が進めやすい
- 「ヒト」の問題への対応ノウハウが得られる
- 職場環境改善により離職防止が図れる
- 本来の患者サービスのための時間が増やせる
- 助成金の活用で生産性向上が図れる
期待効果①:働き方改革が進めやすい
まず、2024年度から始まった医師の働き方改革が進めやすいという効果が挙げられます。
自力で対応を迫られている医療機関にとっては、医師の働き方改革において、「意識改革」の点で苦慮しているところが少なくないのではないでしょうか。
そのなかで、自院の職員が改革の必要性を事務的に伝えるより、外部の専門家の意見もプラスしてアナウンスすることで、医師を始めとした施設全体の「意識改革」が説得力をもって進めやすくなると考えます。
社労士が関与した医療機関における働き方改革の具体的な対応については、以下の2つの記事でも取り上げていますので併せてお読みください。
期待効果②:「ヒト」の問題への対応ノウハウが得られる
次に、「ヒト」の問題への対応ノウハウが得られるという効果が挙げられます。
最も医療機関の頭を悩ませている問題と言えば、やはり「ヒト」の問題なのではないでしょうか。職員同士の問題、職種間の問題、部署間の問題、患者や家族との問題…など、医療機関にはどうしても対人関係の問題がつきまといます。
社労士は「ヒト」に関する専門家と言われています。職場の「ヒト」に関する法令上の知識と、自身の社労士業務から蓄積した知見を基に、医療機関がとるべき対応ノウハウの助言が得られることが期待できます。
医療機関は、職員に対して安全配慮義務が課されています。施設内で起こる対人関係を軽視すると医療機関に法的責任が問われますので、そうなる前に専門家に助言を求めることも検討の余地があるでしょう。
職員に対する安全配慮義務や患者等からのペイシェントハラスメントの対応に関しては、以下の2つの記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。
期待効果③:職場環境改善により離職防止が図れる
また、職場環境改善により離職防止が図れるという効果も期待できます。
社労士は就業規則の他、賃金・育成・評価制度、メンタルヘルスや安全衛生体制の整備や見直し、改善に寄与することができます。
これらによって職場環境が改善されれば、職員満足度が向上し、そもそもの離職防止が図れます。
そして、社労士を活用した職場環境改善が施設の評判を向上させ、職員の急な退職にも即座に補充が行える良好な採用環境が構築できるという好循環も期待できます。
職員のメンタルヘルスや安全衛生の体制整備については、以下の4つの記事で詳しく解説していますので併せてご参考ください。
期待効果④:本来の患者サービスのための時間が増やせる
4点目に、本来の患者サービスのための時間が増やせるという効果が挙げられます。
主に総務・人事部門に関する手続業務を社労士に委託することで、職員の業務負担の軽減が図れます。
そしてその分、本来医療機関が求められている診療の質の向上、患者サービス向上や医療安全、感染防止などのコア業務に時間を割くことができ、施設の価値向上に寄与する効果が期待できます。
患者サービス向上に必要なコミュニケーション能力を高める方策について、以下の2つの記事で解説しています。併せてご参考ください。
期待効果⑤:助成金の活用で生産性向上が図れる
最後に、助成金の活用で生産性向上が図れるという効果が挙げられます。
労働・社会保険諸法令に関する助成金の申請代行業務は、社労士の独占業務とされています。つまり、社労士にはそもそもの助成金の種類や内容、条件、申請手続きに関するノウハウがありますので、助成金業務を社労士に委託することで、効率的に助成金という経済的メリットを享受することができます。
そして、獲得した助成金を活用して院内体制を整備することで、職場の生産性の向上や施設自体の価値向上を図ることが可能となります。
職場の生産性向上の方策に関して、以下の記事で解説していますので、併せてご参考ください。
顧問契約か、スポット契約か?
医療機関が社労士を活用する場合、顧問契約とスポット契約の2パターンが考えられます。
より社労士活用の期待効果を高めるためには、顧問契約を結ぶことが重要だと言えるでしょう。
顧問契約を締結し、自施設のことを深く理解してもらいながら、じっくりと職場改善を図ることができるからです。
一方、顧問契約をしないまでもスポット契約を交わすことでピンポイントに課題解決を図る方法もあります。
いずれにせよコストはかかってしまいますので、もしすでに何らかの労務管理等の悩みを抱えている場合は、まずスポット契約で効果を試してみて、期待どおりの効果が得られた場合は顧問契約に移行する、ということでもいいかも知れません。
期待効果の裏付けは「外部視点」にあり

「外部視点」が生み出すメリットとは?
前項では社労士活用の5つの期待効果についてお話しましたが、その期待効果の裏付けは、全て「外部視点」にあります。
ここでは、その「外部視点」が生み出すメリットとして以下の3点を挙げて説明していきたいと思います。
- 人事業務に対する安心感が得られる
- 職員への説明で納得感が得られやすい
- 研修の効果が向上する
メリット➊:人事業務に対する安心感が得られる
第1に、人事業務に対する安心感が得られるというメリットが挙げられます。
人事・労務関係の業務においては、度重なる法改正への対応が避けられません。総務部門に多くの戦力を割けない医療機関にとっては、社労士という外部資源を活用することで適正に諸規程を運用することが可能になります。
また、例えばハラスメント対応についても、外部視点を持った第三者の意見を聞いて対応することができれば、被害を受けた職員に対しても、その相手方に対しても、より安心・納得感のある対処を施すことができると言えます。
そもそも顧問弁護士との契約はあるものの、なかなか弁護士さんには聞きづらい…、という医療機関も少なくないのではないでしょうか。
社労士であれば弁護士ほど敷居は高くありませんので、特に「ヒト」の問題に関しては迅速かつ適正な対応が期待できるのではないかと考えます。
メリット➋:職員への説明で納得感が得られやすい
第2に、職員へ説明する際に納得感が得られやすいというメリットが挙げられます。
例えば施設の重要な制度を変更する場合、外部の専門家の意見として社労士のコメントをつければ、職員へのアナウンスもしやすく、職員からの納得感も得られやすいでしょう。
そもそも運用を変える際にも、経験豊富な社労士であれば、失敗事例や好事例の情報を複数持っているため、外部視点から自施設に最適な方法を提案してもらうことが可能になります。
メリット➌:研修の効果が向上する
第3に、社労士に研修を依頼することで研修の効果が向上するというメリットが挙げられます。
医療機関では年間通して数多くの研修を実施していると思います。ともすれば義務的に惰性で研修を行うケースもあるのではないでしょうか。
社労士を外部講師として招いて研修を行えば、研修効果を向上させることができるかも知れません。
例えば職員に対するコンプライアンス研修やハラスメント研修などは効果が期待できます。
筆者も医療機関に勤務していた頃は、自施設の職員へ上記の研修を行ったことがあります。
やはり、その施設の職員が講師を行うより、根拠法令や外部の事例などにも精通した専門家を講師として招いて実施する方が、研修を受ける職員の姿勢も異なりますし、何より職員への説得力が上がるため、研修の効果が格段に上がったのではないかと思っています。
社労士に依頼する場合の注意点とは?

これまで社労士へ依頼する場合のメリットについて詳しく触れてきました。
しかし、メリットがある反面、社労士を活用する場合にも以下のような注意点もありそうです。
- 委託コストが増える
- 現場混乱の要因にもなり得る
上記2点について確認していきたいと思います。
注意点➊:委託コストが増える
まず、当然のことながら顧問契約を結ぶ場合は、月単位で定額のコストがかかり続けます。
すでに弁護士や税理士との顧問契約があれば、それに上乗せされるため収支に影響を与える可能性があります。
顧問契約料金は社労士事務所ごとに設定されています。従業員数に応じて料金設定している場合も多く一概には言えませんが、相場としては月額30,000円前後で設定しているところが多いように思います。
コストを抑えるために、すでに締結している他士業との契約内容の見直しが必要になるかも知れません。
なお、社労士には「勤務社労士」という働き方もあります。もし、施設内に社労士の有資格者がいれば、そこまでコストを増やさずに人事・労務分野における人材活用が図れるとともに、職場改善を推進することができます。以下の記事で詳しく解説しています。
注意点➋:現場混乱の要因にもなり得る
2点目に、自施設に合わないルールを導入してしまった場合、現場が混乱する可能性があるという注意が必要です。
そうならないためにも、特に賃金制度や評価制度の導入などに関しては、時間をかけて慎重に行う必要があります。
依頼先の社労士には、医療現場の特殊性や自施設の現状を十分に説明したうえで導入に踏み切ることが重要です。
まとめ
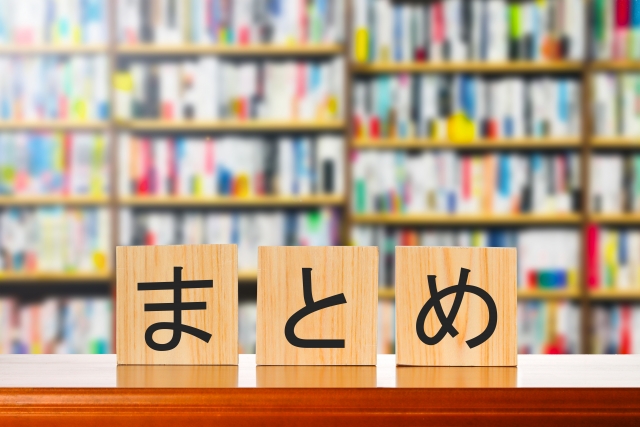
今回は、医療機関における社労士との顧問契約の必要性やその活用方法について考えてきました。
社会活動や雇用環境が複雑化するなか、職場で負の連鎖が始まるとすぐに修復するのは至難の業です。
病棟職員の離職が止まらず、施設基準の維持が難しくなりやむなく病棟閉鎖、というリスクもあり得ます。
そうなる前に、社労士など外部の助言を得て、職場環境改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。
診療内容の充実、患者サービスの向上のほか、医療機関として守るべきところに注力していくためにも、社労士の活用は検討の余地があると考えます。
なお、当事務所は医療業界に特化した労務サービスを提供しております。以下の記事で当事務所の簡単な紹介をしていますので、併せてお読みいただきますと幸いです。もしお問い合わせやご依頼などございましたら、こちらからお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。








