最近になって、しばしば「コミュ力」や「コミュ障」という言葉を耳にするようになりました。
今では、企業が人材を採用する際に重視するポイントの上位に、「コミュニケーション能力」が入ると言われています。
多職種のスタッフと協働し、多くの患者と診療で関わる医療従事者にとって、このコミュニケーション能力は必須の能力と言ってもいいでしょう。
今回は、医療現場で必要とされるコミュニケーション能力と、そのなかでも特に重要となる傾聴スキル向上の取組について考えていきたいと思います。
コミュニケーション能力とは?4つの要素を理解する
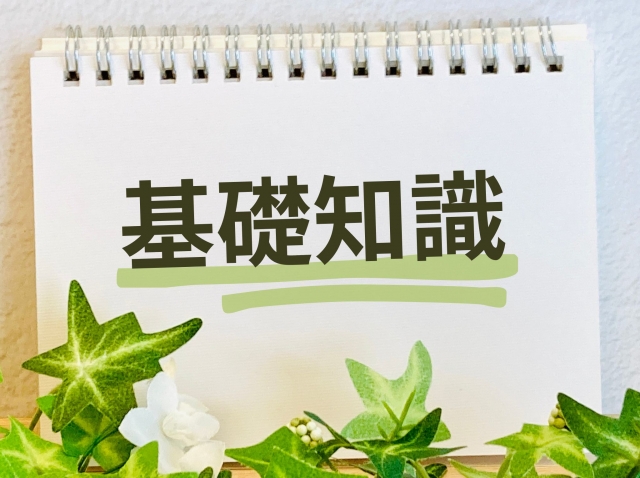
始めに、仕事や人間関係において重視される「コミュニケーション能力」について、少し詳しく掘り下げてみたいと思います。
企業が求める人材像のトップは?
冒頭でも触れたとおり、コミュニケーション能力は、企業が社員に求める人材像のひとつとして挙げられる能力であることは良く知られています。
ここでは、2022年9月に帝国データバンクが発表した「企業が求める人材像」に関する調査結果について紹介したいと思います。(期間:2022年9月2日~5日、対象:小規模企業・中小企業・大企業1,550社から有効回答、方法:インターネット)
| 順位 | 人材像 | 回答割合 |
| 1位 | コミュニケーション能力が高い | 42.3% |
| 2位 | 意欲的である | 42.2% |
| 3位 | 素直である | 35.0% |
| 4位 | 真面目、または誠実な人柄である | 31.8% |
| 5位 | 明るい性格である | 21.9% |
| 6位 | 専門的なスキルを持っている | 18.3% |
| 7位 | 前向きな考え方ができる | 15.4% |
| 8位 | 行動力がある | 12.5% |
| 9位 | 精神的にたくましい | 9.7% |
| 10位 | 主体性がある | 8.6% |
| 10位 | 忍耐力がある | 8.6% |
(マイナビニュースホームページより引用し筆者まとめ)
上の資料のとおり、この調査でもコミュニケーション能力が企業から最も求められている能力として挙げられています。まさに4割以上の企業が「コミュニケーション能力が高い」人材を求めていることがわかります。
そして、コミュニケーション能力の次に多かった回答が「意欲的である」、3番目が「素直である」、そして4番目に「真面目、または誠実な人柄である」という回答が続きます。
このように、企業が求める人材像の上位には、求める人材の人柄や性格面を表す要素が示されていることがわかります。
その一方で、仕事の技術面を示す「専門的なスキルを持っている」という回答は2割を下回る企業しか回答しておらず、上から6番目の回答となっています。
さらに採用形態別に調査結果を分析すると、新卒採用をメインに行っている企業ほど「コミュニケーション能力が高い」人材を求めているとの報告があります。
これはつまり新卒採用する人材に、職場でのコミュニケーションによって対人関係を良好に保ち、長期就業につながるような能力を求めている結果とも言えるかも知れません。
コミュニケーション能力とは
ここで改めて、「コミュニケーション能力」とは一体どのような能力なのか確認していきます。
皆さまは、「コミュニケーション能力が高い人」と聞いて、どのような人をイメージするでしょうか。例えば、社交性があって、会話も上手で、誰とでも仲良くなれるタイプを想像する人も多いのではないでしょうか。
コミュニケーション能力とは、一般的に以下に示す能力と言われています。
上記の説明からわかるとおり、「対人関係において」ということは、つまり双方向のやり取りを円滑にできる能力であることを意味します。
コミュニケーション能力に必要な4つの要素
さらにコミュニケーション能力を深堀りしていきます。
コミュニケーション能力は、大きく分けて「伝える力」と「受け取る力」に大別されます。
そして、2つに大別された「伝える力」と「受け取る力」をさらに細分化し、下の表に示す①~④の4つの要素に分けることができます。
| コミュニケーション能力 | 伝える力 | ①言語 | 話す(書く)内容・言葉選び・感情への働きかけ |
| ②非言語 | 表情・身振り手振り・声のトーン | ||
| 受け取る力 | ③聴く力 | 相手の話の意図や内容を正確に理解 | |
| ④読み取る力 | 相手の言語・非言語情報から真意・本音を理解、推測 |
伝える力には、「①言語」と「②非言語」による能力があります。
「①言語」による能力とは、直接言葉や文字を使って相手に物事を伝える能力、「②非言語」による能力とは、表情や身振り手振りなどを使って相手に物事を伝える能力のことです。
それに対し、受け取る力には、「③聴く力」と「④読み取る力」があります。
「③聴く力」とは、相手の話の内容を理解することや話の意図を理解する能力、「④読み取る力」とは、相手から発せられる言葉や表情、ジェスチャーなどから相手が伝えたいことの真意や本音を理解し、または推測する能力を言います。
コミュニケーション能力の4つの要素を高めていくことは、仕事面においてはもちろんのこと、日常生活における人間関係においても重要であることがわかると思います。
医療従事者にとってなぜコミュニケーション能力が重要なのか?

これまで、コミュニケーション能力の言葉の定義や、企業活動においてコミュニケーション能力が最も重視される能力であることについて確認してきました。
それでは、医療機関に目を移したときに、このコミュニケーション能力はどのように評価されるのでしょうか。
ここでは、医療機関におけるコミュニケーションの必要性と医療従事者に求められる課題について考えていきます。
患者は医療従事者とのコミュニケーションを求めている
患者が医療機関を選ぶ際、以前は、家族や知人に評判を聞いて決めることも多かったと思います。
しかし、インターネットやSNSが発達した現在、誰にも聞かずに、ネット上の口コミだけで受診医療機関を選ぶ人も多くなっているのではないでしょうか。
医療機関の大手検索サイトCalooで利用者の口コミを見てみると、多くの患者が医療機関に、
- 「優しい」
- 「安心」
- 「丁寧」
を求めていることがわかります。
その口コミのなかから2件紹介します。
とにかく親切。症状を細かく聞いてくれてじっくり話をするので安心。
(東京郊外・A内科クリニックに対する口コミ)
近所の内科のなかで一番好き。先生が余計なことを言わずにわかりやすく説明してくれる。安心できるから他に移らず通っている。信頼できる優しい先生。
(東京郊外・B内科クリニックに対する口コミ)
上の2つの口コミから読み取れるように、患者は医療従事者とのコミュニケーションを求めていることがわかります。
つまり、コミュニケーションをとおして自身の症状に対する安心を求めているのです。
以下の記事では、患者が口コミサイトでどのように医療機関の評価を行っているのか、詳しく取り上げていますので是非ご参考ください。

患者からの評価はコミュニケーションで決まる
病気やケガで悩む患者は、特に診察を担当する医師にじっくりと話を聞いてもらい、わかりやすく症状の説明をしてくれると、不安が和らぎとても安心します。
1日20人の予約患者がいる場合、1人の患者は医療機関からみると1日の患者のうちの20分の1の存在かも知れませんが、患者からすると何カ月かに1回の受診機会になります。
その限られた1回の受診機会において、医師や医療従事者とのコミュニケーションの質が高いか低いか、また量が多いか少ないかによって、その医療機関の評価が決まってしまうと言っても言い過ぎではないでしょう。
患者の求めに応じることができるかどうかは、患者と直に接する医師を始めとした医療従事者のコミュニケーション能力次第になります。
そして、患者とのコミュニケーションをより円滑に行うことは、患者の不安を解消して、この先も選んでもらえる医療機関になるための条件になると考えます。
患者とのコミュニケーション不足は診療サービス低下を招く
それでは、医療従事者のコミュニケーション能力は患者を診療するうえで、どのような影響を与えるのでしょうか。
医療現場は、患者とのコミュニケーションの連続です。患者とのコミュニケーションが少なければ少ない程、患者に安心を提供できないどころか、診療上のサービスも低下してしまう可能性をはらみます。
医療現場においては、初診時の問診から「受け取る力」が問われます。つまり、コミュニケーションの4つの要素で言うところの「③聴く力」と「④読み取る力」をフルに発揮することによって、患者が訴える症状を正確に理解し、疾患を特定していく必要があります。
また、診療が進んでいくうちに、患者に対して症状を説明し、同意を求める機会が訪れます。ここでは、「伝える力」が問われます。
医師や看護師などの医療従事者とは異なり、患者は医学的な知識が乏しいです。全く知識がない患者もいるかも知れません。そうした患者を相手にコミュニケーションの4つの要素のうち「①言語」と「②非言語」を駆使して、治療に必要な協力を求めていかなければなりません。
コミュニケーション能力で大別される「伝える力」も、「受け取る力」も、医療従事者においては共に不可欠な能力であることが理解できたのではないでしょうか。
傾聴スキル向上が医療機関の課題

先に触れたとおり、患者とのコミュニケーションは、患者に対する診療の質を上げるための条件になります。
そして、そのコミュニケーションの質を高めていくことは、この先も患者から選ばれる医療機関になるための条件にもなりそうです。
ここでは、コミュニケーション能力における「伝える力」と「受け取る力」のうち、「受け取る力」に焦点を当て、その重要性について考えてみたいと思います。
診療でより重要になるのは「聴く力」と「読み取る力」
先ほど触れたとおり、コミュニケーション能力における「伝える力」と「受け取る力」の両方が医療従事者にとって不可欠な能力であると伝えました。
しかし、患者とのコミュニケーションのなかでより重要になるのが「受け取る力」ではないかと考えます。
もし「受け取る力」が不足していると、患者からの症状の訴えを正確に理解することが難しくなるため、その分、疾患の特定が困難になる恐れがあります。
また、「受け取る力」よりも「伝える力」ばかりを重視していると、患者の訴えに耳を傾けない一方通行の診療になり、患者の精神的な不安が解消されず、医療機関からの患者離れが生じる恐れもあります。
「受け取る力」とは、コミュニケーションの4つの要素で言うところの「③聴く力」と「④読み取る力」です。
「聴く力」と「読み取る力」は、「傾聴スキル」とも言い換えることができそうです。
医療機関では、医師を始めとした医療従事者の傾聴スキルを養うことが、診療の質や患者サービスの向上につながると考えられます。
傾聴とは?
そもそも「傾聴」とはどのようなことを指すのでしょうか。
傾聴を英語で言うと「Active Listening」になり、積極的に話を聴くことを指します。そこには積極的な姿勢が含まれるため、日本では「積極的傾聴」と呼ばれるようにもなりました。
傾聴を簡単に説明すると、「相手の話を丁寧に真心を込めて聴く」ということになります。
つまり、自分の心を相手に傾けて、言葉の向こうにある相手の心情、価値観などをイメージしながら「心」で「聴く」ことを意味します。
来談者中心療法を提唱したアメリカの臨床心理学者カール・R・ロジャーズは、カウンセラーの基本的な対人態度として以下の「3つの条件」を示しました。
- ①受容
-
受容的態度。来談者という存在の全てに肯定的な態度を持っていることを示すこと。
- ②共感
-
共感的理解。来談者の感情を自分自身の中に再構成して実感を込めて理解すること。
- ③自己一致
-
①受容と②共感にうそがない状態。純粋性。
傾聴の場面では、相談を受ける者が来談者を大切にしようとする態度・姿勢こそが最も重要になります。
そして、来談者が「わたしのことを大切にしてくれている」と実感できるときに、前向きに考えることができるとされています。
参考:(株)東京リーガルマインド著「キャリアコンサルタント養成講座 テキスト2」
経営上難しいという現実的な事情も
医療機関において、「受け取る力」、「傾聴スキル」が特に重要であると前述しました。
ただ、そうは言うものの、医療従事者の皆さまの多くは、患者とコミュニケーションを十分に取る必要があることくらいわかっているよと、反論したくなる方も少なくないでしょう。
医療機関にとってみれば、そもそも患者数を増やしたいと思う一方で、予約枠の人数制限を守る必要もあります。全ての患者1人1人に充分時間をかけてなどいられないという経営上の現実的な事情もあることも理解できます。
患者1人1人に対する傾聴は、経営面からみても極めて難しい課題であると考えられます。
さらに、傾聴には医療従事者側にも相当の覚悟や忍耐を伴うことも忘れてはなりません。
精神科医でカウンセラー教育に長く携わる高橋和巳氏は、著書のなかで、話し手を楽にさせる聴き方を「傾聴」と呼び、「傾聴」には3つの要件
- 賛成して聴く
- 黙って聴く
- 世界を代表して聴く
があると伝えています。
さらに、長くカウンセリングに携わる高橋医師においてしても、傾聴の難しさや傾聴に向かう際の覚悟、忍耐が必要になると伝えています。
カウンセリングの最中、
「ずっと聴いていればどこかで賛成できなくなるし、口を挟みたくなります」
しかし、口を挟まず聴くことに徹することが重要
引用:高橋和巳著「精神科医が教える聴く技術」(ちくま新書)
医療従事者に対する相当の負担や経営上の制約があるなか、医療機関がスタッフの傾聴スキルを発揮させるために、どのような取り組みを考えればいいのか。次の項でみていきたいと思います。
なお、傾聴スキルは、政府が示す「社会人基礎力」12の能力要素のひとつに数えられています。医療従事者の社会人基礎力向上の方策に関して、以下の記事で詳しく解説していますので是非ご参考ください。

傾聴スキルを向上させるための4ステップ

それでは、医療機関がスタッフの傾聴スキル向上に向けた取組を考える場合、どのような点がポイントになるのでしょうか。
以下のとおり、医療機関で実践すべき傾聴スキル向上の4ステップを紹介したいと思います。
- ステップ❶:コミュニケーションの重要性について管理者層が共通認識を持つ
- ステップ❷:コミュニケーションの重要性を全スタッフに周知する
- ステップ❸:外部講師による全スタッフ対象の傾聴スキルアップ研修を行う
- ステップ❹:各部署が日々の朝礼等でスタッフへの動機付けを行う
以下、ステップ❶から順に解説していきます。
ステップ➊:コミュニケーションの重要性について管理者層が共通認識を持つ
まず、管理者層全員の意思統一が重要です。
つまり、患者との親密なコミュニケーションが、診療の質の維持・向上においても、集患の面においても、非常に重要な要素になることを、管理者会議などで十分議論し、そのうえで管理者層全員が共通認識を持つことからスタートします。
ステップ➋:コミュニケーションの重要性を全スタッフに周知
管理者層による共通認識が固まったら、次にスタッフへの周知を行います。
周知は院長など経営トップから行うことが重要です。患者とのコミュニケーションが以下の理由から重要であることを、経営トップから医師を含めた全スタッフにアナウンスします。
- 患者に対する診療の質を向上させる要因になること
- 患者に安心を与え、この先も患者から選んでもらえる医療機関になる要因になること
経営トップから全スタッフへのアナウンスは、最初の1回に限らず、可能な限り定期的に直接アナウンスする機会を設けることが大事です。
定期的に経営トップからスタッフ1人1人に啓蒙していくことができれば、さらにコミュニケーションの重要性に関する意識の定着が進んでいくと考えられます。
ステップ➌:外部講師による全スタッフ対象の傾聴スキルアップ研修を行う
スタッフへの周知が終了したら、次はスタッフに対する研修を行います。
日常の診療業務から患者に対する傾聴を行うためには、スタッフに相当のスキルアップやメンタル維持の能力が必要とされます。
スタッフに傾聴の重要性を正しく理解させ、傾聴スキルの向上を図っていくために、全スタッフ対象の研修を外部講師を招いて行います。
医師については、普段の診療業務から傾聴を意識して患者と接することはあまりないかも知れません。しかし、患者との関係性構築で最も重要な職種は医師になります。
傾聴スキルアップ研修は、医師が改めてコミュニケーションの重要性について気づきを得ることで、医師業務へのモチベーション向上や診療の質向上を図る貴重な機会になるかも知れません。
研修日時の設定や実施回数については、医師が全員参加できるように、特別な配慮が必要になるでしょう。
なお、傾聴スキル向上の具体的なノウハウについては、厚生労働省が運営する「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」にトレーニング方法が掲載されていますので、是非ご参考ください。
研修講師の選定については、傾聴スキルを得意とする専門家を外部講師として招聘するのが理想です。
内部人材を講師にあてることも考えられますが、外部講師の方が全スタッフが緊張感をもって受講に臨めるというメリットがあります。
また、傾聴スキル向上に対する管理者層の意識の高さがメッセージとしてスタッフに伝わるというメリットもあるため、外部人材の活用をお勧めします。
研修講師の候補としては、キャリアコンサルタントや社会保険労務士などが考えられます。
キャリアコンサルタントとはキャリア形成支援をする専門家で、傾聴を含む基本的なカウンセリング技法を習得しています。以下のリンク先からリサーチできますので、是非ご活用ください。
社会保険労務士とは人事・労務管理をサポートする専門家で、働きやすい職場づくりを支援します。以下のリンク先からリサーチできます。
なお、社会保険労務士の活用方法に関しては、以下の記事で詳しく取り上げていますので是非ご参考ください。

ステップ❹:各部署が日々の朝礼等でスタッフへの動機付けを行う
全スタッフに対する研修が終了したら、スタッフへの継続的な動機付けを行っていきます。
経営トップから全スタッフへの定期的なアナウンスに加え、各部署において朝礼などの日々の声掛けから、患者への傾聴の心掛けやコミュニケーションの重要性について啓蒙していくことが非常に重要です。
こうしたスタッフへの継続的な動機付けによって、スタッフ1人1人にまで患者とのコミュニケーションの重要性を浸透させることができれば、さらなる診療の質向上や、より患者に選ばれる医療機関になるための条件が満たせるかも知れません。
なお、スタッフへの動機付けの施策として1on1を取り入れる方法もあります。以下の記事で医療機関が1on1を取り入れる際のポイントなどについて解説していますので、併せてご参考ください。
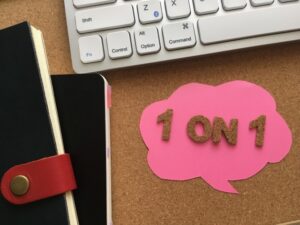
まとめ
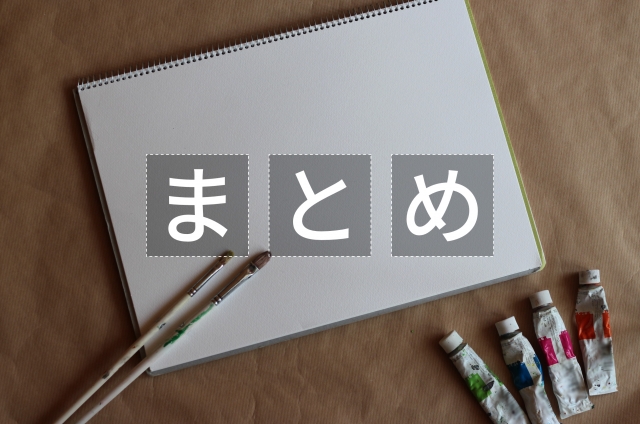
今回は、医療現場で必要とされるコミュニケーション能力と、特に重要となる傾聴スキル向上の取組について考えてきました。
最後に、なぜ医療現場でコミュニケーション能力が重要になるのか、その理由をまとめたいと思います。
- 理由1:患者は医療従事者とのコミュニケーションを求めている
- 理由2:患者からの評価はコミュニケーションで決まる
- 理由3:患者とのコミュニケーション不足は診療サービス低下を招く
先に紹介した精神科医・高橋和巳氏が示す「傾聴」の3つの要件は、
- 賛成して聴く
- 黙って聴く
- 世界を代表して聴く
でした。
この表現からもわかるとおり、傾聴はとても奥が深いものです。
患者との傾聴が大事だと言うのは簡単ですが、忙しい医療現場ではなかなか浸透させるのは難しいことだと思います。
しかし、スタッフのコミュニケーション能力や傾聴スキルを向上させることは、医療機関において患者の定着などの経営面だけに効果をもたらすわけではありません。
患者との親密なコミュニケーションは、患者の診療の質を上げるとともに、患者のヘルスリテラシーを向上させるきっかけにもなります。
患者のヘルスリテラシーが向上すれば、患者やその家族、またその周りの人たち、さらに地域住民のヘルスリテラシーが向上するきっかけにもなるでしょう。
そしてその結果、地域住民全体の健康寿命延伸のきっかけにもなるかも知れません。
地域のヘルスリテラシー向上のために医療機関がなすべき取組について、また、日本人全体のヘルスリテラシーが低い理由と向上策について、以下の2つの記事で紹介していますので、併せてお読みください。


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。








