「労働生産性」という言葉をよく耳にすると思います。
皆さまの医療機関でも、
- 「最近、職場の労働生産性が悪くなってきた気がする…」
- 「生産性を上げるにはどうしたらいいのか…」
と頭を悩ませている管理職の方も多いのではないでしょうか。
そもそも世界の国々のなかで、日本の労働生産性の低さが指摘されています。
なぜ、日本の労働生産性が低いのか?
今回は、日本の労働生産性の現状と、医療機関の労働生産性を高めるにはどのような考え方が必要なのか考えていきたいと思います。
日本の労働生産性の現状を探る
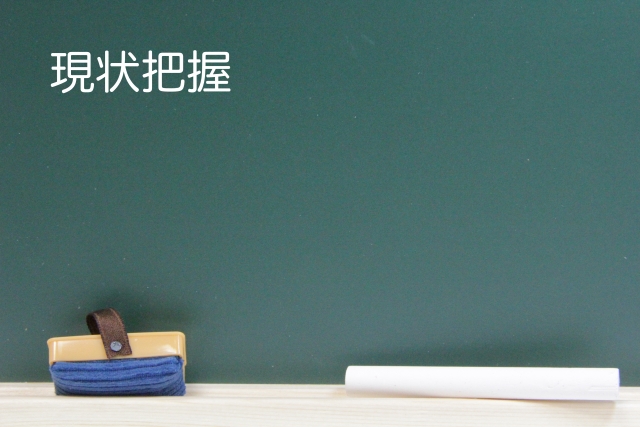
さっそく、労働生産性の基本を押さえつつ、日本の労働生産性の現状について確認していきたいと思います。
労働生産性とは
労働生産性とは、労働者がどれだけ効率的に成果を生み出したかを定量的に数値化したものです。
労働生産性は、以下の式により算出されます。
上記の計算式からわかるとおり、労働者レベルでの能力向上や効率改善、経営レベルでの効率改善等により、
- 「アウトプット(付加価値額)の増」
- 「インプット(労働者数×労働時間)の減」
を図ることで、労働生産性が向上する仕組みになります。
引用:日本生産性本部「日本の労働生産性の動向 2024 概要」
2024年日本の時間当たり労働生産性の概要
それでは、実際、日本の労働生産性は国際的にみてどの位置にあるのでしょうか。
公益財団法人 日本生産性本部がまとめている「労働生産性の国際比較 2025」を参考に、日本の労働生産性の概要について確認していきます。
2024年における時間当たり労働生産性の概要は、以下のとおりです。
- 日本の時間当たり労働生産性 60.1ドル(5,720円/購買力平価換算)
OECD加盟38カ国中28位 - 日本の1人当たり労働生産性 98,344ドル(935万円/購買力平価換算)
OECD加盟38カ国中29位(主要先進7か国中最下位) - 日本の1人当たり労働生産性は、主要先進国の中で最も生産性が低い英国の8割弱で、米国の54%に留まる
- 日本は実質経済成長率のマイナスも影響し、労働生産性上昇率(-0.7%/実質)がOECD加盟38カ国中32位となり、順位低下につながった
- 日本の前後の順位
| 26位 | ポーランド |
| 27位 | 韓国 |
| 28位 | ニュージーランド |
| 29位 | 日本 |
| 30位 | スロバキア |
| 31位 | エストニア |
| 32位 | ハンガリー |
時間当たり労働生産性:上位10カ国の変遷
さらに、国別にみた労働生産性の上位10位までの推移を以下の表にまとめました。
前掲の資料でも示したとおり、日本は2024年にOECD加盟38カ国中29位となっています。
近年の状況をみると日本は2000年には21位でしたが、それ以降は低下傾向が進み、現在は低水準に留まっています。
一方、2024年も首位はアイルランドでした。アイルランドは2000年にはトップ10圏外だったものの、近年急上昇しています。2010年に4位に入り、2020年には首位に躍り出て現在に至ります。
| 順位 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1位 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | アイルランド | アイルランド | アイルランド | アイルランド |
| 2位 | ノルウェー | ノルウェー | ルクセンブルク | ノルウェー | ノルウェー | ルクセンブルク |
| 3位 | ベルギー | 米国 | ベルギー | ルクセンブルク | ルクセンブルク | ノルウェー |
| 4位 | オランダ | アイルランド | ノルウェー | デンマーク | ベルギー | 米国 |
| 5位 | スウェーデン | ベルギー | デンマーク | ベルギー | デンマーク | スイス |
| 6位 | 米国 | デンマーク | フランス | スイス | スイス | ベルギー |
| 7位 | フランス | スウェーデン | オーストリア | スウェーデン | オーストリア | デンマーク |
| 8位 | スイス | オランダ | スウェーデン | オーストリア | 米国 | オランダ |
| 9位 | ドイツ | スイス | スイス | 米国 | オランダ | イタリア |
| 10位 | デンマーク | フランス | 米国 | アイスランド | ドイツ | オーストリア |
| 圏外 | 日本(21位) | 日本(20位) | 日本(27位) | 日本(30位) | 日本(29位) | 日本(29位) |
公益財団法人 日本生産性本部ホームページより引用
日本の労働生産性が低い理由
前掲の資料からも、日本の労働生産性は、国際的にみるとかなり低いことがわかりました。
一般的に、以下のような日本人の働き方の特徴が、労働生産性を低下させている原因となります。
- 「時間=価値」という評価慣習
-
効率を上げて早く帰る人よりも、遅くまで頑張っている人が評価される文化が根強く残る。
- DX・IT投資の遅れと「現場の職人芸」への依存
-
多くの業務が属人化しており、標準化やシステム化が進んでいない。ITによる「省力化」よりも「人手によるカバー」を優先しがち。
- 付加価値の低い「過剰サービス」
-
顧客サービスの水準は非常に高い一方、それが適切に価格に転嫁されていない。
- 労働市場の硬直性と年功序列
-
終身雇用・年功序列の慣習により、スキルに応じた適切な人材配置・労働移動がスムーズに行われていない。
- 投資対効果(ROI)を重視しないマネジメント
-
経営層が「生産性向上」を「コスト削減」と勘違いしているケースも多く見られる。
医療における労働生産性の厳しい現状

それではもう少し深堀りして、日本の産業界の中で医療・福祉分野の労働生産性がどのような状況になっているのか、確認していきます。
医療・福祉業界は労働生産性が低い
まず、日本の産業別における労働生産性の順位を確認していきます。
公益財団法人 日本生産性本部のホームページより、企業レベル生産性データベースの産業別データ(2022年度)を抽出した結果、以下のとおりとなりました。
| 順位 | 業種(大分類) | 労働生産性(千円) |
| 1位 | 金融業,保険業 | 16,877 |
| 2位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 16,845 |
| 3位 | 不動産業,物品賃貸業 | 15,184 |
| 4位 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 9,471 |
| 5位 | 宿泊業,飲食サービス業 | 9,153 |
| 6位 | サービス業(他に分類されないもの) | 8,805 |
| 7位 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 8,190 |
| 8位 | 卸売業,小売業 | 8,144 |
| 9位 | 情報通信業 | 7,999 |
| 10位 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 7,979 |
| 11位 | 医療,福祉 | 7,890 |
| 12位 | 製造業 | 7,624 |
| 13位 | 運輸業,郵便業 | 7,069 |
| 14位 | 複合サービス事業 | 6,045 |
| 15位 | 農業,林業 | 5,487 |
| 全産業 | 8,339 |
表のとおり、「医療・福祉」の労働生産性の順位は、分類された15業種のうち11位でした。
金額でみると、「医療・福祉」は7,890千円となり、1位の「金融業,保険業」の16,877千円に対して、半分以下の結果となっています。
11位という順位が示すとおり、全産業平均の8,339千円よりも5%以上低い結果となっています。
地域別:医療業界における労働生産性の年度推移
さらに日本の地域別にみた医療業界における労働生産性の年度推移について確認していきます。
前項と同じデータ元から、地域別に直近5年度分のデータを抽出のうえ下表にまとめました。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
| 北海道地方 | 5,599 | 6,227 | 5,235 | 6,153 | 6,514 |
| 東北地方 | 6,230 | 6,179 | 5,986 | 7,248 | 6,524 |
| 関東地方 | 9,286 | 8,956 | 8,143 | 9,153 | 8,405 |
| 中部地方 | 5,647 | 7,532 | 9,343 | 8,784 | 8,036 |
| 近畿地方 | 8,491 | 8,233 | 8,166 | 8,161 | 10,471 |
| 中国地方 | 6,676 | 4,458 | 7,089 | 6,222 | 5,672 |
| 四国地方 | 4,510 | 6,504 | 4,771 | 4,734 | 5,284 |
| 九州・沖縄地方 | 5,937 | 7,774 | 6,407 | 6,189 | 8,666 |
| 全国 | 7,423 | 7,627 | 7,404 | 7,786 | 7,890 |
上の表をみると、2022年度で最も労働生産性が高かった地域は、近畿地方の10,471千円となっています。2番目に高いのが九州・沖縄地方で8,666千円、3番目に関東地方8,405千円と続いています。
一方で、2022年度で最も労働生産性が低かった地域は、四国地方の5,284千円となり、最も高い近畿地方と比べるとその約半分の労働生産性ということになります。
四国地方は、前年度の2021年度と比較すると10%超の増加を示しているものの、直近3年間全ての年度において、全国で最低の労働生産性の数値となっていることがわかります。
なお、地域別の年度推移を全体的にみると、やはりコロナ禍の影響を直接受けた2020年度に労働生産性が下がっていることがわかると思います。
一般病院における労働生産性の年度推移
さらに、一般病院に絞って労働生産性の状況を確認していきます。
独立行政法人福祉医療機構がまとめている経営分析参考指標をもとに、一般病院における基礎的な経営指標と労働生産性を年度別にまとめました。
なお、同機構における労働生産性の計算式は以下のとおりです。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 施設数 | 1,319施設 | 1,281施設 | 1,347施設 | 1,446施設 | 1,433施設 |
| 病床数 | 174.0床 | 169.3床 | 167.1床 | 172.6床 | 170.8床 |
| 従業者数 | 310.0人 | 305.4人 | 300.0人 | 314.1人 | 318.0人 |
| 入院患者数/日 | 133.3人 | 129.4人 | 126.3人 | 135.1人 | 137.9人 |
| 外来患者数/日 | 230.8人 | 242.4人 | 234.0人 | 236.5人 | 237.1人 |
| 入院単価 (入院医業収益/患者1人1日) | 50,701円 | 51,560円 | 52,387円 | 53,475円 | 55,098円 |
| 外来単価 (外来医業収益/患者1人1日) | 14,359円 | 14,010円 | 14,516円 | 14,724円 | 14,718円 |
| 労働生産性 | 6,299千円 | 6,520千円 | 6,445千円 | 6,324千円 | 6,417千円 |
引用:独立行政法人福祉医療機構 経営分析参考指標 | WAM
・2021年度(令和3年度)決算分(ダイジェスト版)「2021年度(令和3年度)病院の経営状況」
・2022年度(令和4年度)決算分(ダイジェスト版)「2022年度(令和4年度)病院の経営状況」
・2023年度(令和5年度)決算分(ダイジェスト版)「2023年度(令和5年度)病院の経営状況」
・2024年度(令和6年度)決算分(ダイジェスト版)「2024年度(令和6年度)病院の経営状況」
より筆者まとめ
上記の表では、2024年度では労働生産性が6,417千円と前年度から上昇はしているものの、直近の5年間で見るとほぼ横ばいで推移していることがわかります。
コロナ禍のデータが含まれているため一概に説明できませんが、従業者数の増加と共に、人件費や材料費、経費などのコスト増により付加価値額が減少していることが、労働生産性低下の一つの要因になっているのかも知れません。
労働集約型産業という医療業の性質上、そもそも事業継続には人手がかかるということが前提にあります。他の業界に比べてDX化が遅れている側面もあり、アナログ作業が多く長時間労働が常態化している医療現場も少なくありません。
質の高い医療を維持しつつ、同時にスタッフの疲弊を防ぐには、次章から解説する業務効率化のための組織的な取り組みとともに、どの業務が本当に価値を生んでいるのかを見極める「選択と集中」の実践が重要になります。
以下の記事では、医療DX時代に取り組むべき院内リスキリング戦略に関して概要説明していますのでご参考ください。

業務改善の手がかりは、「5S」・「3S」・「ECRSの原則」

日本の労働生産性は、国際的にみてもかなり低く、中でも医療福祉分野が低いことがわかりました。
それでは、労働生産性を向上させるには、具体的に何をすればいいのでしょうか。
ここでは労働生産性向上のきっかけを考えるために、業務改善の前提となる基礎知識として、日本産業規格による生産管理用語を紹介したいと思います。
生産管理用語は主に製造業の生産現場で用いられるものですが、医療現場でも活用できると考えます。
「5S」:職場の管理の前提
「5S」とは、
「職場の管理の前提となる整理,整頓,清掃,清潔,しつけ(躾)について,日本語ローマ字表記で頭文字をとったもの」
と定義されています。
- 整理
必要な物と不必要な物に区別し、不必要な物を片付けること - 整頓
必要な物を使いやすい場所に準備しておくこと - 清掃
身の回りの物や職場を掃除して、いつでも使えるようにすること - 清潔
➊~➌を維持し、きれいでわかりやすい状態を保つこと - 躾(しつけ)
職場のルールや規律を必ず守り、習慣づけること
「3S」:⽣産の合理化の基本原則
「3S」とは、
「標準化,単純化,専門化の総称であり,企業活動を効率的に行うための考え方。」
と定義されています。
- 単純化(Simplification)
製品・材料・部品の整理、業務工程の見直しで、生産を単純化すること - 標準化(Standardization)
一定の基準に従い、材料や方法を統一して標準的にすること - 専門化(Specialization)
品種の限定や、作業の分担等で専業化を図ること
「ECRSの原則」:改善の原則
「ECRSの原則」とは、
「工程,作業,動作を対象とした分析に対する改善の指針として用いられる,E(eliminate:なくせないか),C(combine:一緒にできないか),R(rearrange:順序の変更はできないか),S(simplify:単純化できないか)による問いかけ。」
と定義されています。
- 排除(Eliminate)
なくせないか? - 結合(Combine)
一緒にできないか? - 交換(Rearrange)
順番を変えられないか? - 簡素化(Simplify)
簡単にできないか?
医療現場で実践したい生産性向上の手順を解説

それでは実際に、前項で紹介した「5S」、「3S」、「ECRSの原則」などを念頭に置いて、医療現場で実行できそうな労働生産性向上の手順について考えてみたいと思います。
生産性向上に向けた6つのステップ
医療現場の生産性向上を図るために考えられる手順をまとめると、以下のとおりとなります。
- STEP1:業務の棚卸、業務プロセスの「見える可」
- STEP2:業務プロセスの分析・改善
- STEP3:業務のDX化
- STEP4:ノンコア業務の外注化
- STEP5:労働環境、処遇の見直し・改善
- STEP6:スタッフの能力開発
以下、STEP1から順に解説します。
6つのステップ:その取組内容とは
業務の棚卸、業務プロセスの「見える可」
まずは、全ての業務の棚卸を行い可視化することから始めます。
業務プロセスの分析・改善
「見える可」したあとは、「3S」、「5S」、「ECRSの原則」等により、業務改善に向けた各業務プロセスの分析をします。
その分析結果から、コア業務とノンコア業務の仕分けを行い「選択と集中」を進めます。
業務のDX化
さらに、自動化が図れる業務はシステム導入を検討のうえDX化を進めます。今後AIがさらに医療の手助けになるかも知れません。
ノンコア業務の外注化
STEP2の段階で仕分けしたコア業務とノンコア業務のうち、ノンコア業務と判断した業務の外注化を進めていきます。
労働環境、処遇の見直し・改善
作業環境の整備やスタッフの処遇改善を図り、職場全体のモチベーション向上を図ります。
スタッフの能力開発
スタッフの研修制度を充実させ個々の能力を伸ばし、業務スピードや質を向上させます。
労働生産性向上がもたらすメリットとは
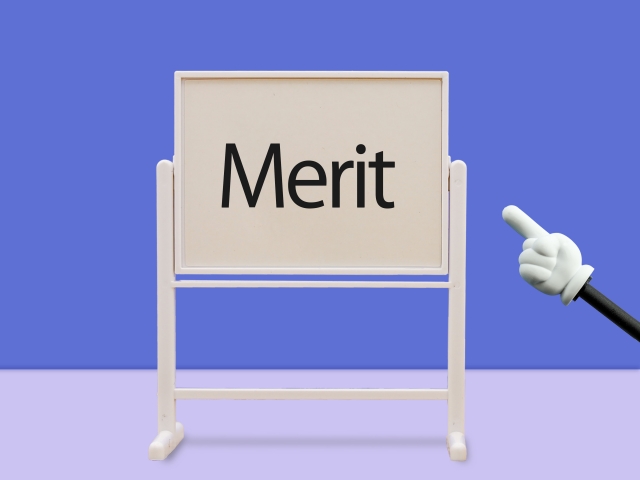
前述した生産性向上の手順に従い業務改善の取組を進めた場合、医療現場にどのようなメリットが得られるのでしょうか。
考えられるメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 収益の向上
- コスト削減
- ワークライフバランスの推進
以下、簡単に解説を加えます。
メリット➊:収益の向上
コア業務への経営資源の集中投下が可能になり、延患者数増、診療単価向上により収益性改善が期待できます。
メリット➋:コスト削減
ノンコア業務の外注化や一人当たりの時間外労働の減少、人員減を図ることで、人件費の削減が期待できます。
メリット➌:ワークライフバランスの推進
人手不足が解消することにより、スタッフの残業が減り、家庭で過ごせる時間が長くなります。有給休暇の取得も進み、心身ともに健康が増進し、院内全体の生産性向上が期待できます。
なお、以下の記事では看護師におけるストレスマネジメントの方法について解説していますので、併せてご参考ください。
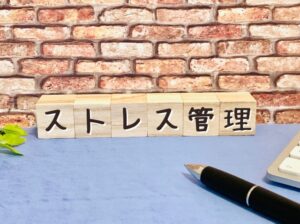
できることから始めていく

前項まで医療機関における労働生産性向上の手がかりや手順、また労働生産性向上によるメリットについて確認してきました。
それでは、実際に現場で業務改善に取り掛かろうと思ったときに、どのようなことを意識すべきなのでしょうか。
ここでは、意識すべきポイントについて考えていきたいと思います。
業務改善は小さな取組の積み重ね
医療業の運営にはとても複雑な要素が絡みますので、製造業と同じ手法で業務改善ができるほど簡単ではありません。
しかし、「5S」・「3S」・「ECRSの原則」などは、あらゆる現場で活用できる職場改善の活動となります。もちろん医療現場においても何らかのヒントになり得ると考えます。
業務改善で大事なことは、どんなに小さなことでもとにかくできることから始めてみることです。
医療現場ではこの「スモールステップ」、「スモールチェンジ」の考え方が有効になると考えます。
ハードルの低い身近なところから手を付ける方が、現場スタッフの負担は軽くなるため、改善の取り組み自体を受け入れてもらいやすくなるメリットがあります。さらにハードルが低い分、取り組みが継続しやすくなる効果もあります。
最初の小さな課題が達成できたら、次はもう少し難しい課題へと取り組みを進めていく。これが現場に改善活動を定着させる重要なポイントになります。
小さなことを一歩一歩着実に進めていくことで改善の軌道に乗っていきます。PDCAにより改善活動を繰り返した先には、効率的に業務が遂行される生産性の高い職場が実現されることでしょう。
病院機能評価や働き方改革がベースになる
病院機能評価受審の取組
病院の場合は、病院機能評価の受審が業務改善のきっかけになります。
病院機能評価の受審をクリアするためには、医療現場に様々な課題が突きつけられます。
これらの課題解決を進めていくには、まず身の回りの業務マニュアルの見直しや「5S」の徹底を図ることなど、できることから始めていくことが求められます。
働き方改革の取組
そして、病院機能評価受審と併せて重要な業務改善のきっかけになる取り組みに、職員の働き方改革があります。
2024年4月から医師の働き方改革が始まり、多くの医療機関が医師の負担軽減や労働時間短縮のための改善活動の必要に迫られています。
やはり、労働生産性向上のベースは働き方改革になるのかも知れません。
各医療機関では勤務時間管理の徹底やタスクシフト・タスクシェアを進めていると思いますが、これらの取り組みこそが、直接労働生産性向上につながり得る現場の改善活動の一つと言えるでしょう。
医師の働き方改革を推進するための対応策とそれに伴う宿日直許可取得・継続に向けたチェック項目に関しては、以下の2つの記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。
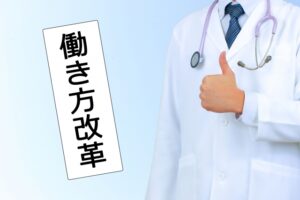

まとめ
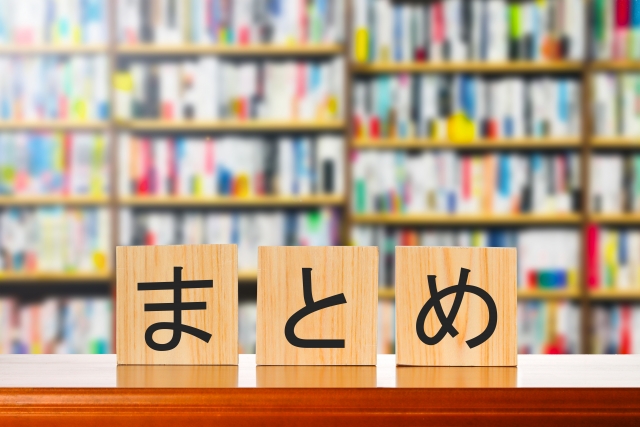
今回は、日本の労働生産性の現状と、医療機関が労働生産性を高めるために必要な考え方について解説しました。
最後に、本記事のポイントをまとめたいと思います。
- 業務改善の手がかりは、「5S」・「3S」・「ECRSの原則」から得られる
- 生産性向上に向けた6つのステップを検討する
- できることから始めていく「スモールステップ」、「スモールチェンジ」の意識が大事
地域医療の支え手である各医療機関が働き方改革を継続的に進め、生産性向上が実現できれば、スタッフのワークライフバランスの推進を図れます。
そうすれば、職場に対するスタッフの満足度が向上し、患者満足度も向上していくでしょう。
今回の記事が、個々の医療機関の生産性向上のきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。







