「人生100年時代」と言われるようになりました。
かつては定年年齢が55歳でしたが、今では、法令により70歳の定年が努力義務とされるようになりました。
この数年のあいだにも、私たちの働く期間が延び、組織や社会と関わる時間が長くなっています。そうした中では、私たち社会人に求められる基礎的な能力についても、見つめ直す必要がありそうです。
今回は、私たちが社会人として長く生きていくうえで必要となる基礎的能力にはどのようなものがあるのか。また、その能力を医療業務で活かすには、どのようなことを考えていく必要があるのか考えていきたいと思います。
「社会人基礎力」とは
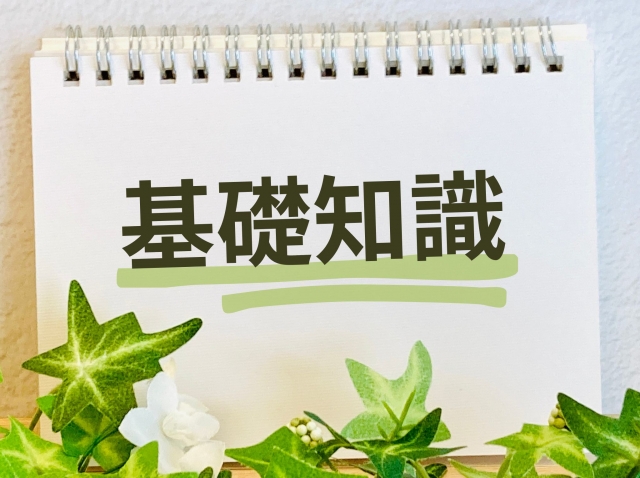
皆さんは、「社会人基礎力」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
実際に言葉自体聞いたことがあっても、具体的に説明できる人は意外に少ないと思います。
経済産業省は、「社会人基礎力」について以下のとおり定義しています。
社会人基礎力は、2006 年に経済産業省により提唱されました。
具体的には、以下の能力のことを言います。
| 1.前に踏み出す力(Action) 一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力 | ①主体性 |
| ②働きかけ力 | |
| ③実行力 | |
| 2.考え抜く力(Thinking) 疑問を持ち、考え抜く力 | ①課題発見力 |
| ②計画力 | |
| ③想像力 | |
| 3.チームで働く力(Teamwork) 多様な人々とともに、目標に向けて協力する力 | ①発信力 |
| ②傾聴力 | |
| ③柔軟性 | |
| ④状況把握力 | |
| ⑤規律性 | |
| ⑥ストレスコントロール力 |
上記のとおり、社会人基礎力は3つの能力に大別され、さらにその中で12 の能力要素に分けられます。
12の能力要素の半分にあたる6つの要素が「チームで働く力」に紐づけられています。このことからも、多様な人たちと協力しながら働いていく能力が重要視されていることがわかります。
ちなみに、「チームで働く力」のひとつにある「傾聴力」については、以下の記事で医療従事者にとっていかに大事であるか解説していますので、併せてご参考ください。

経済産業省ホームページより引用
「人生 100 年時代の社会人基礎力」とは
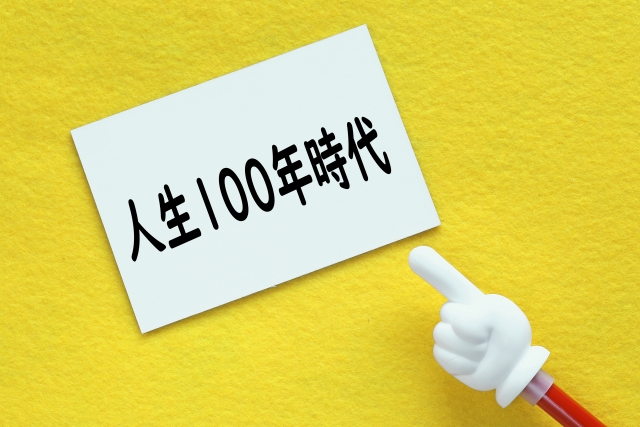
そもそも「人生100 年時代」とは
「社会人基礎力」(3つの能力/12 の能力要素)をベースにして、経済産業省が2018年に提唱した考え方に「人生 100 年時代の社会人基礎力」というものがあります。
その前に、そもそも「人生100年時代」とは何を意味しているのでしょうか。
厚生労働省はホームページでは、「人生100年時代構想会議 中間報告」から引用して以下の内容を紹介しています。
- ある海外の研究では2007年に日本で生まれた子供の半数が107歳より長く生きると推計
- 日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えている
- 100年という長い期間をより充実したものにするためには、幼児教育から小・中・高、大学教育、社会人の学び直しまで生涯にわたる学習が重要
- 人生100年時代に、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会づくりが重要課題
※「人生100年時代」に向けて|厚生労働省より引用し、筆者要約
上記から伺えるのは、長寿社会を迎えた日本にとって、若者から高齢者まで継続して活躍できる社会づくりの土台になる能力こそが「社会人基礎力」ということです。
厚生労働省は、人生100年時代における厚生労働省の対応として、以下の施策を掲げています。
- 幼児教育の無償化
- 待機児童の解消
- 介護人材の処遇改善
- リカレント教育
- 高齢者雇用の促進
上記の❹リカレント教育が、社会人基礎力養成につながる施策になると考えられます。
リカレント教育とは、学校教育から離れて社会に出た後も、必要なタイミングで再び教育を受け、仕事と教育を繰り返すことを言います。
このリカレント教育も、リスキリングと並んで近年よく聞くようになった言葉の一つです。以下の記事では、リカレント教育とリスキリングの違いに関しても解説していますので、是非ご参考ください。

また、❺の高齢者雇用の促進については、昨今の雇用環境から医療機関で検討すべき課題の一つと考えます。以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもご参考ください。

「人生 100 年時代の社会人基礎力」に必要な3つの視点
「人生 100 年時代の社会人基礎力」では、前述した「社会人基礎力」(3つの能力/12 の能力要素)の前提として、以下の3つの視点を取り入れることを提唱しています。
- 「学び(何を学ぶか)」
→「学び続けることを学ぶ」 - 「統合(どのように学ぶか)」
→「多様な体験・経験、能力、キャリアを組み合わせ、統合する」 - 「目的(どう活躍するか)」
→「自己実現や社会貢献に向けて行動する」
「社会人基礎力」(3つの能力/12 の能力要素)を発揮してキャリアを切りひらいていくためには、その前提として必要になる上記の3つの視点をバランスよく持つことが重要です。
「人生 100 年時代の社会人基礎力」提唱の背景にあるもの
2018年、経済産業省は「人生 100 年時代の社会人基礎力」を提唱したわけですが、この背景にあるのは、少子高齢化による働き手の維持のため、今後、私たち個人と組織・社会との関わりが、これまで以上に長くなるということが挙げられます。
人生100 年時代の働き方においては、一つの企業での終身雇用を前提としていません。
「人生 100 年時代の社会人基礎力」は新社会人として必要な基礎力でもあり、かつ自身のライフステージの各段階でキャリアチェンジをした際にも、必要な基礎力として持つべきものです。
医療従事者にとって社会人基礎力養成が必須条件である理由

ここまで、人生100年時代において社会人基礎力の養成がいかに重要であるかについて確認してきました。
それでは、今後、医療従事者や医療機関は、この社会人基礎力をどのように捉えていくべきなのでしょうか。
ここでは、医療従事者と医療機関それぞれが考えていくべきポイントについて押さえていきます。
社会人基礎力なしに医療における専門性の発揮は難しい
医療に従事する場合、いかに自分の専門性を高めていくかを課題にしている人も多いと思います。
しかし、国が示す「人生 100 年時代の社会人基礎力」は、医療において専門性を発揮するための、言わば土台になる能力と考えます。
つまり、医療従事者は専門知識を深める前に、社会人基礎力を習得する必要があると言えます。
新社会人のみならず、医療に携わる全ての人にとって、社会人基礎力として数えられる「3つの能力/12 の能力要素」の養成なしには、自らが専門性を高め、患者に対して質の高い医療を提供することは難しいと考えます。
以上のことを踏まえ、今後、医療従事者が自らの価値を高め、医療機関が成長していくためには、どのようなことを考えるべきなのか。次の項で解説します。
医療従事者が成長するために考えるべき3つのポイント
まず、医療従事者が成長するために考えるべきポイントを3点挙げたいと思います。
- 自己分析して自身の課題を明らかにする
- キャリア形成を思考する際の下地にする
- 社会人基礎力を継続的に養いつつ自己の専門性を深める
以下、詳しくみていきましょう。
医療従事者のポイント➊:自己分析して自身の課題を明らかにする
医療従事者に必要なポイントの一つ目は、自己分析による課題発見です。
つまり、「社会人基礎力」(3つの能力/12 の能力要素)と、その前提となる3つの視点(何を学ぶか、どのように学ぶか、どう活躍するか)について、現時点で自身がどの程度持ち合わせているかを分析することからスタートします。
自己分析により、現状における自身の課題を見つけ、日々の生活や業務をとおして改善していく手がかりとします。
医療従事者のポイント❷:キャリア形成を思考する際の下地にする
自己分析により課題発見できたら、その課題を自身のキャリア形成における課題として紐づけます。
自身のキャリア形成を考えるうえでは、「キャリアアンカー・キャリアデザイン・キャリアドリフト」の反復が、有意義な成長をもたらします。
そのうちの「キャリアアンカー」の段階で、自身の価値観や特性を内省する際に、現状の社会人基礎力のレベル感も認識しておくと、より自身のキャリア観に対する内省が深まるでしょう。
キャリアアンカー等の意義やキャリア形成における活用法については、以下の記事で詳しく解説していますので是非ご参考ください。

医療従事者のポイント❸:社会人基礎力を継続的に養いつつ自己の専門性を深める
自身のキャリア形成上の課題が認識できたら、不足する社会人基礎力を継続的に養いながら、自身の専門性を深めていくことがポイントになります。
社会人基礎力なしに自身の専門性の深化はないと認識することが重要です。継続的に社会人基礎力の養成に努めながら、専門性を深めていきます。
医療機関が成長するために考えるべき3つのポイント
次に、医療機関が成長するために考えるべきポイントを3点挙げたいと思います。
- 社会人基礎力養成を経営課題に位置付ける
- 社会人基礎力養成研修を計画的に実施する
- 研修の成果を定量把握しPDCAサイクルを回す
以下、解説していきます。
医療機関のポイント➊:社会人基礎力養成を経営課題に位置付ける
まず、医療機関の価値向上には、スタッフの価値向上が前提にあることを経営層の共通認識とします。
そして、自院の人材開発の基礎として、社会人基礎力養成を経営戦略上の重要課題と位置付けします。
医療機関のポイント➋:社会人基礎力養成研修を計画的に実施する
次に、全職種必須の研修として、社会人基礎力養成研修を年間の研修計画に組み入れ、定期開催します。
医師や看護師の他、コメディカルや事務職に至るまで、定期的に研修を行うことで、専門性発揮のための土台となる基礎力を全スタッフに植え付けます。
医療機関のポイント➌:研修の成果を定量把握しPDCAサイクルを回す
社会人基礎力養成研修は、実施して終了ではなく、研修の成果を定量的に把握する仕組みをつくることが重要になります。
この仕組みによって把握できた課題は、次期の研修計画に反映させPDCAサイクルを回していきます。
社会人基礎力は医療機関の持続的な価値向上の源泉に
前掲した取り組みを行うことで、医療従事者個々の社会人としての基礎力を継続的に向上させる機会ができるため、医療者としての専門性の発揮が期待できます。
社会人基礎力を土台にして、スタッフ一人一人が限りなく専門性を発揮することができれば、医療機関の持続的な価値向上が期待できます。
こうした考え方は「人的資本経営」につながります。医療機関における人的資本経営の重要性に関して、以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。

なお、公益社団法人東京都看護協会のホームページでは、「令和8年度新人看護職員のための社会人基礎力習得セミナー」の紹介を行っています。
これから医療機関で働く新人看護職員にとって有益なセミナーになるはずですので、自院の研修に組み入れるのも一つの方策だと考えます。簡単に概要をまとめておきます。
- 主催
公益社団法人東京都看護協会 - セミナー概要
新人看護職員が社会人基礎力を身につけ、臨床現場等で看護実践能力を発揮できることを目的に本セミナーを開催。ガイドラインに基づくプログラムに加え、他施設の看護職との交流を通じて成長を支援する、毎年好評のセミナー。 - 日程
令和8年4月9日~5月中旬まで(計10日間設定) - 場所
公益社団法人東京都看護協会会館 - 対象
令和8年度新規入職の新人看護職員で令和8年度入会検討中の方 - プログラム(予定)
【特別講演】看護職としての社会人基礎力
【講演】知っておきたい伝える力~NHKアナウンサーから学ぶ
【講義】看護職の倫理 他
まとめ
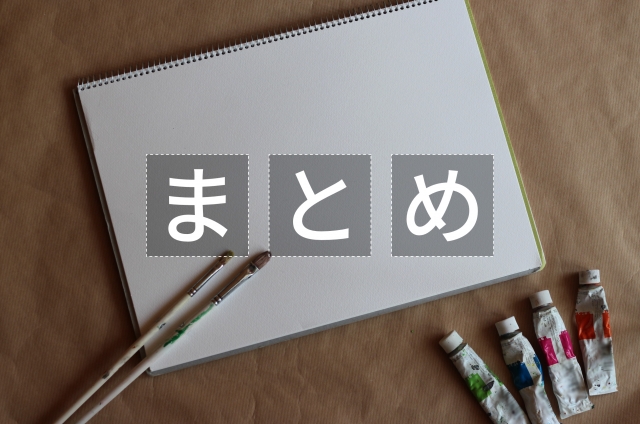
今回は、人生100年時代における社会人基礎力の重要性や、医療業務で活かすためのポイントについて考えてきました。
最後に、本記事の内容をまとめます。
- 社会や組織との関わりが長くなったいま、私たちには「人生 100 年時代の社会人基礎力」が必要
- 「社会人基礎力」とは、3つの能力(前に踏み出す力・考え抜く力・チームで働く力)と、12 の能力要素からなる
- 人生 100 年時代においては、「社会人基礎力」の前提として、「何を学び、どのように学び、どう活躍するか?」の3つの視点を、バランスよく持つことが大事
- 医療従事者が専門性を発揮するには、社会人基礎力養成がその前提となる
- 医療従事者が考えたいこと3つ。
社会人基礎力を、
①自己分析して課題発見
②キャリア形成上の思考の下地に
③社会人基礎力の継続的養成から自身の専門性の深化へ - 医療機関が考えたいこと3つ。
①社会人基礎力養成を経営課題に位置付け
②社会人基礎力養成研修を計画的に実施
③研修成果を定量把握しPDCAサイクル
スタッフに対する社会人基礎力養成研修について述べましたが、筆者が医療機関で勤務していた経験上、自施設で行う研修はほぼ病院運営上必須となる研修(医療安全・感染等)や、各自の業務で必要とされる専門的な研修が大半を占めていました。
専門性を高めることは、当然、医療の質向上にもつながり、人材確保を図るためにも医療機関にとっての重要課題と言えます。
しかし、専門性発揮を期待される医療従事者も、元をたどれば多くの社会人のうちのひとりです。社会人としての基礎的な能力が低ければ、組織への貢献や専門性の発揮も難しくなります。
医療機関においては、個の専門性を高めることと同時に、その基盤となる社会人基礎力養成についても見直す価値がありそうです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。







