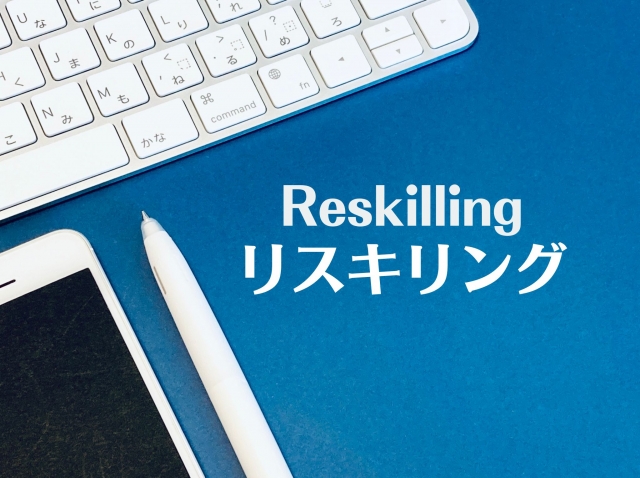ここ数年、「リスキリング」という言葉を聞くようになりました。
リスキリングとは、企業が、今後成長が見込まれるITなどの分野に人材を投じるため、必要な教育を社員に施し、その知識・スキルを活用していくことを意味します。
医療機関にとって、そこで働く医療従事者の質こそが、施設の質を決めると言っても過言ではありません。
医療DXが叫ばれるなか、人材確保という喫緊の課題を克服するためにも、多くの医療機関がリスキリングの考え方を活用する必要があると考えます。
今回は、医療機関におけるリスキリングの可能性や、実践する場合のポイントなどについて考えていきたいと思います。
「リスキリング」と「学び直し」の違い

リスキリングと聞くと、日本では「学び直し」と捉えられることが多いようですが、それとは解釈が異なります。
「学び直し」は、従業員本人が、自分の興味のある分野の学習をし直すことを意味しており、自己啓発に近い言葉として捉えられます。
一方で、リスキリングは、企業が従業員に必要な分野の知識・スキルを学ばせて、新しい業務へ転換させることまで含まれます。
もともと海外では、デジタル化の進展による労働市場の変革により、既存の職業の多くが失われるとの予測がありました。
ITやグリーン分野にその労働力を積極的に振り向けようとする政府や企業の動きが、リスキリングの考え方の始まりと言われています。
「リスキリング」と「リカレント教育」
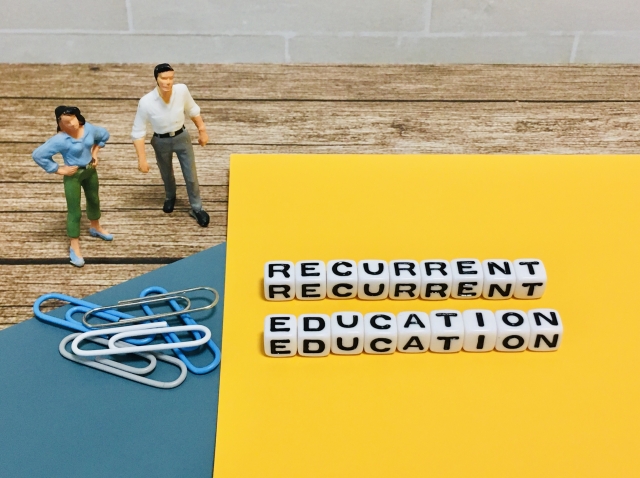
リスキリングと並んで、「リカレント教育」という言葉も近年耳にするようになりました。
リカレント教育とは、以下のことを言います。
そもそも「リカレント」には、「繰り返す」や「循環する」という意味があります。前述した「学び直し」や「スキルアップ」という言葉が、このリカレント教育に含まれると言えそうです。
「スキルアップ」という単語は、医療機関においてもよく聞かれる言葉です。
スキルアップとは、自分の業務に関する既存の技術や腕前をさらに向上させることを意味します。
医療機関で例えると、看護師が特定の分野の認定看護師の資格を取ることや、経理の事務員が簿記の資格を取得することなどが考えられます。
医事部門とシステム部門の外注化が招く弊害

常に人手不足を抱える医療業界にとっては、リスキリングの考え方を活用して、人材の流入を期待したいところです。
個別の医療機関で考えると、人件費を抑えるためにノンコア業務と判断した部門の外注化を進めた結果、ここにきて医療機関の経営を難しくする弊害を生んでしまったケースもあるようです。
その例として、医事部門やシステム部門の外注化があります。それぞれどのような弊害を生むのか、簡単に説明します。
- 医事部門の外注化
-
将来の医療機関のマーケティングに必要な、診療報酬上のノウハウを蓄積できない弊害を招きます。
- システム部門の外注化
-
将来の医療機関のマーケティングに必要な、情報的資源の加工・分析に関わるノウハウを蓄積できない弊害を招きます。
これら両部門におけるノウハウが蓄積できないことは、医療機関の経営戦略面で、将来に向けた競争力低下を招く要因となります。
医療DX時代に避けられないリスキリングによる内部人材活用

なぜ医事部門とシステム部門の外注化が、将来の競争力低下につながるのでしょうか?
それは、医療機関が「医療DXへの対応」という避けて通れない重要課題をクリアしなければならないからです。
「医療DXへの対応」でキープレイヤーになるのは、システム部門のスタッフであることは言うまでもありません。
システム部門のスタッフは、ITに関する専門知識と合わせ、医療に関する知識も兼ね備える必要があるなど、広範な知識やスキルが求められます。
完全外注からシステム部門の内製化を図るには、以下の3つのコストを払う必要があります。
- 広範な知識とスキルを持つIT人材を獲得するための経済的コスト
- 病院システム業務のオペレーションを習得させるまでの育成コスト
- 病院特有の組織文化に適合するまでの定着化コスト
経営資源が潤沢にとれない医療機関にとって、これらの多大なコストを一時期に払うのは、極めて難しいことだと考えます。
そのため、まずは、自院の業務フローや組織文化に慣れた内部人材の活用を検討することが重要です。
「医療DXへの対応」のために必要なIT人材確保と具体的なリスキリングの方策について、SSKセミナーで講師を担当しました。以下の記事で報告していますので是非ご覧ください。

医療機関が内製化を図る際に考えられる3つの選択肢

医療機関が医事部門やシステム部門の内製化を図るには、実際どうすればいいでしょうか。
ここでは、システム部門の内製化を例に、医療機関が考えられる選択肢として以下の3点を挙げたいと思います。
- 選択肢1:IT人材を外部から採用
- 選択肢2:派遣スタッフとしてIT人材を採用
- 選択肢3:院内の人材をリスキリングして配置転換
以下、それぞれ解説していきます。
選択肢1:IT人材を外部から採用
最初の選択肢は、IT人材を中途採用で外部から採用することです。
ここで問題になるのは、医療業界がIT業界に比べて、給与や待遇面で見劣りすることが挙げられます。
令和6年賃金構造基本統計調査によると、SE全体と全職種の平均年収を比較した場合、以下のような金額の開きがあることがわかります。
- SE全体(ソフトウェア作成者):約574万円
- 全職種:約527万円
参考:賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
上記のとおり、全職種と比べるとSEは年収で約50万円も高いことがわかります。
SEという職種自体が、比較的高めの給料設定になっていると言えそうですが、医療機関における院内SEとなると事情が異なります。
医療機関においては、高度な技能を要するシステム開発業務が少なくなります。このことからも、医療機関で雇用されるSEの給与はそこまで期待できず、一般的には400万円~500万円と言われています。
医療機関がIT人材を招へいする場合、病院事務職と同待遇で考えるのではなく、システム専門職としての待遇を用意しないと外部からの招聘が難しくなるでしょう。
選択肢2:派遣スタッフとしてIT人材を採用
2つ目の選択肢は、人材派遣の活用です。
つまり、IT人材を有する派遣会社から有期の派遣契約で人材を招き、既存の業務を引継ぎつつ、将来の完全内製化に向けてノウハウを蓄積していく方策です。
多くの医療機関にとって、この人材派遣活用の選択肢が、より現実的な方策になるのかも知れません。
しかし、人材派遣としてIT人材を招く場合でも、当然、システムに関する全てをその派遣職員に任せっ切りにすることはできません。労働者派遣契約においては、派遣先企業が派遣職員への指揮命令権を有することになるからです。
そのため、派遣職員を管理し指揮命令する総務部門等の正規職員にも、相当程度の業務内容の理解が必要になります。医療機関としては、派遣職員に対する指揮命令権を有する分、追加的な業務負荷が生じることも想定する必要があります。
最終的には、システム業務に適した正規職員を配置して知識やスキルを習得させなければならないため、人事計画はあらかじめ講じておく必要があります。
選択肢3:院内の人材をリスキリングして配置転換
最後の選択肢は、前述したように医療機関にいる既存の人材の活用です。
つまり、医療機関が既存の適任者に対して計画的にリスキリングを進め、完全内製化を図る方策です。
院内SEに向いている人材には、以下の5つの要素が求められます。
- 要素1:貢献意欲が高い人
- 要素2:柔軟でフットワークが軽い人
- 要素3:コミュニケーション能力が高い人
- 要素4:論理的に提案できる人
- 要素5:自ら学べる成長意欲が高い人
配置転換を進めるにあたっては、その後の補充の必要の有無などの検討もあるため、かなりの準備期間を設けるとともに、周到な計画を策定することが必須条件になります。
リスキリングの過程では、現場やスタッフ任せにするのではなく、医療機関のトップ層がPDCAサイクルを用いるなどして進捗管理を入念に行っていくことが重要です。
既存の人材を活用してシステム部門の内製化を進める手順については、次の項で解説します。
なお、院内SEの業務内容や必要となるスキル、また、病院事務職のキャリア形成の考え方に関して、以下の2つの記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。


医療機関がリスキリングを進める際の7つのステップ

ここでは、医療機関がリスキリングによる配置転換を進める際の手順について解説します。
例として、システム部門への配置転換を想定した7つのステップを順にみていきましょう。
- ステップ1:経営方針確立
- ステップ2:経営方針の共有
- ステップ3:配置候補者の人選
- ステップ4:配置候補者への説明と本人の同意
- ステップ5:リスキリング計画確定
- ステップ6:リスキリング開始
- ステップ7:配置転換、事後フォロー
経営方針確立
院長自身が、医療機関の方針として今後システム部門の強化に注力することを明確にします。
経営方針の共有
システム部門を強化する経営方針について、院長が全スタッフに発信し理解を得ます。
配置候補者の人選
既存の職員から、システム部門に配置する院内SEとして適任の候補者を人選します。
配置候補者への説明と本人の同意
人選した候補者へ、経営方針やリスキリングの必要性、手順などを丁寧に説明します。そして、本人の意見や要望も聞いたうえで同意を得ます。
リスキリング計画確定
候補者本人の意見や要望を含めて、本人と計画を策定し確定します。また、候補者本人の既存の業務への補充について、人事部門との検討を行います。
リスキリング開始
リスキリングに要する学習開始後も、本人任せにせず、医療機関側が随時進捗確認を行います。本人に業務上の負荷が見込まれる場合は、他部署からの応援を検討するなど、フォローは必ず行うようにします。
配置転換、事後フォロー
配置転換の実行に際しても、医療機関側が積極的に関与します。配置転換後も、業務負荷に関してヒアリングを行うなど、当分の間は随時フォローを行うようにします。
医療機関がリスキリングを進める際の7つの注意点

医療機関がリスキリングによるシステム部門への配置転換を進める際、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
ここでは、注意点として以下の7項目を考えていきます。
- 注意点1:モチベーションの維持に配慮
- 注意点2:随時進捗管理を行う
- 注意点3:現職務に対する支援の検討
- 注意点4:心理的安全性の確保
- 注意点5:周辺知識の補強のための経済的支援
- 注意点6:最終目標の再認識
- 注意点7:経済的インセンティブの付与
注意点1:モチベーションの維持に配慮
リスキリングにおける学習方法やスケジュールについては、配置候補者と相談のうえ決めていくことが原則になります。
しかし、なるべく候補者本人の意見を尊重してあげることで、本人のモチベーション維持を図ることが重要です。
医療従事者のモチベーション管理の重要性や、内発的動機付けの実践と離職防止策について、以下の2つの記事で詳しく解説しています。


注意点2:随時進捗管理を行う
学習が開始されても、全て候補者本人や当該部署任せにしてしまうと、計画遅れならまだしも計画倒れになる可能性があります。
そのため、あらかじめリスキリングに対する進捗管理の方法を決めておき、随時進捗を共有することが重要です。
注意点3:職務に対する支援の検討
本人やその上長と相談のうえ、本人の現職務への支援体制を検討する必要があります。
必要に応じて人員の確保をして、負担軽減を図っていくことが大事です。
注意点4:心理的安全性の確保
本人の周囲のスタッフにもリスキリングの目的を周知するなど、本人が学習に集中できるよう精神的な配慮をすることが大事です。
医療機関の運営のために勤務時間内にリスキリングを行っているという事実を周囲が理解していることで、本人は安心して学習が進められますし、そのことで学習効率が向上することも期待できます。
なお、医療現場における心理的安全性の確保策については、以下の記事でも詳しく解説しています。
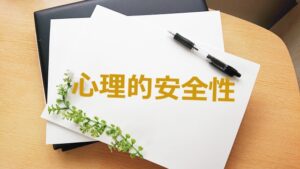
注意点5:周辺知識の補強のための経済的支援
学習を進めていく過程で、周辺知識を補強する必要がある場合、必要に応じて経済的支援を行うことも大事になります。
そのためにも、随時進捗管理を行っていくことが重要です。
注意点6:最終目標の再認識
リスキリングの最終目標が、学習した知識とスキルを、新たな部門で発揮することにあることを改めて認識し合うことが重要です。
リスキリングを終えたとしても、すぐに本人に業務上の結果を求めることはせず、継続的にフォローを行うことで能力を発揮する環境を整えるようにします。
注意点7:経済的インセンティブの付与
リスキリングを終えた後、さらなる専門性の獲得や維持のために、昇給昇格などの経済的なインセンティブの付与について積極的に検討する必要があります。
経済的インセンティブを付与することで、今回の候補者のモチベーション向上はもとより、今後の人材発掘につながる可能性もあるからです。
人材開発は「投資」と考える

リスキリングは、スタッフ本来の雇用されうる能力(エンプロイアビリティ)の向上や、将来に向けた選択肢を増やす源になります。
医療機関にとってリスキリングを図ることは、スタッフの転職の可能性を高めるなど、人材の流動化を促す方策に思えるかもしれません。
しかし、将来の人材強化を図っていくためにも、リスキリング等をとおした人材開発は、医療機関にとっての投資でもある、という認識を持つ必要があります。
このように、人材開発を投資と捉え、人材を組織運営上の「資本」と考える経営の在り方を人的資本経営と言います。
医療機関における人的資本経営の実践策に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので是非ご参考ください。

まとめ
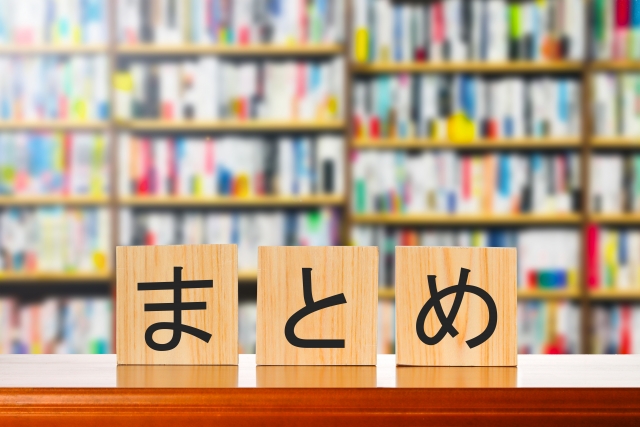
今回は、医療機関におけるリスキリングの可能性や、実践する場合のポイントなどについて解説してきました。
最後に、医療機関がリスキリングを考える際の注意点をまとめます。
- モチベーションの維持に配慮
- 随時進捗管理を行う
- 現職務に対する支援の検討
- 心理的安全性の確保
- 周辺知識の補強のための経済的支援
- 最終目標の再認識
- 経済的インセンティブの付与
政府は多額の予算を投じてリスキリングを推進していますが、人材開発には多くの時間を要します。
現状では、他の業界からの人材流入が待たれるところですが、まずは医療機関に今いる既存の人材をいかに活用していくかを考えることがポイントになります。
そのためには、「選択と集中」を再考して自院がどの分野に注力していくのかを見極めることが不可欠です。
そして、注力すべき分野に適時適切な人材を投入し、必要なノウハウを蓄積して、将来に向けた自院の競争優位性を獲得していくことが重要だと考えます。
なお、先ほど簡単に触れましたが、本記事のテーマをさらに深めた内容について、2025年9月にSSKセミナーでお伝えする機会をいただきました。
本テーマを含むセミナー実績の一例は、以下のページで紹介しています。
▶︎ 登壇実績(研修・セミナー)