組織の成長には、モチベーション管理が大事です。このモチベーション管理は、医療機関において特に重要な経営課題と言えるでしょう。
スタッフのモチベーションが低い職場では、診療の質が担保されず、患者サービスが低下し、医療安全上のリスクが高まります。
さらには、自院に対するスタッフの帰属意識が薄れ、離職者が後を絶たない不安定な職場になるリスクもあります。
「最近、スタッフからやる気や覇気が感じられない…」
そう感じている管理者の方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、医療従事者の効果的なモチベーション向上策となる内発的動機付けの実践方法について解説していきます。
内発的動機付けがモチベーション向上のカギ
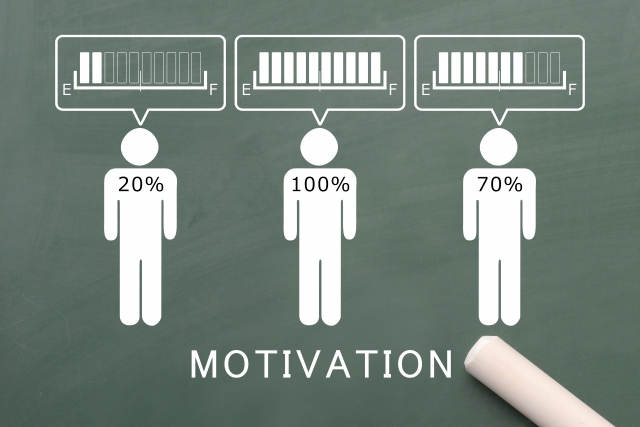
医療スタッフのモチベーション向上策で特に重要になるのは、「内発的動機付け」と言われています。
一般に、動機付けには
- 内発的動機付け
- 外発的動機付け
の2種類あると言われます。
内発的動機付けとは、仕事そのものの楽しさや有能感、満⾜感、⾃己決定の感覚など、自分の内から湧き上がるものを言います。
それに対し、外発的動機付けとは、報酬、昇進など、自分の外から与えられるものを言います。
医療従事者はもともと社会貢献意欲や、職業上の使命感、倫理感が高い人材が多い傾向にあると思います。
自律的な特性を持つ医療従事者のモチベーションをいかに効果的に向上させるかは、内発的動機付けがカギを握っていると考えます。
以下の記事では、なぜ医療機関においてモチベーション管理が重要なのか、その理由と方策について解説しています。併せてご参考ください。

「看護師の働き方に関する意識調査」から実態を探る
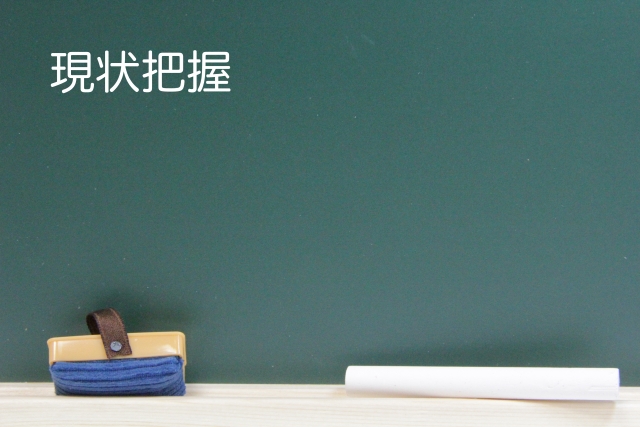
実際、医療従事者は自分の仕事に対して、どのような考えを持っているのでしょうか。
ここでは、株式会社エス・エム・エスが実施した「看護師の働き方に関する意識調査」(2021年11月~12月・「ナース人材バンク」、「ナース専科」を利用している看護職18,130名対象)を参考に、看護師の仕事に対する意識について見ていきます。
Q1:現就業先に対する満足度
Q1では、現就業先に「満足」と感じている看護師の割合が約6割(11.8%+49.2%)、「不満」を感じている割合が約4割(27.3%+11.7%)いることが確認できます。
- 「満足」11.8%
- 「まあ満足」49.2%
- 「やや不満」27.3%
- 「不満」11.7%
Q2:項目別の満足・不満足度
Q2では、看護師が現就業先に感じている満足要因が「患者や同僚との人間関係」に関するもの、不満足要因が「マネジメントや処遇」に関するものであることが確認できます。
満足を感じる点
- 1位「患者との関係」(81.6%)
- 1位「同僚との関係」(81.6%)
- 3位「休日・休暇の希望考慮」(74.5%)
- 4位「やりがい」(66.7%)
- 5位「配属先の希望考慮」(65.6%)
不満を感じる点
- 1位「適切な人員配置」(67.7%)
- 2位「指導方法のバラつき」(64.9%)
- 3位「管理職のマネジメント」(62.9%)
- 4位「企業・施設の方針」(61.4%)
- 5位「各種手当の充実」(60.8%)
Q3:現職を選んだポイント
Q3では、「処遇や立地面」を重視して就業先を選んだ看護師が相対的に多いことが確認できます。
- 1位「勤務時間・体制」58.3%
- 2位「職場へのアクセス」54.5%
- 3位「給与」43.3%
Q4:前職の退職理由
Q4では、看護師の前職の離職理由が、「人間関係、マネジメント、処遇」に関することだったことが確認できます。
- 1位「人間関係への不満」31.0%
- 2位「仕事内容への不満」24.8%
- 3位「管理職のマネジメントへの不満」20.3%
Q5:今後のキャリアの志向
Q5では、看護師のキャリア形成上、現職で継続雇用を希望している人が67.5%と7割近くもいることが確認できます。
- 1位「長く安定的に働きたい」67.5%
- 2位「明確な意向・希望は無い」24.2%
- 3位「他の医療機関での勤務経験も積みたい」14.3%
ハーズバーグの二要因理論からモチベーション向上策を考える

次に、医療従事者のモチベーション向上策を考えるヒントとして、アメリカの心理学者・ハーズバーグの「二要因理論」について解説します。
ハーズバーグは、仕事に対する満足、不満足の要因は別々にあり、
- 衛生要因
- 動機付け要因
の2つに別れると提唱しました。
1.衛生要因とは
衛生要因は、「不満足要因」とも言われます。
希望が満たされないと不満が強いですが、仮に希望を満たしていたとしても特段幸せを感じない、という考え方です。
例えば、スタッフは組織に対する貢献に見合う分の給料がもらえない場合、不満を感じているため衛生要因が満たされることはありません。
しかし、仮に組織への貢献どおりに給料をもらったとしても、当然の報いとして特別幸せを感じることはありません。
衛生要因の例をいくつか紹介します。
- 経営理念
- 上司との関係
- 給与などの処遇
- 対人関係
- 作業環境
2.動機付け要因とは
動機付け要因は、「満足要因」とも言われます。
特段それがなくてもすぐに不満を感じるわけではないですが、希望が満たされると幸せを感じる、という考え方です。
例えば、人のお世話が好きで看護師をしているスタッフは、仕事ぶりに対する上司や患者からの評価がなくても不満は感じません。
しかし、上司から仕事に対する高い評価をもらえたり、患者から日頃の感謝の声をもらえると、その分満足感を得られモチベーションが向上します。
動機付け要因の例をいくつか紹介します。
- 仕事の達成
- 承認
- 仕事そのものへの興味
- 仕事の責任・権限
医療従事者に対するモチベーション向上策に必要な2つの条件
前掲した看護師のアンケート結果から推察すると、医療従事者に対するモチベーション向上策には、以下の2点を満たすことが重要です。
- 衛生要因を(普通に)満たしつつ
- 動機付け要因を重視して、限りなく改善を施していく
❶「衛生要因を(普通に)満たしつつ」とは、先ほどの例で言うと、
組織の貢献に見合う給料は当然に支給し続ける、
ということです。
❷「動機付け要因を重視」とは、先ほどの例で言うと、
人のお世話が好きで看護師をしているスタッフには、組織として継続的に上司からの評価や患者の声をフィードバックする機会をつくり、モチベーションを向上させる、
ということです。
医療従事者に対する具体的なモチベーション向上策

それでは、医療従事者のモチベーションを向上させるためには、具体的にどうすればいいのでしょうか。
- 衛生要因
- 動機付け要因
それぞれ分けて考えていきたいと思います。
1.衛生要因に対するモチベーション向上策
まず、衛生要因の対応策について考えていきます。
①上司との対話の機会を増やし、信頼関係を向上させる
先ほど紹介した「看護師の働き方に関する意識調査」では、現職への不満要因が、
- 「適切な人員配置」
- 「管理職のマネジメント」
という回答が多くありました。
また、前職の退職理由では、
- 「管理職のマネジメント」
- 「仕事内容への不満」
という回答もありました。
つまり、上司は定期面談以外でも、「1on1」や日々の声掛けでスタッフとの対話の機会を増やし、本人の想いを汲み上げる施策が重要になると考えます。
コミュニケーションを高めるための1on1導入策や活用方法については、以下の記事で解説しています。併せてご参考ください。
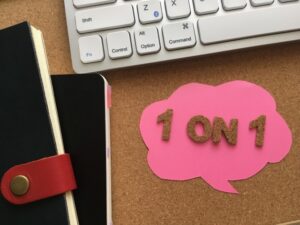
②院内イベントを継続的に行い、スタッフ間の人間関係構築を促す
前掲のアンケート結果で、現職への不満要因が、
- 「管理職のマネジメント」
- 「指導方法のバラツキ」
という回答が多くありました。
また、前職の退職理由では、
- 「人間関係への不満」
- 「管理職のマネジメント」
という回答もありました。
つまり、継続的なイベントをとおしてスタッフ同士の懇親を深め、組織へのつながりを感じてもらうことが離職防止に重要だと考えます。
コロナ禍の流れで院内イベントが減ってしまったのなら、まずは忘年会や暑気払い、さらには旅行やスポーツイベントの復活をとおして職員間の親睦を深め、良好な人間関係の構築を心掛けることが大事です。
なお、院内イベント実施にはスタッフの心理的安全性を高める効果もあります。以下の記事では医療機関におけるリスク管理の土台となる心理的安全性の確保策について詳しく解説していますので、是非ご参考ください。
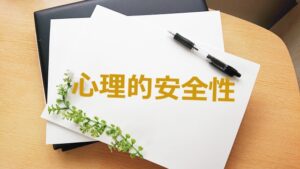
③給与等の処遇や勤務体制を改善し、福利厚生を充実させる
前掲のアンケート結果で、現職への不満要因が、
- 「各種手当の充実」
という回答が多くありました。
また、現職を就業先に選んだポイントとして、
- 「給与」
を挙げています。
つまり、給与の多い・少ないが転職のきっかけにもなり得るため、職務上不可避な危険手当や専門的スキルに対する手当の規定がない場合は改善が必要です。
2.動機付け要因に対するモチベーション向上策
次に、動機付け要因の対応策について考えていきます。
①職場の理念や価値観と、スタッフ個人の目標を同期させる
看護職のアンケート結果で、現職への満足要因が、
- 「患者との関係」
- 「やりがい」
という回答が多くありました。
つまり、組織の価値観や規範に「患者第一」を掲げることで、スタッフの個人目標にも紐づけて目標管理を行うことが個々のモチベーション管理に重要だと考えます。
②院内表彰を継続的に実施し、承認欲求を満たす
上記同様、現職への満足要因は、
- 「患者との関係」
- 「やりがい」
となります。
つまり、表彰制度を取入れ、スタッフの日々の業務を評価し、継続的に達成感を感じてもらう機会を設けることが仕事へのやりがいにつながると考えます。
③積極的に権限移譲を行い、職務充実を図る
上記同様、現職への満足要因は、
- 「患者との関係」
- 「やりがい」
となります。
つまり、上司は積極的に権限委譲を行い、これまでの業務以上の権限と責任を付与することで、日常業務に対するスタッフのやりがいを与えていくことが大事です。
医療従事者の働きがいを高める方策について、以下の記事で解説しています。是非ご参考ください。

「組織の価値観や規範の共有・浸透」が取組の前提
上記のモチベーション向上策を実践する際の注意点は、あくまでも以下のことが取組の前提にあるということです。
「患者第一」という組織の価値観や規範の共有と浸透がスタッフにきちんとなされている
医療機関は、スタッフの大半が国家資格者が占める多職種の専門家集団です。
医療従事者の最大の関心事は、
「患者を治療すること」です。
経営については恐らく二の次になるでしょう。
医療従事者は、そもそも経営層とは業務に向き合う視点が異なりますので、いかに継続的に動機付けを行っていくかが重要になります。
まとめ
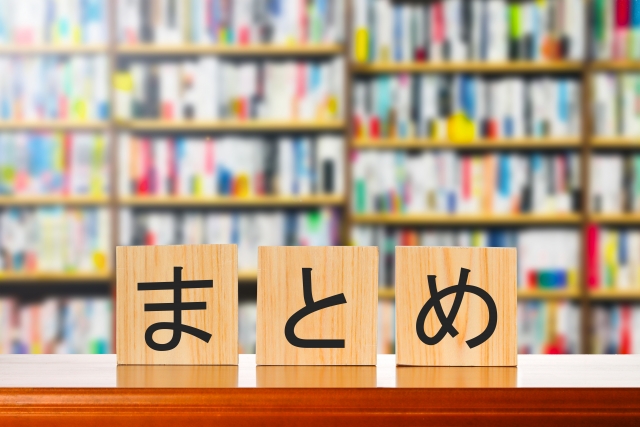
今回は、医療従事者に対する内発的動機付けの実践方法について考えてきました。
最後に、医療従事者に対する具体的なモチベーション向上策をまとめます。
衛生要因に対するモチベーション向上策
- 上司との対話の機会を増やし、信頼関係を向上させる
- 院内イベントを継続的に行い、スタッフ間の人間関係構築を促す
- 給与等の処遇や勤務体制を改善し、福利厚生を充実させる
動機付け要因に対するモチベーション向上策
- 職場の理念や価値観と、スタッフ個人の目標を同期させる
- 院内表彰を継続的に実施し、承認欲求を満たす
- 積極的に権限移譲を行い、職務充実を図る
医療機関が抱える最大の難題は、組織の大半を占める国家資格者の意思統一をいかに図っていくかにあると考えます。
モチベーション向上策の前提として、医療機関では、まず組織の価値観や規範を全スタッフに共有し、浸透させることが重要です。
それができれば、医療者はさらに、患者のためにモチベーションを上げて業務に注力していけるのではないでしょうか。
今回の記事が、医療機関の離職率低下や人材確保、安定的な組織づくりに貢献できれば何よりです。








