いま社会全体が、人材確保に奔走しています。その背景には、少子高齢化や産業構造の変化、コロナ禍をとおした価値観や職業観の多様化があります。
そのなかで、政府は2020年9月に、通称「人材版伊藤レポート」を発表し、「人的資本経営」という考え方を示しました。
労働集約型産業と言える医療機関においては、そこで働く人材の質こそが、施設の質を決めると言っても過言ではありません。
多くの医療機関にとって、この「人的資本経営」という考え方を取り入れることで、喫緊の課題とも言える人材確保の道筋が見えてくるかも知れません。
今回は、人的資本経営の考え方や、医療機関が実践する場合のポイントについて解説していきます。
人的資本経営の概念を示す「人材版伊藤レポート」を紐解く

人的資本経営とは?
そもそも人的資本経営とはどのような考え方を指すのでしょうか。
人的資本経営とは、組織における人材を、管理する対象としての「資源」という従来の考え方ではなく、価値を創造する投資の対象となる「資本」と捉え、人材の価値を最大限に引き上げることで、中長期的に企業価値を向上させていく経営のあり方のことを言います。
「人材版伊藤レポート」とは?
2020年9月に発表された通称「人材版伊藤レポート」は、正式名称を「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書」と言います。
この研究会の座長を務めた、一橋大学CFO教育研究センター長・伊藤邦雄氏にちなんで「人材版伊藤レポート」と呼ばれ、発表以降は国内企業が、その理念を自社に取り入れようと必死になっています。
経済産業省ホームページより引用
「人材版伊藤レポート」のポイント
ここでは、「人材版伊藤レポート」のポイントについて確認していきます。
- 前述の研究会座長である一橋大学CFO教育研究センター長・伊藤邦雄氏により、通称「人材版伊藤レポ ート」が取りまとめられる。
- 組織における人材を、管理する対象としての「資源」という考え方から、価値を創造する投資の対象となる「資本」と捉え、人材の価値を最大限に引き上げることで、中長期的に企業価値を向上させていく経営のあり方を示した。
- その背景には、少子高齢化や産業構造の変化、コロナ禍による企業・個人を取り巻く環境の変化により、個人の生活観や職業観の変化がある。企業はこれに対応する必要がある。
- 人的資本経営の理念となる6つの「変革の方向性」を明示した。
- 人材戦略には「3つの視点」と「5つの共通要素」が必要であるとした(3P・5Fモデル)
「人材版伊藤レポート」では、急激な環境変化により、企業は多くの課題を抱えているものの、それは人材面の課題にもつながるため、迅速に対応する必要があること、また、経営理念にまで立ち返って、持続的な価値の向上につながる人材戦略に変革しなければならないと説明しています。
人的資本経営における「変革の方向性」とは?
この伊藤レポートでは、人的資本経営における「変革の方向性」を下表のとおり明確に示しています。
- ①人材マネジメントの目的
-
「人的資源・管理」→「人的資本・価値創造」
人材は「コスト」であり、管理する対象と捉えていたが、価値を生む「投資」と考える。
- ②アクション
-
「人事」→「人材戦略」
人事制度の運用管理に留まるのではなく、経営戦略から落とし込んだ人事戦略を策定し、持続的な企業価値向上を目指す。
- ③イニシアティブ
-
「人事部」→「経営陣・取締役会」
人事部門任せにしていたのを、経営陣の主導で経営戦略と連動させた人事戦略を策定し、取締役会でチェックする。
- ④ベクトル・方向性
-
「内向き」→「積極対話」
囲い込み型人事による内向き志向から、投資家や従業員と対話や発信をしていく。
- ⑤個と組織の関係性
-
「相互依存」→「個の自律・活性化」
硬直的文化による相互依存関係から、ともに成長できる活性化した組織にする。
- ⑥雇用コミュニティ
-
「囲い込み型」→「選び、選ばれる関係」
終身雇用、年功序列の囲い込み型の関係から、互いが選び合う多様でオープンな関係になる。
人材戦略の「3つの視点」と「5つの共通要素」とは?
伊藤レポートには、以下のとおり人材戦略を進めるうえでの「3つの視点」と「5つの共通要素」(3P・5Fモデル)が示されています。
3つの視点(Perspectives)
| ①経営戦略と人事戦略の連動 | これまでは、人事部門における人事制度の運用が中心となり、経営戦略との紐づけがなされなかった。自社に適した人事戦略を策定するためにも、経営戦略と連動した具体的戦略を考えていく必要がある。 |
| ②As is-To beギャップの定量把握 | 「現在の姿」と「目指すべき将来の姿」とのギャップを定量的に把握し、PDCAサイクルで随時見直ししていく必要がある。 |
| ③企業文化への定着 | 兼業・副業やリモートワーク等の多様な働き方を含め、人材戦略の実行プロセスをとおした、企業文化へ定着させる取り組みをしていく必要がある。 |
5つの共通要素(CommonFactors)
| ①動的な人材ポートフォリオ | 適材適所の観点から、経営戦略のための質と量、両面での人材の充足や最適化を図る必要がある。 |
| ②知・経験のダイバシティ&インクルージョン | 性別や年齢、国籍などの属性に加え、他業界における専門性や経験を取り込む必要がある。 |
| ③リスキル・学び直し | 急激な環境変化や個人の多様化へ対応するため、専門性の向上や、個人の自律的キャリアの構築を支援していく必要がある。 |
| ④従業員エンゲージメント | 経営戦略実現のため、従業員が働きがいを感じる環境を整備する必要がある。 |
| ⑤時間や場所にとらわれない働き方 | いつでも、どこでも、安心して働ける環境整備を平時から行う必要がある。 |
医療機関で人的資本経営を実践する方法とは?

医療機関においては、2年に1回訪れる診療報酬改定や、本格的に始まる地域医療構想などの対応があるため、中長期を見越した人材戦略には難しい面がつきまといます。
しかし、将来の成長に向けて優秀な人材を確保し、経営の安定化を図るためには、人的資本経営の考え方を医療機関にも取り入れるべきだと考えます。
医療機関が考えるべき人的資本経営実践の3つのポイント
これまでみてきたとおり、人材版伊藤レポートは、あくまでも企業向けの指針です。
もし医療機関で人的資本経営を実践する場合、以下の意識を持つことが重要です。
人的資本経営の実践ポイント
- 「できること」と「できないこと」を取捨選択する
- 「できること」のなかで優先順位をつける
- 優先順位の上位で、手の付けられそうな項目から着手していく
これらのポイントを踏まえた実践の流れについては、後ほど詳しく解説します。
「変革の方向性」の共通認識から始める
まず、医療機関が「できること」としては、前述した人的資本経営における「変革の方向性」を自院に当てはめ、経営層で自院が進める変革の方向性の共通認識を持つことです。
医療機関の運営上、「変革の方向性」の考え方のポイントを以下のとおり挙げたいと思います。
- ①人材マネジメントの目的
-
「人的資源・管理」→「人的資本・価値創造」
医療スタッフは、コストと見なして管理する存在ではなく、チーム医療にシナジー効果を与えて、自院に価値を創造する「人財」と考える。
- ②アクション
-
「人事」→「人材戦略」
職種ごとに人材確保策を講じるのではなく、まず中長期的な医療機関全体の経営戦略を立て、それに紐づいた人事戦略を策定する。
- ③イニシアティブ
-
「人事部」→「経営陣・取締役会」
人事部門や各職種の部門長任せの人材確保策ではなく、経営層が策定した経営戦略から落とし込まれた人事戦略を基に、人材確保を行い、随時経営層がチェックを行う。
- ④ベクトル・方向性
-
「内向き」→「積極対話」
経営層のみの会議とは別に、経営層から医療スタッフへ直接アナウンスする機会を定期的に設け、経営方針を含めた対話の機会を設ける。
- ⑤個と組織の関係性
-
「相互依存」→「個の自律・活性化」
従来からのルールや規範、人間関係を重視した硬直的文化による相互依存関係ではなく、医療機関はスタッフに学びの機会を与えスタッフは自律的に学びを深めて組織に貢献する、ともに成長し合う活性化した組織を目指す。
- ⑥雇用コミュニティ
-
「囲い込み型」→「選び、選ばれる関係」
終身雇用、年功序列的な旧来の雇用から、積極的に外部人財を取り入れ能力に応じた客観的な評価も行い、多様性を認めるオープンな組織にして互いが選ばれる関係になる。
なお、医療機関の人事制度を考えるうえで終身雇用と年功序列のメリットとリスクを押さえておくことは極めて重要です。以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

医療機関で人材戦略を考える際の3つのポイント
「変革の方向性」の共通認識をもつことができたら、次に人材戦略の策定にあたります。
上記の実践ポイント1~3を踏まえて、実際に医療機関が人材戦略を策定する際のシミュレーションをしてみます。
ポイント1:「できること」と「できないこと」を取捨選択する
まず、「3つの視点」と「5つの共通要素」、それぞれの取捨選択(「できる」or「できない」)からスタートしていきます。
- 視点① 経営戦略と人事戦略の連動
→できる。
病院理念に紐づいた経営戦略を策定し、それに連動させる人事戦略を練っていく。 - 視点② As is(現在の姿)-To be(目指すべき姿)ギャップの定量把握
→できる。
病院理念の浸透度などについてアンケート調査を行う。客観性を保つため業者への依頼も検討。 - 視点③ 企業文化への定着
→できる。
院長や経営層からスタッフに向けたアナウンスや、対話の機会を定期的に設ける。
- 要素① 動的な人材ポートフォリオ
→すぐにはできない。
人材戦略上の課題とし、可及的速やかに質と量の両面でスタッフを充足させ、人材ポートフォリオの最適化を図る。 - 要素② 知・経験のダイバシティ&インクルージョン
→すぐにはできない。
人材戦略上の課題とし、オープンな文化の土壌を地道に育み、専門性をもった外部人材の獲得を目指す。 - 要素③ リスキル・学び直し
→できる。
計画的にスタッフへの教育の機会を与え、学んだ知識やスキルを業務に活用できる配置の検討も行う。スタッフが自律的に学びを深める風土づくりも併せて行う。 - 要素④ 従業員エンゲージメント
→できる。
病院理念や経営方針について、院長から直接スタッフに語りかける。目標管理制度や「1on1」を取り入れ、自院への愛着や貢献意欲を促す。 - 要素⑤ 時間や場所にとらわれない働き方
→できない。
医療サービスの提供上、時間と場所の限定は必要。
ポイント2:「できること」のなかで優先順位をつける
次に、上記で「できる」と判断した視点や要素のなかで、優先順位をつけていきます。
- 優先順位1
視点② As is(現在の姿)-To be(目指すべき姿)ギャップの定量把握
【例】職員アンケートなど
↓
- 優先順位2
視点① 経営戦略と人事戦略の連動
【例】病院理念に紐づく経営戦略策定と人事戦略の連動
↓
- 優先順位3
視点③ 企業文化への定着
【例】定期的な経営層との対話の機会など
↓
- 優先順位4
要素④ 従業員エンゲージメント
【例】院長からの語りかけ、1on1など
↓
- 優先順位5
要素③ リスキル・学び直し
【例】計画的な教育機会、リスキリングの促進など
ポイント3:優先順位の上位で、手の付けられそうな項目から着手していく
最後に、優先順位の上位の項目を眺めてみて、手の付けられそうな項目から順次着手していきます。
何事も、現状と課題のギャップを把握することから始める必要があります。
「優先順位1」として掲げた、「視点②As is(現在の姿)-To be(目指すべき姿)ギャップの定量把握」の施策としては、『病院理念等に関するスタッフへのアンケート調査』が考えられます。
課題が浮き彫りになったら、次に「視点① 経営戦略と人事戦略の連動」に取り掛かる、という流れで進めていきます。
なお、上記で取り上げた人材戦略上ポイントになるリスキリングによる人材開発や1on1によるコミュニケーション活性化の具体策については、以下の2つの記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。

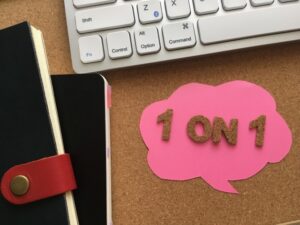
医療機関における「人的資本経営」の実践と好事例
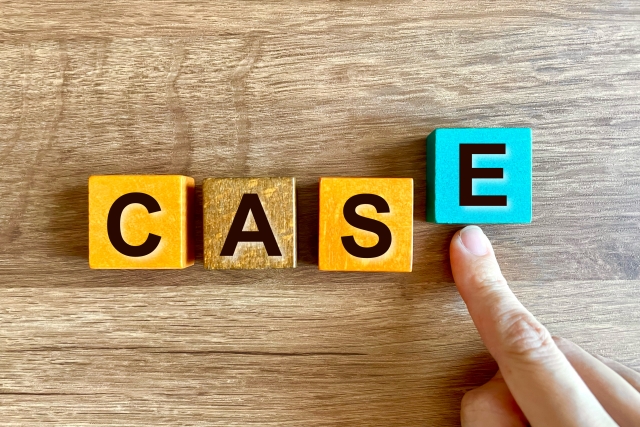
最後に、人的資本経営を具体的に実践している3つの先進事例を紹介します。
1. 日本初の挑戦:医療法人による「人的資本の可視化」
【事例1】医療法人mirai さいわいデンタルクリニック(北海道北広島市)
医療業界でいち早く「ISO30414(人的資本情報開示の国際標準)」に準拠した情報開示(People Fact Book)を行った事例です。
- 取り組み概要:
「人を大切にする」という抽象的な理念を、離職率、研修投資額、多様性といった具体的な指標として数値化し、社外に公開。 - ポイント:
情報開示によって、採用候補者やエージェントからの信頼が向上。
「この法人は自分たちをどう育て、守ってくれるのか」が可視化されたことで、結果的に採用コストの削減と人材の質の向上を実現。 - 専門家の視点:
中小規模のクリニックであれば、いきなり国際規格を目指す必要はありません。
まずは「当院の平均勤続年数」や「年間研修時間」などを採用サイトで公開することから始めるだけでも、十分な差別化になるでしょう。
参考:医療法人miraiさいわいデンタルクリニック ISO30414 2回目の情報開示 | 医療法人miraiさいわいデンタルクリニックのプレスリリース
2. 「自己犠牲」から「ウェルビーイング」への転換:オンライン相談窓口導入
【事例2】特定医療法人 南山会 峡西病院(山梨県南アルプス市)
「医療の質は、職員の心身の健康に支えられる」という信念のもと、外部のメンタルケア体制を構築した事例です。
- 取り組み概要:
現場に根付く「自己犠牲は美徳」という価値観を打破するため、第三者に気軽に相談できる環境(オンライン相談窓口)を整備。
理事長自らが「職員の健康維持は、持続可能な医療提供のための『投資』である」と明言。 - ポイント:
心理的安全性が高まったことで、離職防止だけでなく、現場からの改善提案が活発になるという副次的な効果も生まれた。 - 専門家の視点:
医療現場のストレスは特殊です。
直接上司には言えない悩みを受け止める「外部の目」を持つことは、組織の風通しを良くし、離職という最大の損失を防ぐ賢明な投資と言えます。
参考:「自己犠牲は美徳」からの脱却。Smart相談室がサポートする特定医療法人 南山会 峡西病院の人的資本経営。 | Smart相談室
医療現場において心理的安全性を確保することは、医療提供の安全性を維持するとともに、人材確保の効果も期待できます。以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。
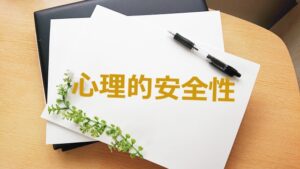
3. 変化に対応する「人材像」の再定義:ヘルスケアの変革を支える戦略的人事
【事例3】塩野義製薬株式会社(大阪府大阪市)
製薬会社の事例ですが、その考え方やエッセンスは「変革を迫られている医療機関」にも共通します。
- 取り組み概要:
従来の「薬を作る会社」から「ヘルスケアサービスを提供する会社」への転換に伴い、必要な人材像を再定義。
単なる専門スキルの向上だけでなく、自ら考え行動する「自律型人材」の育成に注力。 - ポイント:
経営戦略(どういうサービスを提供したいか)と人事戦略(そのためにどんなスタッフが必要か)を連動させ、「チャレンジ」と「働きがい」のある職場の実現を目指す。 - 専門家の視点:
経営目標が違えば、育てるべき人材も、評価すべきポイントも変わります。つまり、人的資本経営とは、経営の想いを人が成長する仕組みに変えることなのです。
参考:広島県「人的資本経営事例集~人材への投資が企業の成長に繋がる」563731.pdf
医療スタッフの働きがいをいかに高めて医療機関の価値を高めるか、以下の記事でも解説しています。

本記事のポイントとまとめ
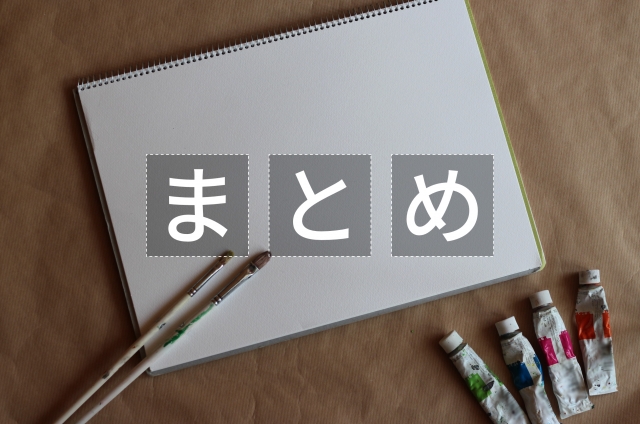
今回は、人的資本経営の考え方や、医療機関が実践する際のポイントについて解説しました。
最後に、「人材版伊藤レポート」の内容と本記事の内容を簡単にまとめます。
- 「人材版伊藤レポート」では、人的資本経営の理念となる6つの「変革の方向性」を明示した。
- 人材戦略は、「3つの視点」と「5つの共通要素」で考える
- 医療機関が人材戦略を考える際、まず「できること」と「できないこと」を取捨選択する
- 「できること」のなかで優先順位をつける
- 優先順位の上位で、手の付けられそうな項目から着手していく
- 医療機関としては、視点②「As is(現在の姿)-To be(目指すべき姿)ギャップの定量把握」から着手するのが妥当
医療機関においては、2年に1回必ず訪れる診療報酬改定の対応などもあり、中長期を見越した人材戦略の策定が非常に困難であることは事実としてあるでしょう。
しかし、常に身構えて何もしないでいるより、ひとまずできそうな取り組みから着手して徐々に進めていくことが、今後の病院運営に望まれる方策だと考えます。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。








