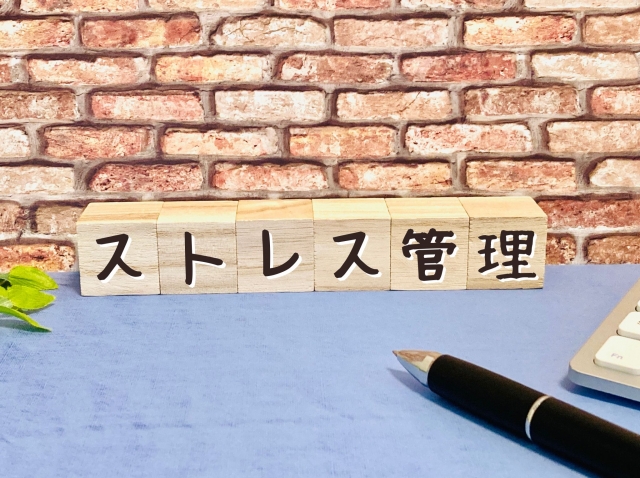日本はストレス社会の象徴とも言われています。
日本人は和を重んじ、目上の人を敬い、我慢することを美徳としています。そんな日本人の長所が、大人から子供に至るまでストレスを抱えさせる要因になっているのかも知れません。
「ストレスとうまく付き合っていく」、とも言われがちですが、実際、世の中にはメンタル不調を抱える人が増加傾向にあるようです。
医療従事者は特にストレスを抱えやすい職種と言えます。中でも看護師は、一人に係る仕事量が多いことに加え、自身で仕事のコントロールがしづらいという業務の特性上、精神的なストレスがかかりやすいと言われています。
今回は、看護師に対するストレスマネジメントの重要性と、医療機関が講ずべき対策について考えたいと思います。
ストレスの正体を知る
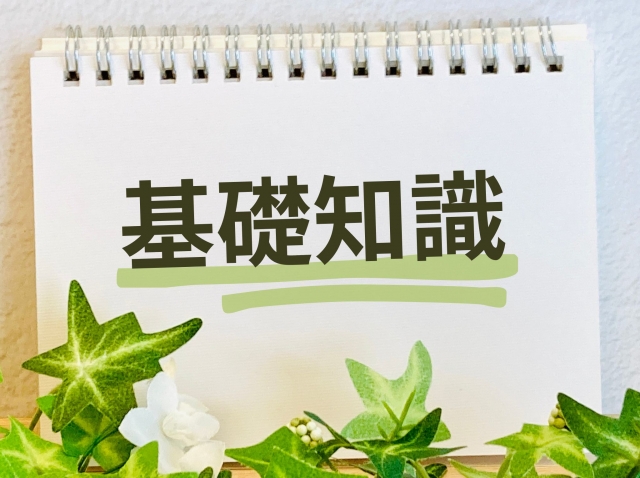
医療従事者にとってストレスマネジメントは、自身が働いていくうえでの重要課題となります。その重要課題を克服するには、ストレスの正体を正しく知る必要があります。
始めに、ストレスの基礎知識について解説していきたいと思います。
ストレスとは?
厚生労働省のe-ヘルスネットによると、ストレスとは、「外部からの刺激などによって体の内部に生じる反応のこと」を言います。
そのストレスの原因となる外部の刺激のことを「ストレッサー」と呼びます。
ストレッサーには、
- 暑さや寒さ
- 睡眠不足
- 職場や家庭での不安や怒り
などがあります。
ストレスは、ストレッサーによる非常事態に備えるための「からだの防衛反応」と言えます。ストレスを過剰に受けると、心身に症状や兆候が現れます。それらの兆候が示されたら早めの対応が必要になります。
| 身体的症状 | 心理的症状 |
| 頭痛 腹痛 不眠 食欲不振 円形脱毛症 | 不安 恐怖 抑うつ |
ストレス・コーピングとは?
ストレス・コーピングとは、ストレス反応を低減、もしくは現状より増大するのを防ぐことを言います。
「コーピング」には「対処」という意味があります。ストレスマネジメントは、ストレスをため込まずに適切に管理するための方法であり、ストレス・コーピングは、その中の具体的なストレッサーへの対処方略のことを言います。
ストレス・コーピングには、大きく分けて2つの方法があります。
- 問題焦点型コーピング
ストレスの原因自体と直接向き合い、解決策を考え実行に移していくもの。
(例)セミナーで解決策を学ぶことなど - 情動焦点型コーピング
ストレスからくる情動的苦痛を弱めて、解消していくもの。
(例)友達に話して楽になることなど
ストレスの対処に必要な「3つのR」
ストレス反応が生じた場合、一般的に以下の「3つのR」が必要とされています。
- Rest(休養・睡眠・安静)
- Relaxation(リラックス・気晴らし)
- Recreation(趣味・娯楽活動)
もし、何らかのストレッサーによって先ほど紹介した身体的症状や心理的症状が現れたら、この「3つのR」を意識して実行することが大事になります。
ストレスを対処するポイントは「質より量」
カウンセラーの岩崎久志氏は著書のなかで、
「ストレス・コーピングは同時に複数使われることがあり、どれが良いというものではありません。」
と伝えています。
そして、ストレス・コーピングのポイントとして以下のことを伝えています。
- 「あまり大げさに考えないで色々試してみる」
- 「気分転換できる為のツールを身近に用意しておく」
- 「大事なのは質より量」
参考:岩崎久志著「ストレスとともに働く」(晃洋書房)
看護師業務に伴うストレスの主な原因

看護師が抱えるストレスの原因は、具体的にどこにあるのでしょうか。
ここでは、日本医療労働組合連合会の『2022年看護職員の労働実態調査「報告書」』のデータをもとに、看護師のストレスの原因について考えていきたいと思います。
なお、業務上の過度なストレスによる医療従事者の精神障害と同報告書のデータの詳細については、以下の記事で具体的に掲載しています。併せてご参考ください。

原因①:長時間労働
看護師は常に人手不足の職種なので、勤務中は時間に追われるため、1人当たりの仕事量が多く、時間外勤務が多いことがストレスの原因になっています。
日本医療労働組合連合会がまとめた『2022年看護職員の労働実態調査「報告書」』によると、
という調査結果が示されています。
原因②:交代制勤務
看護師の働き方は交代制勤務が多いため、生活が不規則になることもストレスの要因になります。
前掲した日本医療労働組合連合会の「報告書」によると、
という調査結果が示されています。
原因③:患者やその家族との関わり
患者やその家族から過度な要求や、威圧的な態度を取られることが看護師のストレスの原因になっています。
前掲した日本医療労働組合連合会の「報告書」によると、
という調査結果が示されています。また、
との調査結果も示されています。これは、ベテラン層や師長などの管理職が患者や家族のクレームに対応をする機会が多いことを示しています。
医療機関の管理職へのストレス対策については、以下の記事で詳しく解説しています。是非ご参考ください。

原因④:職場の人間関係
看護師同士の人間関係であったり、医師や他職種との人間関係がストレスの原因になっています。
前掲した日本医療労働組合連合会の「報告書」によると、
となっています。
医療機関では多職種連携により業務が進みますが、その中でも特に患者との関わりがより深くなるのは看護師です。一人の患者対応について、医師などとの関わりも含めて、看護師に精神的な負担がより一層かかっていることが背景として考えられます。
原因⑤:高い責任感とプレッシャー
人命に関る看護師という仕事そのものに対する責任感と、それによるプレッシャーがストレスの原因になります。
前掲した日本医療労働組合連合会の「報告書」によると、
となっています。
また、人手不足により業務が過重となり、自分が望む看護の提供ができないというジレンマもストレス要因に含まれるかもしれません。
ストレスマネジメントの方法

ここまで、医療現場におけるストレス要因についてみてきました。
それでは、実際に私たちがストレスを感じたとき、どのような対処を考えるべきなのでしょうか。
メンタルヘルスの4つのケア
ここでは、厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示す4つのケアについて取り上げたいと思います。
なお、④にあるEAPは、従業員が自分の悩みを職場の人に知られずに専門家に相談できる仕組みで、近年導入する企業が増えてきているようです。
| ①セルフケア | 労働者が、自身のストレスのことを知り、予防や対処を行い、健康の保持増進に努めること |
| ②ラインによるケア | 職場の管理職が、職場環境の改善や従業員のメンタル不全の気づき相談を行い、産業医との連携を図ること |
| ③事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 職場の産業医などの健康管理室が、随時の相談や職場復帰の判定を行うこと |
| ④事業場外資源によるケア | 職場外の専門機関から、メンタルヘルスの支援を受けること (例)EAP(従業員支援プログラム)など |
セルフケアがストレス対策の第一歩
ストレス対策には4つのケアがありますが、まずは、自分自身が行うセルフケアがストレス対策の第一歩となります。
組織任せにせずに、自身でストレスに気づき、コーピングの方法を得て、過重労働やメンタル不調にならないような心掛けが大事です。
厚生労働省が運営する「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」に、セルフケアの具体的な方法が掲載されていますので紹介します。
- リラクセーション
- ストレッチ
- 適度な運動
- 快適な睡眠
- 親しい人たちと交流
- 笑う
- 仕事から離れた趣味を持つ
医療機関が考えるべき看護師のストレスマネジメント
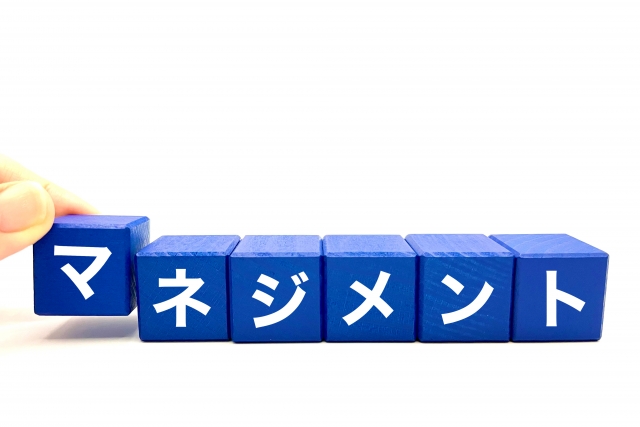
医療現場の約半数を占める看護師のストレスマネジメントは、医療機関にとって積極的に推進していくべき重要課題となります。
ここでは、医療機関が職場の看護師に対してどのようにストレスマネジメントを実践していくのか、その方策について考えていきたいと思います。
①相談窓口や支援体制の充実
院内の支援体制を充実させることは、医療機関が始めに考えなければならないことです。
メンター制度やEAP(従業員支援プログラム)を導入することで、早期にスタッフが抱える悩みを軽減することができます。
また、メンタルヘルス研修を定期的に実施することで、自分を大切にしながら働くことの重要性やセルフケアの方法をスタッフに啓蒙することができます。その際には、自院の支援体制に関するアナウンスを繰り返し行い、積極的な制度利用を促していきます。
前述した厚生労働省による4つのケアのうち、「②ラインによるケア」と「④事業場外資源によるケア」(EAP)については、以下の2つの記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。


②業務量の軽減
看護師がストレスの原因として最も多く挙げるのが、「仕事量の問題」です。
人手不足が看護師のストレスの原因であれば、まずは人材確保から、というのが医療機関が考えるべき根本的なストレス対処の方策となります。
長時間労働を強いることがないよう必要数を配置し、働きやすい職場にして離職防止を図ることが医療機関としての責務です。
また、業務の生産性を高めて、時間外労働を減らす努力も必要です。上から超過勤務の抑制を求めるのではなく、スタッフレベルで工夫して徐々に減らしていけるよう促すことが大事になります。
以下の記事では、医療機関における労働生産性向上のきっかけについて考察しています。併せてご参考ください。

③コミュニケーションの活性化
「職場の人間関係」が看護師のストレス要因として上位に挙げられます。
上司や同僚との関係、医師との関係のこじれが多くの看護師が抱えるストレスの原因になっていると想像できます。
上司との関係で言うと、日頃からの声掛けや、定期面談、1on1をとおしてスタッフの声に耳を傾ける必要があります。
職場内コミュニケ―ションを活発に取り、心理的安全性を高めることも重要です。
また、医師などの他職種に向けて看護師の仕事を理解してもらう取組も重要になります。例えば自部署のメンバー紹介から業務内容、取り組んでいることなどを院内報などで発信することもひとつの方法と言えるでしょう。
医療機関における1on1の導入方法や心理的安全性の確保の方策については、以下の2つの記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
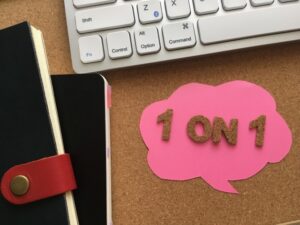
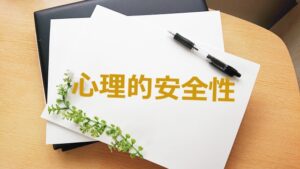
④キャリア支援の充実
「仕事への適正の問題」も看護師のストレス要因として上位に挙げられます。
定期面談では、上司とスタッフ本人が共にキャリアの方向性をつくるという気持ちが大事になります。それには、スタッフ一人一人の声に耳を傾け、スタッフ自身が考えるキャリアの志向を汲み上げる必要があります。
管理職ともなると現場対応もマネジメント業務もともに忙しく、面談の時間もなかなか取れないと思います。しかし、一人のスタッフのストレスは他のスタッフにも影響しやすいため、まずは一人一人と向き合う時間を大切にすることが大事になります。
看護師のキャリアプランの考え方について、以下の記事で解説していますので是非ご参考ください。
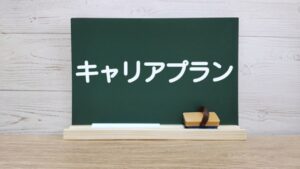
成功事例に学ぶストレスマネジメントの取り組み
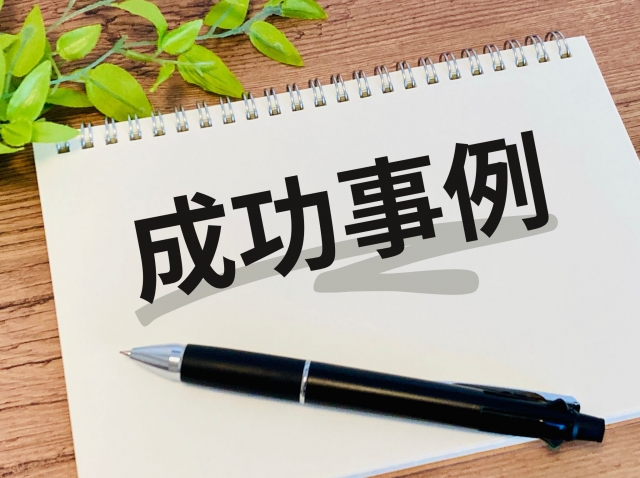
最後に、メンタルヘルスに関する医療機関の取組事例が厚生労働省が運営するサイト「いきさぽ」に掲載されていますので、紹介したいと思います。
- 事例病院
大阪市立総合医療センター(大阪府大阪市・975床) - テーマ
「院内健康管理室での心理相談の周知と実施」 - 取組内容
①「心の健康づくり計画」を策定し、組織的・計画的にメンタルヘルス対策の取組を行っている。
・医療安全ポケットマニュアル(冊子)に健康管理室での健康相談の案内を記載して職員全員に周知している。
・年2回、全国安全週間と全国労働衛生週間のテーマの一つとして健康管理室での心理相談の案内のリーフレットを職員全員に配布し、周知している。
②健康診断の事後措置(医療上の措置、就業上の措置、保健指導等)を実施している。
・職員本人またはその上司の希望、依頼があれば健康管理室での心理相談に応じている。
・定期健康診断の事後措置の一つとして、自覚症状に関する問診票で抑うつのチェック項目に〇を付けた職員に対して、健康管理室での面談を実施している。 - 実施後の成果
・職員本人からだけでなくむしろ部署責任者(職員本人の上司に当たる)からの相談や連絡が増えて健康管理室の保健師に日常的に面談依頼が入るようになり、相談件数が増えてきている。
・看護師の相談件数が多く、2018年度は全体の71%を占めているが、その理由は職員数が最も多いだけでなく業務の繁忙度の高さとコントロール度の低さ等によるストレス度の高さが関係している。
ストレスマネジメントは、医療従事者個人のセルフケアとして重要ですが、本来は組織として支援体制を整えることが欠かせません。
医療機関が職員のメンタルヘルスにどう向き合うべきか、安全配慮義務の観点から整理した内容は、以下の記事で体系的にまとめています。

まとめ

ここまで、看護師に対するストレスマネジメントの重要性と、医療機関が講ずべき対策について考えてきました。
最後に、先ほど掲げた医療機関が考えるべき看護師のストレスマネジメント対策4点をまとめたいと思います。
- 相談窓口や支援体制の充実
- 業務量の軽減
- コミュニケーションの活性化
- キャリア支援の充実
前掲した日本医療労働組合連合会の報告書から、医療従事者の中でも、特に看護師は日常の業務自体からストレスを抱えやすい職種だということがわかりました。
看護師としては、何より自分を大切にすること、セルフケアの知識を取り入れ、積極的に職場の支援制度を活用し、心の健康を保ちながら働いていくことが重要になります。
医療機関としては、まずは人材確保が急務となりますが、院内の支援制度を充実させながら、より働きやすい職場環境を整備して、看護師の長期的なキャリア形成を支援していくことが重要です。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。