皆さんは、新NISAを活用していますか?
新NISA制度は2024年初頭から始まり、日本の株式市場を盛り上げるひとつのきっかけになりました。
私たち現役世代が上手に活用すべきものとして、財形貯蓄やiDeCo(イデコ)といった制度が挙げられます。
しかし、世間の話題は、どちらかと言うと新NISAのことばかりです。一体この新NISAとは、どんな制度なのでしょうか。
今回は、新NISAの制度内容やメリット、デメリット、利用するうえでの注意点などについて解説していきたいと思います。
NISA制度大幅改正の背景にあるものとは
この新NISAですが、当時の岸田政権が掲げる資産所得倍増プランの一環として、2024年に大改正が行われました。
これにより、旧NISA制度と比べ、利用者の利便性が格段に上がりました。
はじめに、NISA制度大幅改正の背景には何があるのか解説したいと思います。
「貯蓄から投資へ」
「貯蓄から投資へ」
よく耳にしたフレーズですが、ここには、国民の財布の中で眠らせているお金を投資に回させて、国民と経済全体を豊かにしたい、という国の思惑があります。
昔は、限られた富裕層だけが投資に参加してましたが、今はスマホひとつで投資ができる時代です。
今後は、大多数を占める中間層を投資に参加させ、幅広い層が資産を増やせる仕組みを作ることが重要であると国は考えました。
つまり、投資で得られる儲けに対して税金は取らない、というNISA制度の仕組みを大幅に拡充したというのが今回の制度改正の背景になります。
自己責任で老後資金をつくる時代に
国は、使い勝手の悪かった従来のNISA制度を大幅に改正し、私たちに老後に向けた資産形成をするよう後押ししています。
その裏には、少子高齢化が急速に進展するなか、公的年金だけに頼らず、自己責任で老後資金をつくるよう国が暗示しているかのように思えます。
新NISA制度の特徴とは

ここでは、新NISA制度の特徴について押さえておきたいと思います。
以下の6点が新NISA制度の特徴です。
- 日本に住む18歳以上が対象
- 投資期間の恒久化
- 非課税期間は無期限
- 年間の非課税枠が拡大
- 生涯投資枠は1,800万円
- 投資対象は元本割れリスクがある商品のみ
それぞれ解説していきます。
特徴➊:日本に住む18歳以上が対象
日本に住む18歳以上であれば誰でも利用できます。
これにより、若いうちから将来のライフイベントに向けて、計画的に資産形成ができます。
特徴➋:投資期間の恒久化
旧NISAは時限的な制度でしたが、新NISAは制度自体が恒久化されました。
これにより、どの時点からでも安心して長期的な資産形成を始めることができるようになりました。
特徴➌:非課税期間は無期限
旧NISA制度では、
- 「一般NISA」5年
- 「つみたてNISA」20年
という期間限定のルールがありました。
しかし、新制度では、非課税期間が無期限となりました。
原則は利子に対して一律20.315%の源泉分離課税が適用されるところ、その分が非課税となるため、非課税メリットを一生涯受けながら、じっくりと効率的に資産を増やすことができるようになりました。
特徴❹:年間の非課税枠が拡大
旧NISA制度では、
- 「一般NISA」120万円
- 「つみたてNISA」40万円
の年間非課税枠の上限設定があり、この2つは併用できませんでした。
しかし、新NISA制度では、
- 「つみたて投資枠」120万円
- 「成長投資枠」240万円
の合計360万円まで年間の非課税枠の上限が拡大されました。
さらに、新NISA制度では「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの投資枠の併用ができるようになりました。
年間非課税枠の上限金額の拡大や、投資枠の併用ができることにより、資産形成の強力な後押しとなりました。
特徴❺:生涯投資枠は1,800万円
旧NISA制度では、
- 「つみたてNISA」最大20年間×40万円=800万円
までが投資枠の上限でした。
しかし、新NISA制度では、
- 「生涯投資枠」1,800万円
- このうち「成長投資枠」は1,200万円
と投資枠の上限が拡大しました。
投資元本だけで1,800万円確保できれば、追加の老後資金として安心感を得られるでしょう。
特徴❻:投資対象は元本割れリスクがある商品のみ
投資対象は、元本割れリスクのある商品のみで構成されています。つみたて投資枠と成長投資枠で、それぞれ商品設定がされています。
- つみたて投資枠の商品は…
金融庁が選定した長期投資に適した商品で構成されています。2025年3月6日時点で319本のラインナップがあります。 - 成長投資枠の商品は…
一定の共通条件を満たしていれば、取り扱う金融機関で設定できます。価格変動の激しい商品や、販売手数料の高い商品も含まれます。
つみたて投資枠であるか成長投資枠であるかに関わらず、制度を利用する際には、投資対象の選定が極めて重要になることを念頭に置く必要があります。
新NISAのメリットやデメリット、注意点

ここでは、新NISAのメリットやデメリット、注意点に解説したいと思います。
新NISAのメリット3つ
まず、新NISAのメリットとして3点挙げたいと思います。
- 運用益が出ても課税されない
- 非課税の上限額まで売買を繰り返せる
- 長期積立投資に最適
以下、解説していきます。
メリット➊:運用益が出ても課税されない
配当や売却時に得られた利益があっても、一切課税されません。これがNISA制度の最大のメリットです。
そのため、積極的に投資に参加することができますし、何より効率的に資産を増やすことが可能になります。
メリット➋:非課税の上限額まで売買を繰り返せる
旧制度にはなかった「投資枠の復活」ができるようになりました。
このおかげで、非課税の上限額まで商品の売買を繰り返すことができ、より柔軟に資産の最大化を図りやすくなりました。
【例】NISA口座で10,000円分購入した商品が値下がりしそうなときを考えてみます。
- 旧NISA制度では…
10,000円分全て売却した場合、10,000円分少ない投資枠でそのまま運用を続けなければなりませんでした。 - 新NISA制度では…
10,000円分全て売却したとしても、その翌年には10,000円分の投資枠は復活し、また別の値上がりしそうな商品を10,000円分買うことができるようになりました。
メリット➌:長期積立投資に最適
投資期間の恒久化や、非課税期間の無期限化により、非課税メリットを長期間享受しながら、じっくり資産形成を行える環境が整いました。
投資で結果が得やすい長期積立投資を新NISAで実践していくことで、老後資金の確保がかなり現実的なものとなりました。
新NISAのデメリット3つ
次に、新NISAのデメリットを3点挙げたいと思います。
- 元本割れするリスクがある
- 利益が出ないと非課税メリットが受けられない
- 他の口座との損益通算ができない
以下、解説していきます。
デメリット➊:元本割れするリスクがある
イデコと異なり、預貯金などの元本保証型の商品が選べません。常に価格変動リスクにさらされ、元本割れする可能性があります。
自身のリスク許容度に応じて、運用することが求められます。
デメリット➋:利益が出ないと非課税メリットが受けられない
運用上の利益が出ない限り、NISA制度の最大のメリットである非課税の恩恵が受けられません。
NISA制度の非課税メリットを最大限に発揮するには、より多くの利益が見込める商品を購入することがカギになります。
デメリット➌:他の口座との損益通算ができない
これは所得税の計算上の話で、NISA口座で損失が出た場合は他口座と損益通算できないため、税金を安く抑えられないというデメリットがあります。
【例】AとBの2つの口座を持っている場合を考えてみます。
- A、BともにNISA口座以外の課税口座のケースでは…
A口座で10,000円の利益が出たものの、B口座で7,000円の損失が生じた場合、通常はAとBで損益通算して3,000円の利益として、所得税の計算ができます。
⇒損益通算した利益3,000円×20%=600円、の税金となります。 - Aが課税口座、BがNISA口座のケースでは…
もしBがNISA口座となると、7,000円の損失が出たとしても、Aの課税口座との損益通算ができません。
⇒A口座の利益10,000円×20%=2,000円、の税金となってしまいます。 - その結果、損益通算できたケースの600円と比べると、1,400円も多く税金を納めないといけません。(※ここでは説明を簡略化するため、税金の掛け率を20%として計算しています)
新NISAの注意点3つ

ここでは、新NISA制度の注意点を3点挙げたいと思います。
- 商品選定や運用のための勉強が必要
- 目的を明確にして長期運用を心掛ける
- 公的年金・イデコ・NISA等の活用を総合的に考える
以下、解説します。
注意点➊:商品選定や運用のための勉強が必要
つみたて投資枠で約300本、成長投資枠に至っては2,000本以上の商品があります。そこから商品を選んで購入し、運用し続けるには、投資に関する相当の勉強が必要です。
投資で成果を上げて、資産を築いていくためには、世界経済の情勢から投資におけるリスクとリターンの関係、運用中の成績や手数料の安さなどの商品に関する情報まで、常に勉強し続けることが重要になります。
注意点➋:目的を明確にして長期運用を心掛ける
新NISA制度では、売却してもその翌年には投資枠の復活ができるようになりました。
旧制度では、一度売却したらその枠は消滅していましたので、より柔軟に資産形成をすることができるようになりました。
しかし、裏を返すと、1年前後の短期投資もできてしまうため、投資効果の得やすい長期投資から外れる行動を取りがちになります。
資産形成の目的を明確に持って、長期目線で運用を心掛けることが、豊かな投資につながると思います。
注意点➌:公的年金・イデコ・NISA等の活用を総合的に考える
新NISAは、元本だけでも1,800万円の資産形成ができる制度です。投資枠上限まで入金できれば、老後資金に安心感を与えることができます。
しかし、NISAの他にも公的年金やイデコといった私的年金の制度があります。
老後に受け取るはずである公私の年金を含め、自身が必要とする収入と支出のバランスを総合的に考えて、NISA制度の活用を考える必要があります。
資産は多いに越したことはありませんが、人生には限りがあります。
資産の取り崩しをどの時点から始め、どのくらいの金額を取り崩していくのか。
このような出口戦略を考慮する必要もあります。
以下の記事では、iDeCo(イデコ)のメリットとデメリットなどについて解説していますので、併せてご参考ください。

もっと早くから資産運用を始めたかった…
筆者は長らく医療機関に勤めてきましたが、30代中頃まではほぼ無計画に給料を使っていました。
40歳に近づくにつれ、ようやく自分のお金と向き合うようになり、その時期から生命保険の見直しをしたり、資産運用を始めたりしました。
旧制度から、NISAも活用して運用を続けています。今までの使いづらさが嘘だったかのように、新NISAでは資産の最大化が格段に期待できるようになりました。
もっと早くから資産運用を行うべきだったと、今さらながらに思います。
自身のお金と向き合う時間を
日々の業務の忙しさから、気にしないうちに時間がそのまま流れていっている人も少なくないと思います。
しかし、一旦自身のお金のことと向き合う時間を取ることを、強くおすすめしたいと思います。
投資は、長期で行うほど利益が得られる確立が高いことは、よく知られていることです。
若い世代はもちろんのこと、ベテラン世代でも遅いことはありません。
NISAは少額からでも利用可能ですので、ここで利用の検討をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、新NISAの制度内容やメリットやデメリット、注意点などについて解説してきました。
投資初心者にとっては、投資は怖いものと、なかなか踏み出せずにいる人もたくさんいると思います。
元本割れが怖く、安全かつ着実に資産形成をしていきたい人は、以下の手順でじっくり資産づくりについて考えていくことをおすすめします。
- 職場の財形制度を利用して、安心安全に貯蓄を進めていく
- ある程度資金が貯まり、心に若干の余裕ができた段階で、イデコも追加して本格的な資産運用開始
- ①と②で金融リテラシーが上がったところで、さらに新NISAで追加運用し、資産の最大化を目指す
これらにより、職場においては、経済的な自立が近づき、自律的なキャリア形成が可能になります。
そして、人生の選択肢を確実に増やすことができるようになるのです。
なお、以下の2つの記事では、財形制度のメリット・デメリットについて、また、金融リテラシーと従業員エンゲージメントの関係性について解説しています。併せてご参考ください。
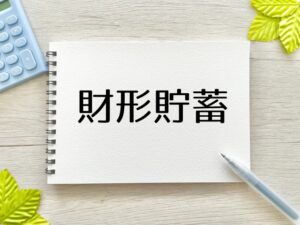

今回の記事が、少しでも何かのお役に立てば幸いです。
参考:田村正之「間違いだらけの新NISA・イデコ活用術」(日本経済新聞出版)








